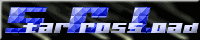――黒き神を呼覚ます事莫れ。
――決して世に解き放ってはならぬ。
――其は残虐なる破壊の神にして、人々の恐れや憎しみの具現なれば。
黒き神の伝承歌
昔々、或る所にとても寒い気候の国がありました。
元々北の方にある国なので、冬ともなると其の寒さは猛烈でした。
川も海も凍り付き、毎日、雪が降って辺り一面が白い世界です。
白い世界はとても美しいですが、人間が住むには大変な国です。
そんな永久凍土が大半を占める小国に、ある日突然沢山の軍隊が押し寄せました。
ずっとずっと南の方の新興の王国が、凄い勢いで世界を侵略していたのです。
此方は人々が暮らしていくだけでやっとの国です。
こんな小国を手に入れても、一体何の得があるのでしょう?
領主は悩みました。
すると新興の王国の使者は要求を突き付けて来ました。
「黒き神チェルノボグの壷を引き渡すのだ。さもなければこの小国を蹂躙し、お前達は全員生き埋めにしてやるぞ!」
領主には何の事かさっぱり分かりません。
でも彼らの要求を飲まなければ、この国は滅亡してしまうでしょう。
国を挙げて「チェルノボグ」の伝承を調べさせました。
しかし、そんなものは全く見当たりません。
領主はいよいよ困り果てました。
するとある若い男が領主に進言しました。
「沢山の頑丈な壷を作って下さい。私に考えがあります」
男は世界中を旅していました。
そして新興の王国が血眼になって魔神を集めている事を知っていました。
そして、今回の侵略に参加しているのは将軍達だけで、国王自身は赴いていない事を知っていたのです。
小国相手にわざわざ魔神を使役して戦いを挑む必要など無いという奢りの為でした。
男は沢山の鋼鉄の壷の全てに鉛を流し込み、蓋が開かないように閉じてしまいます。
そして、侵略者達に言いました。
「さあ、この壷全てがチェルノボグだ。好きなだけ持って帰るがいい!」
将軍達は全ての壷を持ち帰るように厳命されていました。
魔神の壷は全て国王自身の手で開封し、契約を結ばなければならなかったのです。
でも、鉛の入った壷など重過ぎて運ぶのは一苦労です。
沢山の馬車や荷車を使いましたが、其れでも足りない分は食料を降ろし、壷を載せました。
そして、軍隊は引き上げて行きます。
すると、程なく冬がやって来ました。
鉛入りの壷の重さのせいで、馬車は轍に嵌まり込み、中々進めません。
食料はたちまち底を尽きました。
其処に白い悪魔と呼ばれる猛吹雪が荒れ狂います。
雪の恐ろしさを知らない、南方の軍隊は、忽ち立ち往生してしまいました。
そして春が来て…
小さな雪国の人々が見たのは、氷漬けになった軍隊のなれの果て…
彼らは将軍達諸共、雪の中で力尽き、全滅していました。
領主は国を救った男に褒美を取らせようとします。
「お前が欲しい物を言うが良い」
すると男は言いました。
「私にこの壷を下さい」
最後に残った一つの鋼鉄の壷。
領主はもっと高価な宝物を勧めましたが、男は満足そうに其の壷を持ち帰りました。
…数日後。
男が壷を開けると、不思議な格好をしたお姉さんが飛び出して来ました。
「あたしはカーミラ、よろしくねぇ!」
魔神は人の願いから生まれるもの。
だから何の変哲も無い壷も、もしかすると何時の日か魔神の壷に変わるかも…。
「――おしまい、っとぉ」
結びの言葉を書き込んで、あたしは筆を置いた。
こんなに長い時間書き物をしたのは随分と久しぶりの事だ。
こきこきと首を鳴らし、肩を回しながら、んっ…と大きく伸びをする。
窓の無い薄暗い部屋、手が触れてしまいそうな低い天井。
あたしの館は、その昔、マスターと一緒に暮らしていた、あの北の国の小さな家を模して建てられている。
部屋の温度を外に逃がさないようにする為に。
圧し掛かる雪の重みで屋根が落ちてしまわないように。
……それと、あたしがお日様の光を苦手としているからって理由もあったりする。
ま、黒の神、チェルノボグだもんねぇ。
別に灰になっちゃったりとかはしないけどさぁ、何かだるだる〜って感じになっちゃうんだよぉ。
「はぁーぁ、退屈だなぁ。イリスちゃん、今日も遊びに来ないかなぁ」
意外かも知れないけど、あたし達の時間感覚って、人間のと変わりは無いんだよぉ。
暇な時、あたしは書き物をしたり、集めている古銭の整理をしたり、新しい魔導具を作成したりして時間を潰しているけれど、
……やっぱり、人恋しくなっちゃったりもするんだよぉ、うん。
壁際に二つ並べてある棚を、ゴソゴソと漁ってみたり。
「……ぉ。三年前に漬けたハーブ酒が出来上がってる。やりぃ♪」
綺麗な薄緑色、仕上がりは上々。
イリスちゃんと一緒に漬けたんだから、巧く出来てて当然なんだけどねぇ。
ニガヨモギを漬け込んで造るアブサン酒、微妙に神経系統が侵されちゃったりなんかするので、人間にはお勧め出来ない。
栓を抜くと同時に部屋の中に広がる、仄かな芳香。
酒盃代わりに使っている吹き口を塞いだ角笛をいそいそと取り出して、溢れ出しちゃうぎりぎりの線まで、酒瓶の中身をなみなみと注ぎ入れる。
くいっ、と一息に呷る。
舌がピリピリして、咽がかぁっと熱くなる。
実はあたし、お酒の味自体はあんまり好きじゃないんだよぉ。
苦い、ってゆーか、痛くない?
段々と酔っ払って来て、頭がふりゃふりゃ〜ってなる感覚が好きで飲んでるだけなんだよねぇ。
こう見えてあたし、昔はすんごい下戸だったの。
マスターがお酒とか好きな人でさ、何時も美味しそうに飲んでるものだから、興味が涌いて来ちゃって。
じぃーっと見てたら、「あ、カーミラも一緒に飲む?」なぁんて、コップにてんこ盛りで注いでくれたのが九十度数軽く超えちゃうような火酒でさぁ。
寒い国だったからねぇ。
舌の先っちょでちびっと舐めただけで、椅子ごと引っ繰り返っちゃったよぉ。
たはは……。
初めてのお酒。
とても苦くて、美味しくなかった。
みんな、どうしてそんなに美味しそうに飲めるのか、不思議で仕様が無かった。
今なら、少しは分かるよ。
嫌な事とか、悲しい事とか、寂しい事だって、全部忘れてしまえるもの。
マスターは「楽しいお酒じゃないと駄目だよ」……って、何時も言ってたけどね。
銘柄は何だったかなぁ、もう、忘れちゃったよ。
暖炉の火に照らされて、あたしとマスターの影だけが、小さな部屋の中で踊ってた。
とても静かな、北の国の冬。
あたしが壷から出て来てから、一年が経過しようとしていた頃の話。
いけないんだぁ、マスター。
あたし、まだ一歳になってなかったんだよねぇ。
お酒は十八歳から、ってみんな言ってるよぉ。
マスターは笑って、あたしの頭を撫でてくれた。
小さな花の画が描かれた、白い陶器のコップだった。
ちゃんと、覚えてる。
生まれて初めて飲んだお酒。
マスターの唇が触れたその器から、………
「……どうしたの、カーミラ。飲まないの?」
「ぇぁっ!?の、飲むよ、飲みます、飲ませていただきますっ!」
ぁ〜、その、うん。
……あたし、飲む前から完全に酔っ払ってた。
そっと、口を付けて、琥珀色の液体を口に含む。
苦くて熱い液体が、あたしの咽から胸へと通り過ぎて行く。
「うぇっ、けほっ、けほ……」
「大丈夫かい、カーミラ」
「マスタぁー、これ、全っ然美味しくないよぉ」
「うーん、カーミラにはちょっと早過ぎたかな……?」
「むぅ〜。これ、返す」
半分くらい中身が残っているコップを返そうと立ち上がった途端、世界が揺れた。
天井がぐるりと廻り、目の前が一気に昏くなっていく。
カシャーン。
陶の器の割れる音。
「……ラ!」「…−ミ…」
何処か遠い処から、マスターがあたしを呼ぶ声が聞こえたような気がした。
……あたしが目を覚ましたのは、次の日。
太陽が空の頂きに届こうとしている頃だった。
頭が重い。
あたしは、吐き戻したらしい。
服を着替えさせられて、マスターのベッドに寝かされていた。
目を開くと、心配そうな表情であたしを見下ろすマスターの顔。
其の右手には、血に染まった包帯。
「マスター!?」
「おはよ、カーミラ」
「その腕っ……」
「ん?ああ、平気だよ。ストーブに焚べる薪を割っていたら、跳ねた木片が当たっちゃってね」
マスターは嘘を吐いていた。
あたしは覚えている。
割れたコップの破片の上に倒れ込んだあたしを庇ってくれたマスターの腕の感触を。
あたしは黒き神、チェルノボグ。
人間と違って、歳を取らないし、傷を負っても死んだりしないのに。
不注意でマスターの大切なコップを割ってしまったあたしなんかを庇って、マスターは腕を怪我してしまった。
あのコップは、マスターのお母様の形見で、とても大切にされていた物だ。
「ひぐっ、ふ…ぐっ、ふぇぇっ……ごめ…んなさいっ、ますたぁっ、あたしぃっ、壊しちゃったぁっ、」
「ああ、いいんだよ。酒盃ならまた新しいのを焼けば済むんだから」
「でも…でもっ、ますたぁの腕っ、あたしをっ、庇って……」
泣きじゃくるあたしを、マスターはそっと抱き寄せて、優しく頭を撫でてくれた。
あたしが泣き止むまで、ずっと、ずっと。
「大丈夫だよ、ほんの掠り傷だから。こんなの、直ぐに治るよ」
あたしを不安にさせない、力強い笑顔。
……けれども、マスターの腕は元通りには治らなかった。
陶器の鋭い破片は、マスターの腕の筋や神経を深く傷付けてしまっていた。
あたしは、黒き神チェルノボグ。
人々に不幸を運ぶ、呪われた破壊の神。
全部あたしが悪いんだ。
どうして、あたしは癒しの女神とかじゃ無かったんだろう。
あたしは、マスターに付きっきりで、身の回りのお世話をした。
マスターはあたしに優しかった。
其の優しさが、逆にとても辛かった。
雪に閉ざされた小さな館。
灯火の芯と獣油の燃える臭い。
長い冬の夜更け。
マスターは机に向かって書き物をする。
世界各地を旅して廻って見聞きした事物を書き留めた自伝。
綴るのは、嘗てあたしに読み書きを教えてくれていた頃のものとは違う、拙い文字。
時折、ペンを取り落としては、痛む腕を押えて歯噛みする。
あたしは耐え切れず、家を飛び出した。
全部、全部、あたしが悪いんだ。
あたしが居たから、マスターは怪我をした。
あたしは黒き神、チェルノボグ。
人々に不幸を運ぶ為に生まれて来た存在。
これ以上マスターの傍に居たら、きっと更にマスターを不幸にしてしまう。
それだけは、絶対に、耐えられない。
行く宛など知れず、あたしは猛吹雪の中を彷徨った。
あたしとマスターが過ごした家が、次第に遠ざかって行く。
背後の点景に、そして雪に翳んで消えてしまう。
そして、あたしは白銀の世界に投げ出された。
あたしは、生まれ育ったあの家の外の事は何も知らない。
マスターが聞かせてくれた旅の話は、遠い世界の夢物語のようで。
あたしの居場所は、ずっと、マスターの傍だけだった。
お料理の仕方を教えてくれた。本の読み方を教えてくれた。日記を書く事を教えてくれた。楽器の弾き方を教えてくれた。絵の描き方を教えてくれた。歌を歌う事を教えてくれた。お酒の醸し方を教えてくれた。服の織り方を教えてくれた。糸の紡ぎ方を教えてくれた。草花の種類を教えてくれた。動物の名前を教えてくれた。風の読み方を教えてくれた。空の星座の読み方を教えてくれた。笑い方も、生きる事が幸せだという事も、誰かに愛される喜びも、全部マスターが教えてくれた。
だから、もう、会わない。
そう心に決めて、初めて気付いた。
……あたしは、マスターを愛していた。
雪の山道を走りながら、あたしは泣いていた。
もう、会えない。
マスターに会えないんだ。
冷たい風が、流れ落ちる涙の雫さえも凍り付かせて行く。
嫌だ。
そんなの嫌だよぉ。
「会いたい…会いたいよ……」
駄目。振り向いちゃ駄目。
「でもっ、会いたいよっ」
振り向いてしまったら、きっと。
もう、あたしは、前には進めなくなってしまう。
それなのに……
「……どうして」
踏み締める雪の音。白い息。
嗚呼、どうしてあたしはこんなにも弱いんだろう。
あたしを後ろから優しく抱き留める腕の温もりに全てを委ねて甘えたくなってしまう。
「カーミラ、迎えに来たよ」
「どうして、マスターが此処に居るんですか」
「それを聞きたいのはボクの方だ。こんな吹雪の中、どうして家を飛び出したりなんかしたんだ?」
「……駄目なんです」
搾り出す、たった一言が、重くて、痛くて、苦しくて、あたし自身の胸を切り裂いて行く。
それでも、許される筈が無い。許されて良い筈が無い。
この想いは、きっと、絶対に、許されない。
「あたしは黒き神だから。チェルノボグだから。一緒に居る人に不幸を運ぶ呪われた魔神だから。だからっ――」
「……行くな」
今のマスターの腕の何処にこんな力が残っていたのだろう。
「行くな、カーミラ。ボクは……」
耳元で囁く言葉は、あたしを呪縛する、魅了の魔曲。
とても優しくて、残酷な命令、あたしのマスター。
「君を愛している。ずっと、ずっと君と一緒に居たいんだ!」
見つめる瞳は、燃え上がる炎よりも熱く、あたしを溶かして行く。
拒めない。拒み切れる訳が無い。
あたしの心はとっくの昔に、マスターに囚われてしまっていたのだから。
「帰ろう、一緒に。ボク達の家に……」
――そして、あたしはまた罪を犯す。
幾度となく重ね合わせた唇。
あたしの躯にマスターの指が触れる度に、刻み込まれて行く消えない傷痕。
今でも時折、疼く。
蜜よりも甘い歓喜が忘れられなくて、自分で慰めたりもする。
とても、幸せだった、二人の時間。
永遠を、信じていた。
けれども、終らない幸せなんて存在しないんだって事を、
あたしは思い知らされる事になる。
何時しか冷たい冬も過ぎ去り、暖かな春の日差しが訪れる頃。
北の国の春は、南の国よりも遅くやって来て、あっという間に終ってしまうけれど。
だからこそ、北の国の人達は、春の訪れを一層大きな幸せとして待ち望む。
白い悪魔が居る間、外に出られなかった分、太陽の光の下で精一杯背伸びして、野に咲く草花を愛でたり、雪解け水のせせらぎや鳥の歌声に耳を澄ませたりして。
そんな麗らかな春先の或る日の事。
国境に駐留する防衛部隊から、南の国の軍隊が再び攻めて来た事が知らされた。
前回の侵攻時にも勝る大軍を引き連れて、更に今度は、幾柱もの魔神を従える南の国の王自身が直々に軍を率いて来ているとの報告を受けて、北の国は天と地が入れ替わり永久凍土が溶け出したかのような大騒ぎになった。
ある者は言った。
「何という事だ、ご領主があの若者の意見を採り入れて、姑息な策などを用いて南の国の軍隊を追い返したりしたからだ」
「敵軍と言えども全滅させては、恨みを買うのも当然ではないか」
「だから、私は反対したのだ」
また、ある者は言った。
「今は春、白い悪魔の助力も宛てには出来ぬ」
「物見の報告によれば、敵軍の兵力は優に十七万五千を数えると聞く。他方、我が軍勢は国境防衛部隊三千七百、王都防衛部隊二千六百、これでは話にならぬ」
「実戦経験の無い我が軍勢が太刀打ち出来よう筈がない」
「だが、降伏するにしてもどうやって許しを請うのか」
「魔導王は残虐非道、逆らう者は容赦なく生き埋めにされると聞く」
「東の帝国は城民悉く焼き払われたと聞いたぞ」
「西の国では王族から民草まで全てが奴隷にされたそうな」
「王は奴隷を使役し、地獄の底へと続く大穴を掘らせているらしい」
評議会は夜明けと共に始まったが、日暮れまで協議しても結論など出よう筈も無い。
降伏しても、民の生命と財産を守れる保障など何処にもありはしないのだから。
ただ、南の国の軍隊と戦おうと言い出す者は誰一人として居なかった。
それほどまでに、北の国と南の国の兵力の差は絶望的だった。
ある者が言い出した。
「誰か、あの若者を此処に連れて来い」
「おお、そうだ。今回の騒動は彼の安易な行動が招いたもの」
「責任を取らせようではないか」
「彼を捕らえ、南の王に戦犯として引き渡して、許しを請うのだ」
「待て待て、彼の事だ。ひょっとすると今度もまた巧い手を考え付くかも知れぬぞ」
早速、領主の命令でマスターが王宮に呼び出された。
ご領主様と、居並ぶ廷臣達に向かって、マスターは言った。
「戦いましょう、南の王の軍勢と」
「貴君、正気か!?」
「ええ、地の利は我等にあり。王都に入るには険しい山嶺を抜けねばならず、山路は細く、残雪が積もり、大軍を以ってしても一息に押し通る事など出来ません」
「しかし、誰が我が軍を率いて南の軍勢と戦えようか」
「率いるものが居らぬのならば、私が指揮官となりましょう」
こうして、あたしのマスターは指揮官として、北の国の命運を背負い戦う事になった。
ご領主様がマスターに真紅の外套を羽織らせ、剣を腰に帯びさせた。
率いるは実戦経験皆無の王都防衛部隊二千六百余名のみ。
砦も無く、援軍も無く、自然の地形だけを頼りに戦い抜けるのだろうか。
王宮を後にするマスターの背に問い掛ける。
――勝てるよねぇ?……マスター?
――分からない。それでも、戦わなくてはならないんだ。
――二人で、何処か遠い国に逃げちゃおうよぉ。
――何処に逃げても、何時かは戦わなくてはならない時が来る。
マスターは話してくれた。
旅先で見て来た沢山の悲劇。
戦火に焼かれて家も財産も失ってしまった人。
荒れ果てたまま放置された麦畑。
毒を投げ込まれて枯れてしまった水源。
軍馬に蹂躙されて踏み砕かれた兵士。
幾人もの男に囲まれて陵辱される女。
食べる物が何も無くて飢え死にしてしまう子供。
奴隷として自由を奪われ、死ぬまで働かされ続ける人達。
たった一人の男の野心が生み出す、数え切れぬ程の悲しみの声。
――ずっと、目を閉じて、逃げて来たんだ。
何処に逃げても。
何処まで逃げても。
剣戟の響きは止まない。
この世界全土が、戦場になろうとしていた。
逃げる場所なんて、何処にも無い。
暗黒の時代だった。
――ボクは、この国の民を守りたい。みんなの笑顔を守りたいんだ。
――それだけなのかなぁ。
――……え?
「南の国の王様が求めているのは、黒き神、チェルノボグの壷でしょ」
あたしは、知っている。
マスターが策略を使って南の国の軍勢を撤退させたのは、北の国に黒き神の壷なんてものが存在しなかったからだ。
もしも、あの時、この国にチェルノボグの伝承が実在したならば。
ご領主様は迷わず壷を引き渡しただろう。
土地も痩せている、鉱物も産出しない、年間半年は港も凍り付いてしまう、そんな北方の小国は、時代から忘れられたかのように、ひっそりと、平和な時を刻めただろう。
「……あたしを引き渡せば、戦争は未然に回避出来るよ」
誰も死なずに済む。
誰も傷付かずに済む。
たった一つの冴えた遣り方。
「……ああ。……分かってる……」
気付かない筈が無い。あたしのマスターだもの。
だけど、マスターはあたしの為に戦場に赴く事を選んだ。
敵、味方、大勢の人が傷付いても、戦う事を選んでしまった。
ほんと、あたしって疫病神だよねぇ。
マスターの選択、明らかに間違っているのに、嬉しいだなんて思っちゃって。
こんなだから、黒き神なんて呼ばれちゃうんだよぉ。
「あたしも、一緒に付いて行くからね」
「駄目だ。君を戦場になんか連れて行けない」
「マスター、剣を振れないでしょ。あたしが代わりに戦うよぉ」
「君の手を血で汚したくないんだ」
「……あたしはマスターと一緒に戦う。あたしのせいで大勢の血が流れる戦いだもの、あたしだけ安穏と見てなんて居られない。あたしはマスターの剣、絶対に離れない。置いて行かれても、勝手に付いて行くよ」
あたしの意思が揺るがぬ事を見て取ったマスターは、部屋の中に山積みにされている荷物の中から、細長い布包みを掘り出して来て、あたしに渡してくれた。
「ボクが旅をしていた頃、使っていた槍だよ」
魚を獲る銛のようにギザギザした返しが付いた、鋭い穂先。
其の根元に埋め込まれた、大粒の四つの貴石。
羽が生えているかのように軽々と振り回せる、骨に似た素材で出来ている長柄。
掘り込まれているのは、槍の銘だろうか。
未だあたしの知らない文字だった。
「仇為す魔槍、雷の投撃(ジオ・ボルグ)」
マスターが読み方を教えてくれた。
大昔に妖精が造り出した槍で、投げ付ければ穂先が三十もの小さな矢になって飛び回り、敵を打ち据えて戻って来る。本来は、グリフォンやクラインといった空を飛び回る魔物に対抗する為に生み出された武器らしい。
「四大元素の宝石はボクが埋め込んだんだ。魔神相手に何処まで通用するかは分からないけれど」
「綺麗な槍だねぇ、マスター」
「……穂先が敵の体内で爆ぜて、原形を留めないくらい滅茶苦茶に破壊してしまうんだ。出来る事なら使いたくは無い、残虐な武器だよ……」
それでも、多数の敵を相手取るには最適の武器だと思った。
あたし達は戦場に赴き、国を守る為に人を殺す。
迷わない。
きっと殺れる。
あたしにとって一番大切なのは、マスターなのだから。
岩を落として幾つかの道を塞ぎ、進撃可能な道を限定する。
大地を埋め尽くす十七万五千の大軍も、山間の隘路を通り抜ける時には一本の紐のように延び切り、力の重厚を欠く。
国境防衛部隊は既に全滅、迎え撃つは王都防衛部隊、総員二千六百十七名。
されど、南の国の軍勢は、諸方の兵の寄せ集め。
王の力を恐れて従っているだけの烏合の衆に過ぎない。
指揮官を倒せば、士気を失い逃亡するだろう。
前軍は遣り過ごし、谷間に伏せた兵の奇襲攻撃を以って、側面より敵国の王の首を挙げ、一気に片を付ける。
マスターの指示を受けて、工兵部隊が動き出した。
もうすぐ、戦争が始まる。
響く火薬の炸裂音。
敵の先遣隊を、雪崩れや崖崩れに巻き込んで、外界へと通じる道を封鎖。
マスターが造った爆裂玉の破壊力は伊達じゃない。
「前線より報告!敵軍先遣隊第一部隊、及び第二・第四部隊、殲滅完了!」
「報告します!王都に通じる主要な街道の封鎖完了しました!」
「報告!桟道の崩落に伴い、敵軍の食料部隊に大打撃を与えました!」
次々に舞い込んで来る伝令達の報告。
そしていよいよ、敵軍本隊が、あたし達の待ち伏せている谷間に差し掛かる。
「来た!」
敵の中軍、白馬に跨るエメラルド色の甲冑を着た男。
燃える紅髪、漆黒の瞳、漆黒の大剣を身に帯びて。
「……あれが、南の国の王……」
魔導王、リト。
無数の魔神と軍勢を従え、数多の奴隷を使役する絶対君主。
思っていたのとは随分と違う。
世界征服の野心に燃える覇王だなんて言うから、オーガみたいな大男だと思ってた。
実際に見た彼は、何て言うか、まるで……子供が、そのまんま大人になってしまったみたいな感じの……少し危うげな印象の人に見えた。
駄目だ、この人に世界を渡したりなんかしたら、とんでもない事になる。
「行こう、マスター!」
頷き、マスターが左手で剣を抜いた。
高らかに掲げ、号令と共に振り下ろす。
「――全軍突撃!狙うは敵軍指揮官のみ!!」
鴇の声を挙げ、一斉に敵軍兵士へと切り掛かる。
飛び交う煙幕玉に粘着玉。
側面からの不意打ちを受けて面食らう敵軍の中心に向けて、あたしは魔槍を放つ。
拡散し、身の内に喰い込み爆ぜる、雷光を帯びた三十の穂先。
倒れ伏す兵士、飛び散る肉片、朱に染まる残雪。
手元に槍が戻って来るまでの間に、更に敵兵に向けて呪文を放つ。
「数多の闇よ、敵を討て(ラナ・ハーム)!!」
掌に生み出した暗闇の渦。
あたしに撃ち掛かって来た敵兵らの四肢を無惨に捻り飛ばす。
唱和する悲痛な叫び。
「魔法!?」「魔神が敵軍に居るのか!?」
手元に戻って来た魔槍を高々と掲げて、あたしは名乗りを挙げた。
「我が名はカーミラ!北国を守護する黒き神!我らに仇為す者共を一人残らず討ち滅ぼしてくれようぞ!さあ、我に挑まんとする者は前に出るがいい!!」
瞬く間に、兵士達の間に動揺が広がって行く。
無理も無い。
魔神の脅威を最も熟知して居るのは、他ならぬ彼らなのだから。
そして、それもまたマスターの作戦の内なのだ。
畏れに囚われた兵士達に向けて、あたしは小声で呪文を唱えた。
「暗き闇夜に蠢く幻影よ、敵を惑わせ(ソムニア)」
暗闇は人の恐怖を倍加させ、彼らの心にありもしない幻影を映し出す。
「ひっ、魔物だ!」
「こっちにも居るぞ!?」
「来るなっ、来るなぁぁァ!!?」
敵軍の士気を下げ、煙幕玉や粘着玉で動きを止め、魔法で敵を混乱させて、真っ向から刃を合わせる事も無いまま、一気に敵の指揮官の首を獲る。
それが、被害を最小限に抑え、奇襲を成功させる為にマスターが立てた作戦だった。
「魔導王、覚悟!!」
幻影に怯える敵の群れを抜け、あたしは魔槍を振り翳す。
白馬に跨る標的目掛けて投げ付けようとした刹那、
「――瓦解する大地よ(ナファール)!!」
突然、足元の地面が崩れ落ちる。
間一髪のところで後ろに飛び退いた。
「誰っ!?」
「其処までです。私の主に危害を加える事は許しません」
風に踊る薄紅色の長い髪、戦火の照り返しを受けて輝く翡翠色の瞳。
頭上に三日月の宝冠を戴き、嫋やかな其の身を包むローブは栄光の純白。
まるで英雄伝承の絵巻物から抜け出て来た姫君のようだと思った。
「おお、ティララ様!」
「我らに祝福を!」
彼女の周囲を取り囲み平伏す傷付いた兵士達。
此処は戦場なのに、武器さえも投げ出して、まるで聖堂で祈るかのように。
「蘇れ、再起せよ、皆に等しき救いを(リサ・ユナーシャ・エレクマーシャ)」
兵士達の傷が癒されて行く。
手足を捻じ切られ、臓腑が爆ぜて絶命した筈の兵士が起き上がる。
幻影に恐れ慄く兵士の瞳に、理性の光が戻る。
煙幕の煙が吹き払われ、粘着液が清められて純水に変わる。
癒しの光に包まれて元気を取り戻した敵軍兵士達は、再び剣を執り、あたし達の軍に向かって攻撃を再開。
「うわ、ちょっと待ってよ!それ、困るぅっ!」
真っ向から戦って勝てる筈が無い。
瞬く間に形勢は逆転し、あたし達の軍は次第に押され始めた。
いけない。早く、魔導王の首を――
あたしは魔槍を振り翳す。
横合いから放たれた光刃の槍が、あたしの脇腹を貫く。
あたしは、魔神、この程度の傷で……
「ぅぁ…ぁぁああああああああっ、死ねぇぇっ、魔導王ぉぉぉっっ!!」
「下がりなさい、無礼者!!」
万物を灰燼と化す炎(エスレイオン)。
マスターから渡されていた結界護符を使って、咄嗟に凌ぐ。
「ぅ……ぐ…ぁ………」
「貴方達に勝ち目はありません。大人しく軍を退きなさい」
「ぐ…ぅ……は、はっ、絶望のッ、闇よッッ(ガルナ・ヴェール)!!」
動く。まだ、動ける。
あたし達はまだ負けてなんか居ない。
質量を持つ漆黒の闇の津波を解き放ち、癒しの女神に向けて魔槍を振るう。
ぶつかり合う、魔槍と神槍。
発生した衝撃波が、周囲を無差別に薙ぎ払う。
「愚かな!何故、死に急ぐのです!」
「降伏して、奴隷として死ぬまで穴を掘れなんて言われたら、誰だって剣を執って立ち上がるに決まってるじゃないの!あたし達は、魔導王の道具じゃないっ!」
あたしの槍が、ティララの肩を貫く。
「等しき救いなんて嘘ばっかり!」
返す槍でティララの槍を持つ手を狙う。
弾き返される。
あたしの脇腹の傷口から大量の血が噴き出す。
「どうして!?誰かを助けられる力を持っているのに、貴方が其の気になれば全ての人を幸せにしてあげる事だって出来るでしょうにっ!何で皆を傷付けたりなんかするのよっ!!」
其れは、あたしが欲しかった力。
大切な人を癒してあげられる、守ってあげられる力。
望んでも、得られなかった、光の力。
「――うるさいっ!」
ティララの槍の一薙ぎが、空間ごとあたしを切り裂く。
「私だって……私だってっ、人間を癒す為だけの道具じゃないわよっ!」
右腕の筋を断たれ、骨を粉々に砕かれた。
流石のあたしも、これはかなり痛い。
けど、まだ、左手が残ってる。……まだ、戦えるっ。
「私を愛してくれたのは、リトだけ。私を見てくれたのは、リトだけ。だから、私はリトの為に戦う。リトが望む人だけを癒してあげるの!」
「あんた、世界が見えてないの!?あんたの大好きな魔導王サマの我侭のせいで、どれだけ多くの人間が泣いてると思っているのよぉっ!!」
――ごめん。ちょっとだけ、嘘。
あたしには、ティララの気持ちが解ってしまった。
あたしだって、同じだ。
大好きなマスターと離れたくなくて、大勢の人の血が流れると解っていながら、北の国と南の国の戦端を開いてしまった。
ぶつかりあう剣戟の音は遠く、燃える硝煙の臭い、血に煙る鉄錆びの臭い。
嗚呼、みんな死んでいく。
剣を振るい、人を殺し、剣を浴びて、死んでいく。
「ごめんね、ティララ。それでも、あたしは、魔導王を殺す。そして、みんなが、自由に生きられる時代を取り戻すよ」
次が、最後の一撃。
あたしの、全力を魔槍に込めて、一気に解き放つ。
「「――――――――――――――――――――!!!!!」」
交差する一閃。
あたしの槍は、ティララの心臓を貫いた。
「か………ふっ……」
魔神は人の願いから生まれるもの。
例え、傷付き倒れようとも、時が経てば蘇る。
ごめんね、ティララ。
次は、平和な時代に会えたらいいな。
きっと、あたしの事、許してはくれないだろうけど。
あたしは、ティララの胸に突き刺さった魔槍を引き抜く。
対峙する、白き馬上の男。
魔導王、リト。
ティララの想い人。
そして、今から、あたしが殺す男。
あたしは、槍を、振り被った。
「……………め……」
血と泥に塗れた純白のローブ。
穿たれた胸、抉れた心臓。
ありえない、この状況で動けるなんて、
「…り…とぉ、…ろさ、ないで……」
「――っ、魔導王ぉぉぉっ!!」
「駄目ぇぇぇぇっっっ!!!」
ティララが、あたしに飛び掛る。
あたしを羽交い絞めにして、取り落とした魔槍を遠くへ蹴り飛ばす。
半狂乱になって、優美だった女神の面影も無く、ただ、只管に泣き喚きながら。
そんなあたし達を、馬上の男は冷ややかな目で見つめていた。
ゆっくりと、馬の歩を進めて、あたしと、ティララに向けて、大剣を突き付ける。
大剣の刃は、あたしごと、ティララを貫いた。
「……っぐ…っ……か…ふっ」
ぼたぼたと咽を通って吹き上がって来る鮮血。
魔神は人の願いから生まれるもの。
例え、傷付き倒れようとも、時が経てば蘇る。
だからって、こんなのっ、
「道具じゃない…って、言ったじゃない、ティララぁ……」
一撃。
更に一撃。
あたしと、ティララと、二人を刻む黒の大剣。
「……終わりだ、チェルノボグ……」
無慈悲な最後の一撃を繰り出さんと、剣が振り上げられた刹那。
「カァーーミラァーーーっっ!!!」
「来ちゃ駄目ですっ、マスタぁーーっっ!!」
あたしと、ティララを、突き飛ばす。
弧を描く大剣の軌跡。
背中を大きく抉られて、倒れ伏すマスター。
「……どうして」
流れ出る血、冷たくなって行く躯。
「どうして、マスターが此処に居るんですかっ!!」
「カー…ミラ、迎…えに……来たよ……」
背嚢から癒油を取り出し、傷口に注ぎ掛ける。
マスターの傷は深く、出血は止まらない。
流れ出て行く。マスターの生命が、流れ出て行く。
「マスターっ!しっかりして下さい、マスターっ!!」
「帰…ろう、一緒に…。ボク…達の…、家……に……」
「ええ……ええ……帰りましょう、マスター……」
帰らなきゃ。
早く王都に戻って、マスターをお医者様に連れて行かなきゃ。
大丈夫、きっと、助かる筈。
既に戦局は決していた。
王都防衛部隊二千六百余名の大多数が戦死。
南の軍勢による殲滅戦の様相を呈していた。
あたしは、マスターを馬に乗せた。
戦場では、まだ友軍が戦っている。
みんな見捨てて、逃亡した。
死んでいく。
みんな、みんな、死んでいく。
あたしのせいで。
どうでもいい。
誰が死のうと、あたしの知った事じゃない。
あたしはっ、マスターさえ助かれば他の人なんてどうでもいいっ。
……ごめんなさい。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
ごめんなさい。 ごめんなさい。 ごめんなさい。
神様、あたしの命なんて要らない。
だから、マスターを、助けて下さい……。
あたしは懸命に馬を走らせた。
凍った山道を崖に落ちるギリギリの速度で駆け抜ける。
遥か頭上を飛んで往く、翼を持つ魔神達。
「もう、やめてよ……」
ああ、そうだ。
道を封鎖したとしても。
大空を往く魔神を防ぎ切る事なんて出来ないじゃないか。
遥かに見下ろす王都は、天をも焦がす業火に包まれていた。
「もう、やめてよぉっ!!」
あたしの声は、天に届かない。
これは、罰。
マスターとの愛に溺れて、人々の生命を軽んじた罪の。
あたしは黒き神、チェルノボグ。
人々に不幸を運ぶ為に生まれて来た存在。
呪われた破壊神。
憎しみを込めた贈り物。
主を滅びの道へと歩ませる者。
まるで、鉛の詰まった鋼鉄の壷のように。
轟々と唸りを上げて燃え盛る炎に包まれて、
崩れ落ちる建物、逃げ惑う人々。
王都に戻ったあたし達を取り囲む、怨嗟の視線。
「おまえ達のせいだ」
誰かが叫んだ。
「殺せ!こいつらをぶち殺せ!!」
口々に叫び、獲物を振り上げる。
「待って!お願いっ、あたしなら袋叩きにしても構わないからっ、マスターをっ、マスターを助けてっ!!」
返事は、風切り音と共に放たれた。
強く引き絞られた弩から、雨霰と降り注ぐ無数の矢。
あたしは、マスターを抱き抱えた。
無数の矢が背中に刺さっても、あたしはマスターを守り抜く。
マスターが立ち上がる。
「待ってて……」
満身創痍の筈なのに、両手を広げてあたしの前に出ようとする。
「きっと、君を探しに行くから……」
そして、致命的な一撃。
マスターの咽に、深々と矢が突き刺さる。
消え行く意識の中で、掠れた声で、マスターは最後にあたしにこう告げた。
「生まれ変わっても、ボクは、永遠に、君だけを、愛し、続け……――」
――それが、永い物語の終わり。
「マスター、マスターっ……」
――マスターはもう、目を開かない。
「うぁっ、ぁぁ……」
――其の温もりも消え失せて
「ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああっっっっっっっっっっっ!!!!!!!!!!!」
――あたしに微笑みかけてくれる事も、無い。
黒き神が目を覚ます
其は歴史より抹消されし伝承
贖い切れぬ罪の慟哭、全ての希望を闇へと閉ざす
ああ、悲劇は、永久に繰り返されるのか
邪神カーミラ、再臨す!
あたしが、マスターを殺した。
悪いのは、全部、あたし。
じゃあ、矢を放ったのは誰?
どうして、こんな事になってしまったの?
沢山の人を殺した。
家も、お城も、全部、破壊し尽くした。
北の国は消滅した。
土地は汚染され、水は毒に変わり、誰も住めない場所になった。
間違えたのは、誰?
何時、間違えた?
何処で、何を、間違えてしまったの?
本当に悪いのは、誰?
全てが滅んだ焼け野原で、あたしは考えて、考えて、考え抜いた。
答えは、出なかった。
誰も悲しまなくて済む世界って、あるのかな。
完全な世界って、あるのかな。
でも、もし世界が完全じゃなかったとしても……。
あたしは、あの人が帰って来てくれれば、其れでいいと思うの。
だって、あたしにとって、あの人は……存在理由そのものだったのだから。
――からんからん。
館の扉に取り付けられたドアベルの音。
『マスター!?』
……何度期待し、何度裏切られただろう。
『そっかぁ……。ティララ、あんた遂に見つけたんだねぇ。……なんか悔しいなぁ。あたしのマスターはまだ帰って来ない……。ふふふ、応援してるわ。頑張ってね』
幾つの冬が過ぎて、幾つの春を数えただろう。
『待ってて……』
あたしは、あの人を待ち続けている。
『きっと、君を探しに行くから……』
約束、したから。
「生まれ変わっても、ボクは永遠に、君だけを愛し続けるよ……カーミラ」
「ただいま」
「……おかえりなさい、あたしの愛しい人」
−Fin−