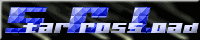“ちょっと様子を見て来るよ。ここで待っていてくれないか?”
“大丈夫、すぐに戻って来る”
“おいおい、お前を残して、勝手に死んだりするわけないだろう? 馬鹿だなぁ”
心配しないでちゃんと待っていろ、とあなたが言った。
絶対に無事で戻って来るから、と約束してくれた。
だけど、それがマスターの下した最後の命令となった。
ねぇ、次は何をすれば良いの? どこを目指して進めば良いの? 分からない。教えてよ。早く私に指示を出して。
信じてた。
ずっとずっと信じてた。
明日も空に太陽が昇るのと同じくらい、夜には闇の帳が下りるのと同じくらい、確かに信じてた。そう、いつか必ず帰って来る、と。
あなたと再び巡り会い、側に仕えることを望まれ、力となることだけが私の存在意義。だから、今でもこうして待っているのに――
ねぇ、あなたの声が聞きたいよ。あなたの笑顔がもう一度見たいよ……。
「ま、魔法石の欠片60個ぉ!?」
気だるい昼下がりの交換所に、調子外れなリトの叫びが響き渡った。耳にした者の同情を誘わずにはいられないほど、情けなく裏返った声を発してしまったのには理由がある、もちろん。
今、話題に上がっている魔法石とその欠片は、交換所の北に位置する廃坑で比較的容易に採取できる。しかし、何十個単位で集めようと思うと、結構な時間と労力を要する作業になるだろう。つまり、平たく言うと「かなり面倒くさい」。普通はたった一日で60個なんて、そんな無茶な数を集めようとは誰も思わない、……はずだ。
唐突に無理難題を提示したのは、閉ざされた島の西側で交換所を経営する女性――カーミラだ。普段から何の役にも立ちそうにないガラクタを、物々交換という形で冒険者から譲り受けては収集している人物――正確には魔神、である。今日は交換所を訪れたリトの姿を認めるなり、目を輝かせながら明日の予定の有無を尋ねて来た。うっかり「特に外せない用事はない」などと答えてしまったのが運の尽き。魔法石の欠片集めを依頼されてしまったというわけだ。
「そうそう、急にどうしても必要になっちゃってねぇ。お兄さんに手伝ってもらえるとすっごく嬉しいなぁ!」
「……か、帰る」
カーミラがあまりに満面の笑顔で迫って来るので、リトは圧倒されたようにじりじりと扉付近にまで後ずさる。そのまま、背を向けて交換所を出て行こうとしたが、カーミラに後ろ髪をむんずと掴まれてしまった。しかも、手加減抜きで。
「いっ!? 痛てててっ!!」
「お兄さぁん? この間、各種玉系アイテム14個セット、サービスしてあげたこと忘れちゃったのかなぁ?」
「う゛っ」
痛いところを突かれてしまった。リトは扉に手をかけた姿勢のまま、彫像のように凍りついて動けなくなってしまう。冷や汗が次から次に、頬から首筋へと伝って落ちた。
そうなのだ。まずいことにリトはカーミラに借りがあった。これまた悪いことに、彼は見た目以上に義を重んじるタイプでもあったのだ。今の彼は追い詰められたネズミよりも無力と化している。露骨なまでの笑みを浮かべたカーミラに、背後からぽんぽんと肩を叩かれただけであっさり白旗を揚げてしまった。
「ごめんなさいカーミラさん、俺なんかで良ければ、どこへなりとも連れて行って下さい。あああああ……」
リトはがっくりと頭を垂れて、この場からの脱出をあっさり諦めた。まさしく全面降伏である。口の端はひくひくと引き攣り、セリフは感情がこもらず棒読みだったが、カーミラは初めからまったく頓着しない。少しは気にして欲しいのだが。
「じゃ、交渉成立だねぇ!」
かくしてリトはめでたく地獄行きの切符を手に入れたのであった。
翌日。
廃坑探険ツアーの決行日としては、皮肉なほど綺麗に晴れ上がった天気だった。
「あーあ……」
青く澄み渡った早朝の空を仰いでは、リトは心底うんざりした様子でため息をつく。普段より一時間は早くベッドから出て、カーミラより先に待ち合わせの場所にやって来る辺りが妙に律儀だ。今日は霧も少なくて、ずいぶん過ごしやすい気候のようだな、と頭の片隅でぼんやり考えたりしている。もっとも薄暗い廃坑の中では、好天の恩恵などこれぽっちも享受できないのだが。……どうにも虚しい。
約束の時刻を少し過ぎた頃、カーミラが空間を切り開いて唐突に姿を現した。空間転移の術は彼女の持つ特殊能力の一つである。挨拶の言葉もないまま、彼女はなぜかリトの姿を見て、あからさまな驚愕の表情を作った。まずは遅刻の非礼を詫びるべきではないか、などと考えたのは残念なことにリトの方だけのようである。
「あれま、まさか先に来てるとは! お兄さん、なかなかやる気だねぇ。当日になってやっぱり嫌だ〜なんて言って、逃げ出しやしないかとヒヤヒヤしてたんだよ」
「そんなことしたら、後で百倍返しの報復が待ってるだけだろ」
「あははは! それもそうだねぇ、よく分かってるじゃない」
カーミラの弁舌は本日も絶好調のようである。これほど陽気な彼女と一緒ならば、とりあえず退屈だけはせずに済みそうだった。だからといって、魔法石の欠片集めが少しでも楽になるわけでもないのだが。
リトは曖昧な笑顔を張り付かせたまま、のろのろとした動作で廃坑の入り口をくぐった。ちなみに、彼が契約を交わし、その力を使役する三柱の魔神は一緒ではない。さすがにカーミラとの個人的な取引にまで付き合わせる気にはなれなかったのだ。今日は「休暇」という名目で、ファルたちには一日自由に過ごすよう言ってある。……人手はいくらあっても足りないというのに。リトは総じて、魔神のマスターとしてはかなり甘い方のようだった。
坑道内部に足を踏み入れた途端、ひんやりとした空気が全身を包み込んだ。湿っぽい土の匂いの裏側に隠れるように、わずかに漂って来る不快なカビ臭さが鼻をつく。潔癖なティララ辺りは「陰気で鬱陶しい、やなトコ」と評して毛嫌いする場所である。けれど、リト自身はこの閉鎖的な雰囲気が実はそう嫌いではなかった。
「しつこいようだけど、目標は今日中に60個だよ。真剣にやらないと、あっという間に日が暮れちゃうんだからねぇ」
「分かってるよ……」
カーミラに手渡された麻袋を、リトは腰のベルトのきっちり結び付けた。この袋がいっぱいになるまでに、一体どれほどの時間を要することか。想像しただけで頭が痛くなって来る。
「でも、それだけの数が集まらなかったらどうするんだ?」
「嫌だねぇ、60個揃うまで帰すわけないでしょ〜」
「……」
どうやら聞くだけ無駄だったようだ。カーミラの返事は軽口めいていたが、彼女の性格なら「居残りの刑」の執行が容易に想像できる。リトはいよいよ覚悟を決めざるを得なかった。そう、何が何でも60個、なのだ。
「やれやれ、しょうがないな」
リトはゆっくりと深呼吸をした後、廃坑の奥を鋭い眼差しで睨み、おもむろに鞘から愛用の剣を抜いた。まずは軽く空を斬り、武器の感覚を手に馴染ませる。そして、闇の向こうに潜み、蠢くものたちを真っ直ぐに見据えた。魔法石の収集を始める前に、まずは「お掃除」が必要である。彼らが足を踏み入れた瞬間から、廃坑をねぐらとする数体のモンスターが、殺気立った目つきでリトたちの様子を窺っていたのだ。
「頑張ってねぇ〜」
臨戦体勢に入ったリトの真剣な表情とは対照的に、一段高い岩場に腰を下ろしたカーミラが呑気にひらひらと手を振っている。手助けしようという素振りは皆無だ。悠然と両脚を組み合わせて、優雅に高みの見物と決め込んでいる。今のリトの実力ならば、廃坑のモンスター相手に梃子摺るはずがないと分かっているからだ。
「―――――ッ!!」
一瞬、周囲から音にならない唸り声が発生した。リトは素早く地面を蹴り、最も近くのモンスターに一閃を食らわせた後、勢いのまま次の標的に思い切り足で攻撃する。そいつが怯んだ隙に、左側から襲いかかって来たオーガの拳を盾で受け止めた。――それまでの所要時間・約五秒。
洗練され、計算され尽くした身のこなしの連続に、カーミラは拍手と共に賞賛の口笛を吹いた。
「お兄さん、やるう!」
「感心してないで、少しくらい手伝ってくれよ……。はっ!」
動く気のないカーミラにぼやきつつも、リトはけして気を抜かずに太刀を振るい続ける。やがて、彼の死角となる位置から、新たな敵が現れたのを見て取り、カーミラもようやく重い腰を上げた。懐から爆裂玉を取り出し、にやりと不敵な笑みを浮かべる。
「あたしもちょっとは働かないと、お兄さんに怒られちゃうからねぇ」
あくまで余裕の態度は崩さずに、カーミラは爆裂玉を絶妙な位置に投げ付けた。ただの小さな玉が地面に接触した途端、火花を発しながら凄まじい勢いで弾け飛ぶ。その爆風に煽られて、数体のモンスターの足止めに成功した。
ここまで来れば、仕上げまでにはものの数秒も掛かりはしない。最後の一体も、リトの正確な剣撃で喉を貫かれて、派手な音を立てて地面に倒れ伏した。
「いやはや、ついこの間まで新米冒険者だったのに、お兄さんもずいぶんに立派に成長したものだねぇ。あたしも感動だよ」
おどけるような軽い足取りで、カーミラがリトの側まで歩み寄った。実際、魔神のサポートがあったとはいえ、鮮やかな剣さばきを見せつけた彼は息一つ切らしてはいない。そして、リトに怪我がないことを確認すると、カーミラは楽しそうに魔法石の採取の開始を宣言した。
「それじゃあさっそく。まずはあそこの壁と、向こう側に一つずつだねぇ〜」
「はぁ、人使いが荒いよなぁ」
「はいはい、文句は60個集め終わってからにしてよ」
「……やっぱり帰りたい」
しかし、リトの心からのぼやきは、あっさり聞き流されたのであった。
それからたっぷり三時間。坑道に残されたレール沿いに奥へ向かっては、群がるモンスターを手当たり次第に薙ぎ払い、ありったけの魔法石を回収してさらに進んでゆく。そんな地味で疲れる作業がひたすら続いていた。
無駄口は叩かず、一心不乱に採取に打ち込むのが、この苦行から解放される最短の道だとはリト自身も理解しているのだが……。ついつい、側にいる誰かに話しかけたくなるのが人間の弱い部分だと言えよう。おまけに今日の同行者はかなりの話し上手で、聞き上手でもあった。
「なあ、カーミラ」
「んー? 何?」
「そもそも、どうして魔法石の欠片が60個も必要なんだ?」
リトが何気なく口にしたのは、今さらと言えば今さら過ぎる質問だった。会話の最中でも、お互いに視線は手元に落としたまま、短剣を使って器用に魔法石の欠片が埋まった壁の土を削り取っている。すると、一体何がおかしいのやら、カーミラはけらけらと愉快そう笑い出した。
「悪いけど、それは企業秘密ってやつかなぁ」
「ええ!?」
カーミラのつれない返答に、リトの声はみっともなく裏返った。おまけに、動揺のあまり目測が狂って、自分の指をダガーで軽く抉り取ってしまう。ちょっと痛いかもしれない。怪我した親指を舐めつつ、さすがのリトも恨みがましく抗議した。
「こんなに苦労して協力してるってのに、ひどいなぁ……」
「ま、色々と謎は多い方が楽しいでしょ〜。これも女を美しく見せる秘訣ってヤツかなぁ。ミステリアスな魔神ってカッコ良いじゃない?」
「はぁ……」
どうやらカーミラは断固として理由を明かすつもりはないらしい。これ以上の追求はおそらく上手くはぐらかされるばかりで無意味だろう。自分のしている行為に意味が見出せないとなると、リトはますます疲労感が上乗せされたような気分だった。
そして、さらに十分後。
じっとりと湿気を含んだ坑道の空気は、汗の滲み出した全身に耐えがたいレベルの不快感を与え始めていた。ぬぐってもぬぐっても切りがない。
「ああ、疲れたぁ。お兄さん、そろそろ休憩にしようか?」
休みなしのぶっ通しの作業で、さすがに集中力も途切れがちになって来た頃でもある。まるでタイミングを見計らったかのように、カーミラが女神のような笑顔で嬉しい提案してくれた。……そもそも、この状況に陥った原因が誰であるかは考えないことにする。彼女は魔法石がざっと40個は入っているであろう麻袋を慎重に地面に降した。リトもすぐにそれに倣う
「はぁ、何か体中がめりめり言ってるし……」
リトは肩の凝りをほぐすように、両腕をぐるぐる回しながら地べたに座り込んだ。慣れない作業の連続に、普段から体を鍛えている彼も若干へこたれ気味のようである。これなら、思い切り身体を動かせる分だけ、冥界の門でスケルトンの骨でも集めた方がマシだったような気がしないでもない。どちらにしても、ただ働きであることには変わりないのだが。
「あはは、お疲れさま〜。でも、まだまだ頑張ってもらうんだからねぇ」
「なぁ、続きは明日にしないか?」
「ダメだよ〜、今日中と言ったら今日中!」
カーミラは期日と個数に関してだけは絶対に譲らない。そして、彼女は荷物の中から大きな保温ポットを取り出した。この水筒の中に湯を入れておくと、いつまでも熱いまま冷めない便利な代物なのだと言う。どうやらカーミラ自慢のコレクションの一つのようだ。こういった不思議な魔法のアイテムを彼女はいくつも所有しているらしい。
二人分のカップにポットの中身が注がる。ふわりと立ち昇る白い湯気と共に、何とも言えず芳しい香りが広がった。片方のカップをリトに手渡しながら、カーミラは幸せそうに表情を綻ばせた。
「はい、イリスちゃん特製ブレンドのハーブティーだよ。本当はお酒でもあった方が良いんだけどねぇ〜」
「あ、ありがとう」
意外な気遣いに面食らいつつも、リトは温かいカップを素直に受け取った。そして、一口。喉の奥に落ちていった爽やかな香りが、全身を綺麗に浄化してくれるような感覚。疲れも一気に吹き飛んでしまった気がする。
体内で澱んでいた空気を追い出すように、リトは心を落ち着けて深呼吸を数回繰り返す。すると、目の前にいきなり包み紙の上に乗せたクッキーが差し出された。星型やら、ハート型やら、やけに可愛らしい形をしている。
「それと、お茶請けにお菓子もどうぞ。こっちはあたしの手作りなんだから、ありがたく噛み締めるように食べてよねぇ」
「へぇ、綺麗に焼けてるなぁ。たいしたもんだよ」
「ふふふ、だからってあたしに惚れちゃダメなんだからねぇ〜」
「って、なんでそうなるんだよ……」
リトはクッキーを一つ口の中に放り込み、なぜか胸を張って自慢するカーミラの様子を眺めた。舌の上で優しく溶ける、ほのかなバターの風味。砂糖が控えめにしてあるのか、甘いものが得意ではないリトでも、ついつい二枚目に手が伸びるような美味しさがあった。
(でもやっぱり、なんとなく意外だよなぁ)
交換所でのカーミラしか知らないリトには、お茶を片手にくつろぐ彼女の姿はどこか新鮮だった。わずか半日を共に過ごしただけだが、相手の思わぬ一面をいくつも発見できたような気がする。カーミラがクッキーを頬張るたびに、肩の上で綺麗な金髪が小さく揺らめいていた。
確か、彼女は自らを指して、黒き神――チェルノボグと言っていたはずだ。しかし、目の前の陽気な女性からは、そのような負のイメージはまったく伝わって来ない。……けれど、一緒にいるとこんなに楽しいのに、孤高の人というイメージが付き纏うのはなぜだろう?
あまりにまじまじと観察し過ぎたせいか、さすがにカーミラもリトの視線に気付いたようだ。
「んん? さっきからあたしのこと見つめちゃって……。その熱〜い眼差し、もしやホントに恋でもしちゃったぁ? あたしってば罪な女だねぇ」
「変な冗談はやめてくれよ……」
「そうだねぇ、お兄さんがあたしに夢中になんかなっちゃったら、おばさん……じゃなくて、ティララのヤツがうるさいだろうしなぁ。女の嫉妬は怖い怖い」
「? ティララがどうしたって?」
リトの反問はあまりに不用意だったが、なぜここでティララの名前が出てくるのか、鈍感な彼にはさっぱり見当が付かなかったのだ。リトが本気で分かっていないと知ると、カーミラは口の端をにやりと意地悪く吊り上げた。からかいがいのあるオモチャを見つけた悪戯っ子の表情である。
「あらま、もしかしてまぁだ気付いてないの?」
「だから、何が?」
「はぁ〜、お兄さんも罪な男だねぇ。あいつ、なんだかんだでベタ惚れみたいだから、あんまり泣かせるようなことしないでやってよねぇ。愚痴を聞かされるのは私なんだからさぁ」
カーミラにばんばん肩を叩かれても、当のリトはまったく話に付いて行けていない。異様な女の迫力に押され、身に覚えもないのに妙な汗が伝い落ちる。
「いや、だから何のはな……、いてっ!」
その時、リトの後頭部に小さな痛みが走った。思わぬ不意討ちに驚いて、即座に背後を振り返ったが何の気配も見当たらない。数秒の後、カランと乾いた音が響いて、足下に小さな石が転がり落ちただけだった。天井から崩れて来たのものが、ちょうどリトの頭に命中したのだろうか……。真偽の程はともかく、すっかりカーミラへの追及のタイミングを逃してしまったことだけは確かだった。
「ま、頑張ってねぇ〜」
カーミラはクッキーを二、三枚まとめて放り込み、意味の良く分からない無責任な声援を送っていた。思考がますます混乱して、リトががっくりと脱力したのは言うまでもない。
長かった魔法石の欠片集めも、いよいよ終盤に突入と言ったところだろうか。しかし、疲労と飽きと集中力の衰えから、確実にペースダウンしている事実は否めなかった。
「あ、後二つ……、たったの……ふた、つ……」
壁際に手を付いたリトは、全身を引き摺るようにして、じりじりと廃坑の奥に進んでゆく。すでに目は虚ろで、まともに焦点も合っていない。まさか魔法石の収集ごときで、廃人の三歩手前を体験することになろうとは思ってもみなかった。
麻袋の中身が50個を超えた辺りから、極端に入手効率が悪くなり始めている。もしや、とっくに廃坑内の魔法石をすべて採取し尽くしてしまったのではないだろうか。と言っても、数日も経てばまた自然に生成されるものなのだが。この場合、「何が何でも今日中に!」という期限が問題となる。
「……なぁ、2個くらい多めに見――」
「お兄さんも諦めが悪いねぇ。何度聞いても答えは同じだよ〜」
「お、鬼」
「どうせなら、魔神と呼んで欲しいなぁ」
リトがどれだけ弱音を吐いても、カーミラは断固として60個のラインを譲らなかった。それどころか、どんどんやつれてゆくリトの姿を愉快がっている節すらあるから性質が悪い。彼女は鼻歌まじりに、踊るようなステップでリトの背中を追いかけた。どこからそんな元気が湧いて来るのか、リトはさっきから本気で理解に苦しんでいた。
「ったく、カーミラみたいな魔神のマスターを務めるのは大変そうだな」
軽い足取りで付いて来るカーミラを、ちらりと横目で振り返りながらリトはたまらず苦笑した。そもそも人間が魔神に使われている、というこの状況からして異常なのである。
魔神は人の望みから生まれ出たもの。魔神は人の願いを叶えるために力を揮うもの。……という風に聞いた覚えがあるのだが、もしかしてリトの勘違いだったのだろうか。どうやら彼の周辺には、型破りで常識外れな魔神が多く集まり過ぎているようだ。とはいえ、非常識な魔神たちに振り回される、こんな騒々しい毎日が案外気に入ってたりもするのだが。
「ん、そうかも、ね」
59個目の魔法石の欠片を発見し、壁に貼り付くように回収作業を始めたリトは、消え入りそうなほどか細いカーミラの返事をあやうく聞き逃しそうになった。彼女らしくもない弱々しい呟きに、触れてはならない話題だったのかと一瞬危惧する。と同時に、胸の内に膨らんだ好奇心を抑えることもできなかった。
「あのさ、カーミラにもやっぱりマスターっているんだよ、な? 一体どんな人なんだ?」
「……」
今まで、リトの問いにカーミラが沈黙で以って応えたのは初めてのことだった。冗談を飛ばすことも、笑ってはぐらかすこともしない。いや、「できなかった」と表現する方が正しいのか。薄く細められた彼女の両目は、今までリトが見たこともないような淀んだ色をしている。それはまるで、深い深い底知れぬ闇を映しているようだった。
「カーミラ?」
急激に得体の知れない不安感に襲われて、リトはわずかに腰をかがめて相手の表情を窺おうとした。すると、カーミラはぱっと面を上げて、何事もなかったかのように明るい顔を見せた。不自然なくらいに自然に。
「ほらほら、怠けてないで! あそこにも二つ見えてるよ〜」
「え? あ、ああ……」
しかし、カーミラの指し示す方向を振り返っても、リトには魔法石の輝きを見付けることはできなかった。カーミラは「あれれ、見間違えちゃったかな、ごめんねぇ」と照れ笑いしながら失敗を詫びている。彼女らしくもないストレートなごまかし方だった。いつも口先三寸でまるめこまれ、うまく話題の焦点をずらされているリトとしては拍子抜けも良いところである。……それほどまでに禁忌(タブー)の話題だったということなのか。
その証拠に、カーミラの表情はわずかに引き攣れ、歪んでいた
リトは何も言わずに、カーミラの先に立って奥へと進んだ。そう、何も見なかった振りをすればいい。これ以上、彼女を傷付けずに済む方法は他に思い浮かばなかった。モンスターが一体、物陰に身を潜めていたが、カーミラの援護もあってリトは難なく撃破に成功した。
「あ、ここってもしかして……」
いつの間にか、坑道の行き止まりにまでたどり着いてしまったらしい。目の前には不気味な銅色の輝きを放つ「黄色の扉」が立ちはだかっていた。酒場のマスターが言うには、錠を開けるためには神官の鍵が必要なはずである。何か不思議な力に吸い寄せられるように、リトは扉のすぐ目の前にまでゆっくり歩み寄った。
「この扉って、確か抜け道に通じてるんだったよな」
つい先日、古城から抜け道を経由して、この扉のすぐ向こう側に安置してある宝箱から、神官の鍵を手に入れたばかりだった。ちょうど今も胸のポケットに大事にしまってある。鍵の管理はリトの役目なのだ。
カーミラがリトの隣に並んで、どこかつまらなさそうに扉を眺めた。
「そうみたいだねぇ。もっとも、あたしはあんまりこの先には行きたくないけど」
それでも――
冒険者たちは誰もが漆黒の迷宮を目指し、島の奥深くに眠る「真実」を求めて旅を続けるのだ。お兄さんもきっと同じように、たとえ絶望しか待っていないとしても、自ら進んで暗闇にすら身を投じるんだろうね、と。カーミラは瞳だけでそんな風に問い掛けているような気がした。しばしの思案の後、リトは胸元から神官の鍵を取り出した。
「なぁカーミラ、ちょっと向こうの様子を見て来ても構わないか?」
「……それは明日でも良いんじゃないかなぁ」
「う〜ん、本当に少しだけだからさ。この間、抜け道で人影を見かけたんだけど、あいつらは人間の姿なんて見てないって口を揃えて言うし……。妙に気にかかるんだよ」
「今日、……は魔法石の欠片を集めるの、が最優先だよ。サボ、ろうと思ったって……、無駄なんだからねぇ」
カーミラの語尾が徐々に掠れて、普段の威勢の良い喋り方は鳴りを潜めてゆく。彼女の握り締めた両手のひらが白くなり、肩も小刻みに震えていることにリトは気付かない。なんとか彼女の許可を得ようと、しきりに説得を試みているだけだった。
――ちょっと様子を見て来るよ。ここで待っていてくれないか?
「カーミラはここで待っていてくれたら良いからさ」
「そんなこと、言って」
――大丈夫、すぐに戻って来る。
「すぐに戻って、最後の一個もちゃんと見つけるよ」
「どこかに行ったきり、なんでしょ」
――おいおい、お前を残して、勝手に死んだりするわけないだろう? 馬鹿だなぁ。
「今さらカーミラを残して、勝手に逃げ帰ったりするわけないって。俺って、そんなに信用がないのか?」
「分かってるんだから、騙され、ないんだか、らねぇ、今、度は」
――約束、約束、約ソク、ヤクソ、ク、ヤ、ク、ソ、ク……?
「カーミラ? 聞いてるのか?」
ぶつぶつと独り言のようなカーミラの受け答えに、いくら鈍いリトでも心底から反対されているらしいことを悟った。とはいえ、よほど緊急に魔法石の欠片が必要だったのだろうか、くらいの安易な想像しかリトの脳裏には浮かばない。それにしては不自然な反応だとも思ったが、彼女の気分を害してしまったことは率直に反省した。もともと廃坑には彼女のためにやって来たのだから、我が侭を言うのはせめて約束をきちんと果たしてからだ。
「ごめん、悪かったよ。ここに魔法石はないみたいだし、あっちに戻ってさっさと最後の1個を見つけよう。……な?」
相手を安堵させようと、なるべく穏やかな口調で促したつもりだった。神官の鍵をポケットにしまい、さっき来た道を戻ろうとする。しかし、リトがカーミラに背を向けた瞬間、――何かが壊れた。極限まで薄く張った氷の膜のように、安定の悪い場所に積み上げた小石の山のように、いともあっけなく。すべてが崩れ落ちた。
「い、や」
絞り出すような強張った声は、リトが振り返るよりも早く、彼女の狂気を伝える危険信号だった。数瞬後には張り裂けんばかりの絶叫へと変わる。
「いや、いやいやいやあぁぁぁ!!」
まるで幼い子供のようにヒステリックに、カーミラは髪を振り乱して「何か」を必死で拒絶していた。彼女の全身にまとわりついたオーラは、毒々しいまでの異様な色彩を放っている。リトは呆気に取られて、とっさに何のリアクションも返せなかった。
「ど、どうしたんだよ、いきなり……」
「そうやって、いつまでも戻って来ないつもりなんでしょ!? 嫌だよ、もうこれ以上待ってるのは嫌だよぉぉぉ!!」
カーミラの細くて白い指が、リトの服の裾を乱暴に掴みかかった。伸びた爪が皮膚にまで食い込んで、痺れるような痛みをもたらすほどに強く。リトは困惑の波に飲み込まれそうになりながらも、なんとか正気を取り戻させようとカーミラの肩を揺さぶった。とにかく、このまま激情に引き摺られることだけはあってはならない。
「カーミラ、しっかりしてくれよ! 俺はここにいるから!」
「嘘、嘘、嘘! うそつき!!」
カーミラにはリトの言葉がまともに届いていないようだった。涙に濡れた彼女の瞳は、もはや目の前の相手の姿を捉えてはいない。どこか遠くにいる別の誰かに、無我夢中で縋り付いているのだ。けして置いて行かれまい、と。
「……」
リトは迷っていた。極度の興奮状態にあるカーミラを落ち着かせるため、少々強引にでも抱き締めて自由を奪ってしまうべきなのだろうか。しかし、リトがその行為を思い留まっていたのは、自分が彼女を受け止めるに足る人間だとは到底思えなかったからだ。――カーミラは誰かを待っている。リトではない誰かを。その人に優しく抱き留めてもらえる日を、悲しいくらい一途な思いで待ち続けているのだ。
「カーミラ、もしかして君は――」
「ああああんたら、さっきから一体何やってんのよおおおっ!!」
リトの指先がカーミラの背に回される直前。鼓膜を突き破らんばかりの絶叫が、空気をびりびり振動させ廃坑中にくまなく響き渡った。たとえ古城にいても聞こえたのではないか、と本気で疑ってしまうほどの凄まじい声量である。カーミラのものでも、ましてやリトのものでもない。どうやら思わぬ第三者が乱入して来たようだった。
「な、な、な……っ!?」
唖然として固まるリトの目の前に、鮮やかなピンク色の髪がふわりと広がった。常に手入れを欠かさない女神様ご自慢の美貌は、言葉に尽くせぬ怒りに支配されて見る影もなかったが……。見間違えようもなく、リトが契約を交わした魔神のうちの一柱・光の女神ティララである。
「今日は二人で魔法石集めって聞いたけど、さっきもずいぶん楽しそうにお茶してたわねぇぇぇ……。一体どういうことなのかしら、ええ?」
ティララは憤慨も露わに、腕を組んでリトの真正面に仁王立ちになった。あまりの展開に口をぱくぱく動かすことしかできないリト。しかし、天は無情にも彼にさらなる追い打ちをかけた。
「もうティララ! おっきな声出すから耳が痛いの〜!」
「まったく非常識だな」
「それに、さっきもリトに石をぶつけたの! ティララはらんぼうものなの! ファルのほうがずーっと優しくて、リトにふさわしいの!」
なんとティララの背後から、残りの二柱・ファルとディーヴァまでひょっこり顔を出したのだ。要するに、いつも通りのメンバーが勢揃いしたことになる。……せっかくの休日に、わざわざマスターを尾行して何が楽しいのか。
「ねぇリト、一緒にクゥを集めに行くの〜!」
さっそくリトの元へ駆け寄ろうとするファルを制し――具体的には首根っこを掴み上げて動きを封じ――、ティララがまさに鬼神のごとき形相で詰め寄って来た。
「で、リト? あなたカーミラに何をしたのよ? あいつがあんな情けない声を出すなんて尋常じゃないわよ!?」
「お、俺は何もしてな」
「この期に及んで言い逃れなんて見苦しいわ! ……正直に白状すれば、隕石三発くらいで許してあげないこともないけど?」
「嘘だ、絶対嘘だ……」
情けないことに、立っているだけでやっとなほどリトは怯えまくっていた。正直に言って、冥界の門に待ち受ける強き者たちより恐ろしい。事の顛末を包み隠さず話したところで、ティララが大人しく引き下がってくれるとは思えなかった。さっきから何となく感じていた頭痛が、どんどん激しさを増しているのが分かる。メテオストライク十連発の刑はもはや覆しがたい決定事項のように思われた。話題の張本人であるカーミラが、唐突にティララの腕にしがみ付いたりしなければ。
「あは、あはははははは……、何だ、ティララじゃない……」
「ちょ、ちょっとカーミラどうしたのよ? あんた、ついに気でも触れちゃったわけ?」
「あはははは、あは、あはははははははは……」
涙で顔中をべたべたに汚しながら、カーミラはしきりに笑い転げている。さすがのティララも毒気を抜かれ、手のひらに溜まっていた魔力が音もなく消え去った。なんとか命拾いをしたことを知り、リトは密かに安堵のため息をついたが、直後にティララに恐ろしい形相で睨み付けられてしまう。反射的に身を縮こまらせてしまう辺り、リトは魔神のマスターとして致命的に威厳が足りないようだ。もっと堂々としていれば良いものを。
「あはは……、ファルちゃんにディーヴァまでいるんだぁ……」
おかしくてたまらないという風に、カーミラは一人でひたすら笑い続けている。さすがに心配になったのか、ファルが恐る恐る近付いて行って、カーミラの手のひらを小さな手で優しく包み込んだ。完全に余談だが、リトから見て一番可愛らしく見える角度で首を傾げていたりする。
「みぃ?」
「そうだよねぇ……。あたし、馬鹿だよねぇ、本当に……」
ついにカーミラはその場にしゃがみこんでしまい、ファルの手のひらの柔らかな温もりに身を任せた。ディーヴァも静かに彼女の背中をさすってやっている。ティララは呆れたような表情になりながらも、カーミラの目の前に跪いて彼女のおでこを軽く指で弾いた。怒りの感情はすっかり抜けた様子である。
「まったく、世話が焼けるんだから」
「うん、ごめん」
カーミラは涙を拭って、ティララの二の腕辺りに頭を持たれかけさせた。もう泣いてはいない。リトが見た彼女は心から安らいでいて、幼い子供のように清く澄んだ目をしていた――
「お兄さん、今日は本当にごめんねぇ」
「あ、ああ。ちょっと驚いただけだからさ、別に気にすることなんてないよ」
「お兄さんは優しいねぇ……」
結局、魔法石の欠片探しは後1個のところで中断し、五人揃って廃坑の外にまで引き上げることになった。夕暮れ時の涼やかなそよ風が、リトとカーミラの隙間を優しく埋めてくれる。茜色に染まった西の空は息を飲むほど鮮やかだった。
ティララたちは少し離れた場所から、彼ら二人の様子を遠巻きに窺っている。カーミラがしばらくの間、リトと二人きりにしてほしいと頼み込んだのだ。いくら嫉妬の炎に取り憑かれたティララでも、友人の涙を見た後では無碍には断われなかったようである。最後には渋々ながらも承諾した。
「おかしいよねぇ、お兄さんとあの人、全然似てないのに……。一緒だった頃を思い出して、何か頭おかしくなっちゃったみたいだよ」
「あの人って、カーミラのマスターのことか?」
「うん」
カーミラは今度は素直に肯定した。その横顔は意外なほど晴れやかで、過去の重荷を一つ吹っ切ったように見える。彼女の中でどのような心の動きがあったのかは推し量りようもないけれど。
「あたしを置いたまま、全然帰って来ないんだぁ……」
手のひらを目の上にかざし、西日を遮りながらカーミラは山の向こうを眺めた。まるで視線の先に思い焦がれた主人の姿を探すように。リトもつられて同じ方角を振り仰ぐと、鳥の群れが一斉に飛び立つ様子が目に入った。食事の時間なのか、それとも寝床に帰るのだろうか。
「それで、カーミラはずっと待ってるんだな」
「……だからって、お兄さんに八つ当たりしちゃうなんて、あたしもまだまだ修行が足りないみたいだねぇ」
カーミラはリトの確認の言葉に対する明言を避けた。もしかしたら、彼女の中にも確かな答えは存在しないのかもしれない。いつだって迷い、苦しんでいるのだ。
もう帰って来るはずがないのだと、そんな風に諦めてしまった方が楽だろう。主人への忠誠を捨て去って、寄せた想いも忘れてしまえば、精神の束縛の糸から自由になれるはずだ。流れる無為の時は、彼女の身を苛み続けている。今この瞬間にも。
けれど――
「でも大丈夫。だって、今はお兄さんがいてくれるし」
「へ?」
なにやら爆弾発言を聞いたような気がするが、カーミラは涼しい顔で天に向かって大きく伸びをしていた。そして、一呼吸置いてから、リトに向かって思い切り破顔して見せる。黄昏色に染められた彼女の相貌は、透明な覚悟に満ちて今までになく美しかった。
「ティララはやかましいヤツだけど、なんだかんだでウマは合うみたいだしねぇ。ファルちゃんやイリスちゃんは可愛いし、ディーヴァの差し入れしてくれる手料理は最高だし。……ま、要するに――概ね幸せ、ってトコなのかなぁ」
カーミラの出した結論は、きっと本心からのものだったろう。ああ、そういうことか、とリトは目を細めて笑った。長い長い時を一人きりで待つのは辛くても、共に笑い合える仲間がいるのなら耐えてゆける。いつ再会できるとも知れない想い人も、そうやってカーミラが明るく生きてゆくことを願っているはずだから。
「強いんだな、カーミラは」
「そんなことないよ、さっきも失態見せちゃったしねぇ」
「でも俺、カーミラに謝らないといけない。色々余計なこと詮索したし、魔法石の欠片も結局60個集められなかったし……。って、もしかしてこれから居残りか!?」
リトの顔面から急激に血の気が引いてゆく。今から廃坑に引き返すなんて、ティララたちに馬鹿にされても仕方ないほど間抜けな話ではないか。おまけに、よくよく考えてみれば、休憩の時にクッキーを数枚口にしただけで、胃袋の満足するようなまともな食事を取っていない。いい加減、体力的にも限界である。
しかし、リトが本気で青ざめているにも関わらず、カーミラはばんばんと彼の肩を叩きながら笑い出した。
「あはははは! お兄さんは本っ当に真面目だねぇ!」
「な、何だよ。そもそも60個なんて無茶なこと言い出したのはそっちじゃないか」
「そうだねぇ、確かに数はそれで合ってるけど……」
くくく、とこみ上げる笑いを噛み殺しつつ、カーミラは魔法石とその欠片がぎっしり詰まった麻袋を手で探った。そして、中から綺麗な球体をした魔法石を一つ選び出す。なめらかな表面が夕日を反射し、一瞬だけ強くリトの目を眩ませた。
「?」
相手の意図がまったく読めず、リトはぼんやりと彼女の行動を見守るしかない。カーミラは軽くまぶたを伏せ、手のひらに乗せた魔法石に魔力を集中させた。ほどなく、ぱんっと乾いた音がして、魔法石は綺麗に二つに割れてしまう。どうしてそんな勿体無いことを……、とリトが抗議するより早く、カーミラは悪戯っ子のような可愛いらしいウインクを投げた。
「ほら、これで60個になったでしょ」
「え? え……、あ、ああーーーっ!?」
ようやく彼女の行動の意味を悟り、リトはさっきのティララにも負けない大声で喚いた。そう、カーミラはあくまで魔法石の「欠片」を60個集めて欲しい、と依頼のだ。なのに、リトは綺麗な完全体の魔法石まで、1個としてカウントしていたのである。馬鹿正直なことに。
「そ、そんな手があったのか……」
全身が砂で汚れるのも構わず、リトはその場にへたり込み、崩れ落ちそうな体を支えようと地面に手を付いた。どさくさに紛れて、ノルマよりかなり多く集めさせられたような気がする。思い付きもしなかった自分も自分だが、教えてくれなかったカーミラも人が悪い。――否、魔神が悪いとでも表現するべきなのか?
「お兄さんはもうちょっと要領良く生きることを覚えないとねぇ。正直者は馬鹿を見るって言葉、知ってる〜?」
がっくりとうな垂れるリトに、カーミラはどこまでも容赦がなかった。それどころか、やけに生き生きしているようにすら思える。けれど、その子供のような無邪気さで、相手をからかい笑い転げる姿こそが一番カーミラらしい姿なのかもしれなかった。
これでは、彼女を責める気にもなれない。リトはひたすら苦笑い。
「……まったく、カーミラらしいよ」
「あはは! それじゃ、みんな帰ろうか! 今日はあたしがめいっぱいご馳走を作っちゃうからねぇ〜。そうそう、イリスちゃんも呼ぼう!」
そして、カーミラは再び、元気いっぱいに駆け出したのだった。