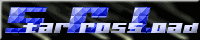「あの人、今度こそ死ぬよ」
ブロンドの髪をふわりと揺らめかせて、何でもないことのように冷めた口調で断言する。普段
の彼女からは想像できぬほど、空虚な瞳はどんな感情も宿してはいなかった。
「んー、今まで何人もの冒険者を見て来たからかな。なんとなく分かっちゃうの」
ならば、なぜ本人に向けて忠告し、無謀な挑戦を止めてやらないのか、と彼女に尋ねてみた。
我ながら、実に愚かな質問だと自覚しながら。そう簡単に探究心を抑えられるのならば、島の住
人は誰一人として嘆かずに済むだろう。案の定、幼稚で浅はかな提案はあっさりと笑い飛ばされ
た。
「あはは、それができるくらいならね。でも、どうせみんな聞く耳なんて持ってくれない。わた
しに許された精一杯の悪あがきは、せめて一日でも長く生き延びる方法を伝えることくらい」
彼女はすべてを諦め切った表情で静かに微笑んでいた。
(お前はいつか、俺の背中にも死神の姿を見るんだろうか)
ダンジョンに潜む強敵を命からがら打ち倒すたびに考える。そして、あの美しい女性の面影を
目裏に思い描くのだ。
(……なあ、レジーナ)
閉ざされた島の唯一の酒場はいつでも賑やかだ。大勢の冒険者たちが自然と集まる安らぎの場
所。明日の命の保証がないことが分かっていても、彼らは島の奥深くに隠された真実に全力で挑
もうとする。とはいえ、普段は楽しく陽気に日々を過ごしている者ばかりだ。
「やっほぉリト君、良い所に来てくれたね。見てよ、こんなにたくさんクラゲを捕まえたんだよ!
」
リトが酒場の扉を開くやいなや、とびきり明るい笑顔が出迎えてくれた。冒険者のうちの一人
で、栗色の髪が愛らしいグレイスという若い女性である。彼女は相棒のミルコと一緒に、7大珍
味と呼ばれる食材を収集することに命をかけている節があった。それも一つの生き方なのだろう、
とリトは思う。
「うわ、すごい量だな、グレイス」
「でしょ? ミルコと二人じゃ食べ切れないから、みんなにもお裾分けしてるんだよ〜!」
溢れんばかりのクラゲの山を、グレイスは満足そうに厨房へと運ぶ。彼女の後について店内に
足を踏み入れた途端、リトは代わる代わるに冒険者たちから声をかけられた。たとえ共に行動す
ることはなくても、この場所を訪れる者は全員“仲間”なのだ。温かく穏やかな空気に包まれて、
リトの表情も自然と緩んでしまう。
「カレン、あなたまた私のお財布を勝手に持ち出したでしょう!」
「えええ〜? 濡れ衣だってば!」
「前科が多すぎなんですよ、あなたの場合!」
空になった酒瓶が大量に転がり、先客たちはすでにどんちゃん騒ぎを始めている。あまりのや
かましさに、来るタイミングを間違えたかな、とリトは密かに苦笑するしかなかった。しかし、
今さら出直すわけにもいかない。誰かにぐいぐいと背中を押されて、リトはなかば強引に空いて
いた席に座らされた。あれよあれよという間に、目の前のテーブルはお酒と料理でいっぱいになっ
てしまう。どうやらグレイスたちのクラゲのおかげで、ちょっとした宴会が繰り広げられている
ようだった。
早くも酔い潰れる者、延々と愚痴をこぼし続ける者、けたけた笑っていたかと思うと、なぜか
唐突に涙を流し始める者――さまざまな人間模様がそこかしこに見て取れた。
「いやホント、あそこで後ろからグリフォンに襲われた時はかなりヤバかった」
「ああ、俺も神殿では愛用の短剣をなくしちまったよ。その時は死にそうな思いで帰って来たぜ」
情報交換という名目で始まった雑談は、だんだんあらぬ方向へと捻じ曲がってゆく。隣の席に
座っていたタルバインが、突然リトの肩に腕を回して耳元で囁いた。……吐く息がかなり酒臭い。
「なあなあリト、いつもお前と一緒にいるファルちゃんって可愛いよなぁ。今度、俺にも紹介し
てくれよ。なっ!」
「えっ! う、うう〜ん……」
下心満点の耳打ちに、リトは心底から困り果てた。ファルの正体が魔神であることは、タルバ
インはおろか街の誰にも教えてはいない。言えば、余計な混乱を招きそうな気がしたからだ。そ
れに、ファルにとってリトはマスターというより保護者のような存在に近いらしい。父親と娘ほ
ど年の離れた男相手に、軽々しく会わせる約束をして良いものかと頭を悩ませた。――とはいえ、
実年齢はファルの方が遥かに上なのだが。
「あ、あのさ、最近、シアとユリアンの姿を見かけないけど、どうしたんだ?」
期待に満ちたタルバインの視線が痛くてしょうがない。拒絶も承諾もできず、冷や汗をかいた
リトは強引に話題を転換させた。こんな稚拙な話の逸らし方では、タルバインの追及からは逃れ
られないだろうと思いながら。
しかし、意外なことにリトの願いはあっさり叶えられた。重く気まずい沈黙の到来によって。
さっきまでの騒々しさが嘘か幻のようだった。
「……あの二人は」
誰もリトとは目を合わせず、明らかに次の言葉を言い澱んでいる。すると、最年少かつ天真爛
漫な性格のグレッグが、煮え切らない周りの態度に痺れを切らして、告げた。年齢に似合わぬほ
ど平坦な口調で。
「死んだんだよ、神殿で。今頃は狼の餌にでもなってるかもね」
「おい! もうちょっと言い方ってものが……」
「どんな風に誤魔化したって、結局それが事実じゃないか!」
制止しようとしたタルバインを、グレッグは怒気も露わに捻じ伏せる。和やかな空気は一瞬に
して壊れてしまっていた。リトは何も言えない。それどころか、グラスを握ったままの体勢で微
動だにできずにいた。
分かっていたはずだ。ダンジョンの探索は常に死と隣り合わせ。ちょっとしたはずみで凶悪な
罠の餌食になったり、魔物の巣窟に足を踏み入れてしまったりすることだってありうるのだ。
「リトさんは新人さんだから、まだ冒険者の死に目に立ち会ったことがないんですね……」
誰かの何気ない一言が深く胸に突き刺さった。どこかから小さくすすり泣く声も聞こえて来る。
リトは自らの不用意な発言を心から悔やんだ。悲しみは伝播し、ついには場を支配してしまう。
このまま重苦しい雰囲気がいつまでも続くのかと思われた、その時――
「よぉテメェら! 男の中の男、イアソン様がただ今お帰りだぁッ!」
ガタガタガタンッ、と凄まじい音が店内に響き渡った。さらに、威勢の良い怒鳴り声が飛び込
んで来る。入り口の扉を行儀悪く蹴飛ばして現われたのは、冒険者仲間の中でもトップクラスの
実力を持つイアソンだった。全身から漂う自信に満ち溢れたオーラと、トレードマークの白いバ
ンダナが一際目を引く青年である。
「あぁ? どうしたんだよ、どいつもこいつもシケたツラしやがってさ。もっと明るく行こうぜ、
ぱーっとな!」
傍若無人な彼も、さすがに店内の異様な空気に首を傾げた。しかし、あまりに唐突な展開に面
食らい、誰も気の利いた反応を返せそうにない。辺りが奇妙な緊張感に包まれる中、一人の女性
が席を立ち、イアソンの真正面にまで歩み寄った。
「おかえりなさい、イアソン。あなたが無事でとっても嬉しい」
「お、レジーナ。今日は一段と綺麗だな。まさか出迎えの抱擁でもしてくれるってのか? モテ
る男はつらいぜ」
「あははははは、馬鹿言ってるんじゃないわよ、このサル頭」
レジーナと呼ばれた女性は、可愛らしく微笑みながら剣呑なことを口にする。そして、だしぬ
けに両腕を持ち上げると、細い指でイアソンの首をギリギリと締め付けた。
「酒場のドアは足で開けるものじゃないって、一体何度言ったら分かるのかしらねぇぇぇ。この
間、あんたが壊してくれた扉を、マスターとナインが直したばっかなんだから。……いい加減に
しないと、本気で息の根止めるわよぉ?」
「し、死ぬ死ぬ! マジで死ぬからやめろ!!」
「こうやって調教しないと、ちっとも学習しないくせに」
うふうふうふふと不気味に口の端を吊り上げ、レジーナは一切の容赦もなく両手にますます力
をこめたようだ。傍観者たちはみな呆気に取られていたが、お調子者のミルコが小さく吹き出し
たのが契機となって、次の瞬間にはどっと哄笑が湧き起こった。
「イアソン兄貴も、レジーナ姉ちゃんには頭が上がらないんだよね。なっさけないなぁ!」
「うるせぇ、ガキは黙ってろ! ……って、ぐわぁっ!!」
「へぇ〜、年下相手には強気な態度になるなんて最低よねぇ」
ようやく年相応の表情に戻って、グレッグがにやにやしながら囃し立てた。それをイアソンが
ムキになって叱りつけ、レジーナが「教育」と称してヘッドロックを決める。どうやらすっかり
いつも通りの構図に落ち着いたらしい。リトはほっと胸を撫で下ろした。
「う、うう、ごめんなさいレジーナ様……。今度、古城から王の宝をどっさり持って帰って来ま
す。だから、どうか許して下さい……、ぐふっ……」
「イアソンの約束なんて、全然あてにならないけどね。ま、いいかな」
呼吸困難の一歩手前でイアソンを解放し、レジーナはぱんぱんと仰々しく手のひらを払った。
何事もなかったかのように、そのまま扉近くの指定席にまで戻る。一方のイアソンはたいして懲
りた様子もなく、何人もの酒の勧めにいちいち律儀に応じていた。酔い潰れるのは時間の問題だ
ろう。
一連の騒動のおかげで、タルバインもすっかりさっきまでの話を忘れていた。これ幸いとばか
りに今までの席を離れ、リトは比較的静かなレジーナの正面に陣取った。
「レジーナありがとう、助かったよ」
「んー、何が?」
「俺が余計なこと言ったせいで、ちょっと険悪な雰囲気になったからさ……。でも、レジーナの
おかげで、いつも通りのみんなに戻ったみたいだ」
「ああ、いいのいいの。わたしは単に、あの馬鹿にがつんと言ってやりたかっただけだからさ」
レジーナは涼しい顔をして、なみなみと酒の注がれたグラスを一気に空にした。可愛らしい外
見からは想像もできぬほど肝っ玉が据わっているらしい。気持ちの良い飲みっぷりに感心したリ
トは、だんだんレジーナという一人の女性に興味を持ち始めた。
「前にイアソンがずいぶん残念がってたよ。どう口説いても、レジーナがダンジョン探索のパー
トナーを組んでくれない、って」
「うん、わたしはもうダンジョンには行かないって決めてるから」
レジーナはあっさりと切って捨てた。時折、彼女はびっくりするほど冷淡なものの言い方をす
る。急激な態度の変化に途惑いながらも、リトはなおも執拗に食い下がって問いかけた。
「レジーナは昔、腕利きの冒険者だったってマスターから聞いたことがある。なのに、どうして
今は……」
好奇心を抑え切れず、何にでも首を突っ込みたがるのは我ながら悪い癖だと思う。ふと気が付
いた時には、レジーナはやんわりと、しかし明らかにリトの無遠慮な詮索を拒絶していた。
「つまんない話だよ。今の君に聞かせるようなことじゃない」
口調は穏やかだが、レジーナの目は笑っていない。いくら鈍感なリトでも、踏み込んではなら
ない領域を侵そうとしてしまったことだけは分かる。慌てて謝罪の言葉を探していると、レジー
ナが急にずずいと身を乗り出した。
「じゃあ、わたしと飲み比べで勝てたら教えてあげよっかぁ」
「え、えええええ!?」
イアソンが以前レジーナと勝負をして、大敗を喫した挙句に三日三晩寝込んだという話は、こ
の酒場に集う者なら誰もが知る伝説だった。一気に顔面蒼白になったリトは、もげそうなくらい
強く首を左右に振って見せる。目の前の女性はくすくすと楽しそうに笑っていた。
やがて時は流れて、リトも新米冒険者とは呼べぬほど逞しくなった。ファル以外にも、ティラ
ラとディーヴァという二柱の魔神と契約を交わし、彼女らの助けを得ながら数々のダンジョンを
順調に踏破してゆく。迷うことなく真っ直ぐに。
しかし、身の回りに起きるのは喜ばしい変化ばかりでもない。酒場に集う冒険者たちは、一人
また一人と尊い命を落としていった。リトが直接、死の瞬間に立ち会ったこともある。そのたび
にやり切れない思いでいっぱいになるのだった。
「ピリカも抜け道で……。俺が看取ったよ」
「そうか。無事なのはもう、イアソンとお前だけみたいだな」
鎧に身を固めた女性――ナインが苦虫を噛み潰したような表情で呟く。あんなに多くの常連客
でひしめき合っていた酒場が、今では別の場所のようにひっそりと静まり返っていた。無言でグ
ラスを磨くマスターも、眉間に刻まれた皺の数を日に日に増やしている。ただ、レジーナだけは
飄々とした態度を崩さず、いつものように指定席で酒を飲んでいた。
「ま、イアソンは害虫みたいに生命力が強いからね。心配なんかしなくても大丈夫でしょ」
憎まれ口を叩きつつも、彼女も心の底では今の状況を悲しんでいるに違いない。それが証拠に、
空瓶の増えてゆくペースが普段よりも格段に遅かった。一人で寂しく飲むアルコールなど、たい
して美味いものではないのだから。
まだ昼を過ぎたばかりだというのに、重く沈んだ店内はなぜか薄暗く感じられた。どうしよう
もない居心地の悪さを感じて、リトが道具屋に戻ろうかと考え始めた時である。
「おーっす、お前ら! まさしく冒険者の鑑、イアソン様がお帰りになっ……、ん?」
いつもと同じように扉を蹴破って、けたたましい騒音と共にイアソンが姿を現した。しかし、
今となってはもう、彼の大げさな口上にまともに耳を傾ける者はいない。その事実に気が付くと、
珍しく真剣な表情に摩り替わって、イアソンはひどく忌々しそうに舌打ちをした。そして、不機
嫌を隠そうともしないまま、あまり行儀が良いとは言えない体勢でカウンター席に着く。
「マスター! 何でも良いから、とにかく腹いっぱいに食わせてくれ」
ずいぶん適当な注文をしてから、イアソンはあらためてリトたちの方を振り返った。
「やっと……、やっと抜け道の出口を見つけた。あの向こうには俺たちの求めるもの――漆黒の
迷宮があるような予感がするんだ」
「……漆黒の、迷宮」
その単語を反芻するだけで、リトの胸にも奇妙な昂揚感が去来した。イアソンもまた、普段の
彼からは想像もできぬほど、一片の余裕もない思い詰めた表情をしている。それでいて、強い意
志を秘めた“男”の顔。彼の気迫に圧倒されて、リトは二の句が継げなかった。
真実を追い求める人は美しい、崇拝の念すら抱かせるほどに――
やがて、イアソンは出された料理をものすごい勢いで喉の奥に流し込んだ。一瞬で食事を済ま
せると、ゆっくり休む間もなく席を立つ。
「じゃあな、俺はダンジョンに戻るぜ」
「あっ……」
どうやら本当に腹を満たすためだけにやって来たらしい。カウンターに小銭をばら撒いて、イ
アソンは慌しく酒場を出て行ってしまった。所在なく立ち尽くしていたリトの反応など、最初か
ら求めていなかったかのようにまるで気に留めない。扉の閉まる音だけが耳の奥で幾重にも反響
した。
「ふぅ。いつまで経っても、頭の中身が空っぽなんだから」
レジーナは彼の背中を見送りもせず、そっぽ向いたままグラスを傾けていた。そういえば、彼
女らしくもなく、相変わらず無作法なイアソンに対して一言の文句も発していない。
「わたしとの約束なんて、どうせもう忘れてるんだろうなぁ」
まあ、最初から期待なんてしてなかったけどね、とレジーナはつまらなさそうに付け加える。
「約束」という単語に引っかかるものを感じ、記憶の糸を手繰り寄せてみると、リトの脳裏に数
週間前のどんちゃん騒ぎが鮮やかに甦って来た。思い出すだけでも胸が締め付けられる、二度と
手に入らない仲間たちとの楽しい時間。
「約束って、古王の財宝を持って帰るっていう?」
「そ」
レジーナの返事は極端にそっけない。なのに、リトはまたしても自分が無遠慮な追求をしてい
ることに気付けなかったのだ。
「だったら、次に会った時に催促し……」
「でもあいつ、今度こそ死ぬよ」
「――え?」
冷え切った手のひらで、心臓を鷲掴みにされるような嫌な感覚。リトは一瞬、世界がぐるりと
反転するほどの不快な錯覚に耐えねばならなかった。彼女が今、何を言ったのかが理解できない。
「んー、今まで何人もの冒険者を見て来たからかな。なんとなく分かっちゃうの」
レジーナは顔色一つ変えず、こちらの抱いた疑問に先回りして答える。まったく取り乱さない
彼女が恐ろしくて、リトは渇いた喉の奥からどうにか反論を搾り出した。
「……だったら、どうして止めなかったんだ」
「わたしの言うことなんて聞いてくれるわけがないもん。あいつの場合は特に、ね」
「それで本当に平気なのか! 君は……、君自身の心は……!」
「ねぇリト君。どうして私が冒険者をやめたのか知りたがってたよね。理由を教えてあげようか」
リトが激情に飲み込まれる寸前で、レジーナはさらりと話題を逸らす。それでいて、彼女の言
葉には問答無用で相手を従わせるだけの力があった。強固な意志を前にして、リトは操り人形の
ように小さく頷くしかない。
レジーナは笑っていた。ガラス玉にも似た生気のない目をして。
「もう嫌になっちゃったの、何人もの冒険者が死んでゆく姿を目の当たりにするのが。どんなに
仲良くなったって、いつかみんな死んじゃうから」
「!」
レジーナの出した結論は冒険者に対する侮辱とも取れた。全身が一気にかっと熱くなる。最初
からすべてを諦める彼女の考え方を、なんとか否定し、改めさせてやりたいとリトは躍起になっ
た。
「違う、そんな考え方はずるい……!!」
「あーあ、やってらんない!」
しかし、一切の反論が許されぬうちに、レジーナは激しい騒音と共に席から立ち上がった。こ
の女性があからさまに感情を昂ぶらせる姿など初めて目にした気がする。リトはとっさに口をつ
ぐんだ。
「……なんだか海が見たくなってきちゃった」
無理に取り繕った一言が、わずかに涙声交じりだったのは思い過ごしではないだろう。レジー
ナはそのまま、誰とも目を合わさずに酒場を出て行ったのだった。
リトはイアソンの後を追うように、抜け道から続くダンジョンの存在を知った。死の匂いが充
満した、光の差さぬ呪われた場所――冥界の門。
倒しても倒しても復活する骸骨の群れを薙ぎ払い、三柱の魔神を従えたリトはがむしゃらに駆
け抜けて行った。もしかしたら、どうにかしてイアソンに追い付いて、レジーナの思いを伝えた
かったのかもしれない。こんな中途半端な状態で、彼ら二人の繋がりが潰えてしまうなんて絶対
に納得できなかった。
そして、目の前には意味ありげな石版が一枚。
「“ここは死者の通る道、引き返すことは許されぬ”、か……」
薄汚れて判別しにくい文字を読み上げながら、「石版に刻まれた文章はなんらかの警句らしい」
というイアソンの教えをぼんやり思い出していた。しかし、今のリトに警告の意味を深く考えて
いる暇はない。構わず先に進もうとすると、ふいに背後から何かが迫り来るような奇妙な感覚に
襲われた。
「な、何だ!?」
「ふいい〜、怖いのリト!」
小さく悲鳴を上げて、ファルがリトの体に強くしがみ付く。唐突に地面が激しく揺れ動いたか
と思うと、今まで辿って来た道があっけなく崩れ落ちたのだ。暗闇がぽっかりと口を開けて、次
なる犠牲者を手招きして待っている。
予想もしなかった事態を前に理性を失い、恐怖心に耐え切れず無様にわめき散らしたくなる。
だが、ぴったり密着した少女のぬくもりが、リトに不思議な安堵感をもたらしてくれた。今では
三魔神の存在は、彼にとって精神的な支えにもなっていたのである。
「大丈夫よ、リト。私たちがちゃんと側にいるから」
ティララの一言のおかげで、リトはなんとか落ち着きを取り戻した。ディーヴァも彼女の隣で
力強く頷いてくれている。迷う必要などどこにもない。
「ああ、分かってる。ありがとう……」
とはいえ、その後すぐに壊れたアストラルゲートを発見し、“警句”の意味を否応なく思い知
らされたのだった。リトは手始めに邪魔な骸骨どもを倒し、焦る気持ちを抑えながら辺りの様子
をじっと観察する。最初に北へ伸びる道を認識し、左手の脇道には後から遅れて気が付いた。先
程の一件を思うとやはり、どちらに向かうかは慎重に決定しなければならないだろう。
ふと、踏み締めた地面に違和感を覚えた。何事かと訝しんで見下ろすと、生々しい血痕が辺り
一面にべったりと染み付いている。比較的新しいものらしく、その色はまだ鮮やかな真紅のまま
だった。
「ッ……!」
直感が一つの事実を伝えている。これほどまでに的中して欲しくない予感は初めてだった。心
臓が急激に早鐘を打ち始め、もはや正常な判断力は完全に失われていた。リトは魔神たちに断わ
りもせず、血痕を辿って一目散に脇道へと進んだ。
その先はすぐに行き止まりになっており、全身を血液で汚しながら倒れ伏す人影が見付かった。
柔らかそうな茶髪によく似合う、見覚えのある真っ白なバンダナ。――紛れもなくイアソンその
人であった。
「イアソンッ!」
後頭部を鈍器で殴られたような衝撃が走る。リトは夢中で友人の側に駆け寄った。間近で見る
ほどに、怪我人の出血量の多さに絶望させられる。どう見ても致命傷だった。レジーナの不吉な
予言は現実のものとなったのである。
必死の呼びかけが届いたらしく、イアソンの虚ろな目がリトの姿を捉えた。そして、自嘲的な
笑みを浮かべる。
「ははは……、何だリトじゃないか、まさかこんな所で会うとはな」
「待ってくれ、すぐに手当てを!」
「やめとけ、薬の無駄だ……。自分のことは自分が一番よく分かってる。もう助からねぇよ……」
確かに本人の言う通り、イアソンはもはや身じろぎ一つできない状態である。焦点もきちんと
定まってはいない。全身から気力を振り絞っても、かすれ声で喋るのが精一杯のようだった。
やがて、イアソンは震える手で懐を探り、クゥの尻尾をリトに差し出した。そして、真っ直ぐ
北を目指せ、としつこいくらいに何度も念を押す。彼は死の間際になってもなお、自分が助かる
ことよりもリトへの助言を優先したのだった。
「ついでに、こいつもくれてやる。俺には……もう必要なさそう……だ……」
一緒に手渡されたのはゲートクリスタルだった。受け取った手のひらから、ひんやりとした感
触が伝わって来る。イアソンの思いをけして無駄にはしまいと、リトは漆黒の迷宮を目指す決意
を新たにした。
後から追いかけて来た魔神たちも、リトの背後で固唾を飲みながら、主人と友人のやり取りを
見守っている。さすがに彼女たちも、今は口を挟んで良い状況ではないとわきまえているようだ。
「それと……、一つだけ頼みがある。聞いてくれねぇか……?」
「ああ、俺にできることなら何でも」
「お前なら……、そう言ってくれると思った……。サンキュ……」
イアソンは最後にもどかしい手つきで、流麗な装飾の施された短剣を取り出した。エメラルド
とおぼしき美しい宝石に真っ先に目を奪われる。武器としてではなく、宝物(ほうもつ)としての
意味合いが重視されているのだろう。
「こいつを……レジーナに渡してくれ……。遅くなって……悪かった……って……」
「もしかして、あの時の“約束”の?」
「あいつ……、意外と執念深いから、さ……」
イアソンはヘヘへっ、と子供のように無邪気に笑う。そして、激しく咳き込んだかと思うと、
固く目を閉じて何も喋らなくなった。直前に「もう一遍、会いたかったなぁ」という微かな独白
が零れたような気がした。
「――イアソンッ!!」
どんなに呼びかけても、勇敢な冒険者から返る言葉はなかった。幾度となく人の死を見て来た
リトには、彼の魂が肉体から離れたことが分かってしまう。何もしてやれない自分の無力さが悔
しくてたまらなかった。
「リト、さっきから妙な地響きを感じるわ。もしかしたら、ここも崩れるのかもしれない。……
早く逃げましょう」
大地の唸り声を敏感に感じ取り、残酷なくらい冷静にティララが告げる。一緒になって感傷に
浸るよりも、主人の身の安全を確保するのが彼女たちの役目だからだ。
こんなダンジョンの真ん中では、亡骸を葬ってやることすらままならない。リトは後ろ髪を引
かれる思いで、もう動かない青年に一礼をしてから来た道を戻って行った。けして振り返らずに。
そして、一行はイアソンの忠告通りに北を目指した。途中の分かれ道には目もくれず、とにか
く街へ――レジーナの元へ帰還することだけを考える。イアソンの最期の願いを叶えるために。
思っていたよりも簡単に、無事なアストラルゲートは見付かった。譲り受けたクリスタルをは
め込んで、リトたちはようやく慣れ親しんだ場所へと戻って来ることができた。草葉の匂いのす
る空気を吸い込んだだけでほっとする。
ふと、酒場の前で立ち尽くす華奢な人影を見付けた。
「おかえりなさい、リト君」
レジーナだった。イアソンの無事を祈りつつ、再会の時を待ち侘びていた違いない。素直でな
い彼女は強がって見せるだろうが、のんびり酒も飲んでいられぬほど心配でたまらなかったのだ
ろう。
「みんな、先にイリスの所に帰っていてくれないか? 後から俺もすぐに戻るから」
リトは三魔神に小声で指示を出した。ティララとディーヴァは最初から心得ていたように素直
に命令に従う。ファルだけはしばらく名残惜しそうにリトの上着の裾を掴んでいた。とはいえ、
彼女もやはり主の意志には逆らえない。
きつく両の拳を握り締め、リトはレジーナの正面にまで歩み寄った。何から話して良いかわず
かに逡巡したものの、回りくどい前置きはやめにして初めから核心に触れる。
「さっき、ダンジョンでイアソンに会ったよ」
「うん」
「だけど、イアソンは……もう……」
言い澱んだリトに、レジーナは悲しいくらい綺麗な笑みを見せた。
「いいよ、言わなくても。リト君の顔を見てたら、全部分かっちゃったからさ。勘が良過ぎなの
も考えものかなぁ」
あくまで軽い調子のまま、彼女は霧のかかった青空を見上げていた。胸の痛みを誤魔化すため
には、すべてに無関心でいるしかなかったのだろう。今まで数多の死を見つめて来たレジーナは、
感覚を麻痺させることで自分の身を守っていたのだ。
大切な人を失った時くらい、思い切り声を上げて泣いてしまえば良いのに。涙には悲しみの浄
化作用があるのだから。いっそ彼女の頬を乱暴に打ち付けて、卑怯な逃避から目を覚まさせてや
りたいとすらリトは思う。だが、その役目はもっと相応しい人物に委ねることにした。
「イアソンは最期に、レジーナに謝ってくれって言ってたよ」
「どうして?」
「約束、遅くなったから」
リトはイアソンから預かっていた一振りの短剣を差し出した。金箔や宝石を贅沢にあしらった、
まさに王の宝と呼ぶに充分な一品である。物事の飲み込みの早いレジーナは、目の前に突き付け
られた宝剣の意味を即座に理解したようだった。
「……あいつ、忘れてなかったんだ」
彼女は心底から驚いていた。両の瞳をいっぱいに見開いて、小刻みに震えた手のひらで短剣を
受け取る。その直後、イアソンの形見をきつく胸に抱き寄せた。わずかに残った彼のぬくもりを
探すように、強く強く。
長い長い空白の後、レジーナは万感の思いを込めて吐き捨てた。今はもう、本当に伝えたい相
手には届かないけれど。
「馬鹿な男……!」
俯いてしまった彼女の表情は窺い知れないが、涙の粒がぽたりぽたりと地面に染みを作ってゆ
く。レジーナはようやく、自分の感情に正直になる方法を思い出したのだ。どんなにつらくて悲
しくても、喪失の痛みを真正面から受け止めることが、散りゆく命に捧ぐ最上の鎮魂なのかもし
れない。
「こんな物、今さら何の意味もないのに……ッ!!」
レジーナはついに幼子のように声を上げて泣き始めた。その場に崩れ落ち、短剣と一緒に自ら
身体を両腕で抱き抱える。リトはただ目を閉じて、彼女の悲痛な慟哭を全身で感じていた。
やがて、一陣の風が吹き抜けてゆく。彼女を優しく慰めるように、あるいは冷たく突き放すよ
うに、酒場の前を静かに通り過ぎていった――
END