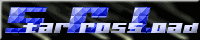「たまには昔の話をしよう」
からん。雫のついた素朴なグラスを片手に、イアソンはそう言って辺りを見回した。
誰も、いない。
学者肌の秀才も、腕っ節の強い女性も、楽しい仲間たちも。無二の親友も。
もう、ここには昔の馴染みは誰もいない。否、一人だけいる。テーブルの向かいで話を聞いてくれている、暇人が。
酒場の店主――ロックだけは、イアソンの昔を知る、生きた旧知の人だった。
あいまいな返事をする店主に向けて、ほろ苦い笑みを浮かべ、イアソンは目を閉じた。
緋色の髪をした、たくましい青年。いよいよ最後の場所へと駆け抜ける、最も新しい冒険者。ついに自分を追い抜いた勇敢な男。
リト。
いい響きの名だ。面と向かって「いい名だな」と言った日は、これほどまでに遠く感じられる昔のことだっただろうか。
イアソンは思う。
願わくば、勇敢な男に最大の祝福があらんことをと。
「ま、悪くない人生だったか」
そして、最後の冒険者は想う。
最初の日に立っていた、幼い日の自分のことを。
「充実した十年だったぜ」
それは、まだ。閉ざされた島が幾度目かの転機を迎える前のこと。
「おお、しみる、しみるっ!」
海に流れ込む小さなせせらぎにアザだらけの足を突っ込んで、ある少年が身震いしていた。
その髪は肥沃な大地のように明瞭な茶、その瞳は空よりもなお青く、ひたすら真っ直ぐと澄み渡っていて、人の心をおのずと引き寄せる。穢れを知らない、果敢な瞳。
「くそう、次こそ勝ってやる」
冷涼な水にひどく痛む稽古の傷跡に悶絶しながらも、少年は小さく一人ごちた。
独り言は青空に吸い込まれていって、やはり誰にも聞こえはしなかった。
絶えず流れていく川は、空の光を一杯に受けて、きらきらと輝きながら海への道を急いでいく。誰も気にかけることはないけれど、それは昔からずっと続いている、不変のこと。誰もが当たり前のように、この川の流れは留まらずに、海へ流れ着く事を知っている。
けれど、人は海辺より先のことを誰も知らない。霧でかすんだ青の果てには、一体何があるのだろうか。当たり前の中に謎を見出した数少ない人々は、手作りのいかだで漕ぎ出して、二度と帰っては来なかった。
彼らは、たどり着いたのだろうか。
ほんの少しの疑問を抱いて、少年は空を見上げた。海の向こうはあんなにぼやけて解らないのに、陽が高く輝く空はいつも、突き抜けるような青さでこちらを見下ろしていた。これもまた、今も昔も、ずっと不変のこと。そして、これからも変わらないこと。
天空が見せる青と白のコントラストに、思わず少年は見とれてしまった。
空は、何て大きいのだろう。彼は漠然と、圧倒されていた。無言で、少年は見上げ続けた。青の瞳は、悠然と流れる雲と、晴れ渡った上空の大海を、魂が吸い込まれそうなほど、見つめていた。
まだ踏み出して間もない少年の背中を、優しい風が後押しするかのようにそよぐ。
「すげえなあ」
少年が空を見上げて言った一言は、たったこれだけだったけれど、その声は心にあるありったけの感服を含んでいた。いつまでも変わらない空に、永遠に旅をする雲に。
そうして、空の美しさを見上げ続け、ついに空に心が届くかと思った時。
かさり。
突然、少年の思考を現実に引き戻すように、川のそばの草むらから物音がした。同時に、ひょいと魂も心も、少年の身体の奥にある定位置へと引っ込んだ。
「何だ?」
見上げすぎで首が痛くなっていた事もあって、少年はゆっくりと首を物音の方向に向けた。何事だろうと、少し眉をひそめながら。
何かは解らない。しかしながら、少し背の高い草をゆらゆらと揺らしながら近づいてくる、得体の知れない何かが、確かにいた。
(師匠か?)
とっさに少年は己が師匠と―今のところは―呼ぶ人物を思い起こしたが、それにしては小さな足音だった事にすぐ気付き、それでないと確信した。
(もしかして、魔物か!?)
暗闇を好む獣人(コボルト)も、狼も、決して陽を見ないわけではない。先輩冒険者の話を聞いておいて良かったと感謝しつつ、少年は水際に素早く寄って、無造作に打ちすててあった練習用の短い槍を取るや否や、構えた。水の中というのが、足を取られて問題になるかもしれないが、まあ何とかなるだろうと甘く思いながら。
かさかさ、かさかさ。草を掻き分けて、真っ直ぐと向かってくる。少年はひりひりとする緊張感の中、草むらから飛び出してくるであろう相手に、決して警戒を怠らない。
しかしながら、実を言うと、この少年は狼はともかくとして、コボルトという魔物が、一体全体どういう形をしていて、どういう生き物なのか、まったく知らない。それが余計に彼の神経をすり減らしているようで、いつ飛び出してくるか解らない相手に、この少年は少なからず怯えていた。
それもそのはず。彼はこの閉ざされた島にやって来て、まだ一週間しか経っていない、全てを失ったままの少年なのだから。
それ以上に、この槍使いの少年はまだ見習いで、地底回廊はおろか、王の墓所にも行っていない、本当の新米だったのだから。
「うおおおおおっ!」
少年は果敢に吼えながら鋭い槍の一撃を突き出したが、同じように槍を構える大男の前でそれは無意味だった。
「ダメだ、足元が甘い」
大槍を棒きれのように軽々と振り回し、男はひょいと少年の足元をすくった。
たちまちバランスを崩し、少年はべしゃりと情けない音を立てて、潰れたような声を上げながら地面に倒れて広がった。
「ぐえ、じゃねえよ。ほら、立て。もう一戦やるんだろ?」
白髪混じりの大男が苦笑いしながら、少年に手を貸した。
少年は男の手を取るも、すぐさま負けじと立ち上がり、お礼の代わりにぎらつく対抗心を剥き出しにして槍を構えた。
「当たり前だ! クーガー、今日という今日は」
「解ったから、それ以上言うてくれるな。そんな台詞じゃあ、まるですぐやられちまう悪役だぜ」
びゅうと音を立てて振るい、大男は新米冒険者の――正確には、新米冒険者の卵の――少年の言葉を切り裂くかのように、大槍を担いだ。その一連の動作は余裕に満ち溢れ、豪快そのもの。豪放磊落とは、まさにこの男のためにある言葉だと少年以外の誰かがいたのなら言ったに違いない。だが、少年はあいにくと、そんな言葉はまだ知らなかった。
ありふれた基礎的な攻撃に、基本から編み出した動作を織り交ぜて、少年はまたも突撃する。まだ槍を担いだままの巨大な師匠に向けて。
「ふむ、覚えが早いのは感心なんだが」
ぼやきながらクーガー氏は槍を構え、すぐさま動作に移った。茶髪の少年は思わず回避に移ろうとするが、時すでに遅し。
気が付いた時には、上着を槍の穂先に引っ掛けられて、ぶらぶらと空中で揺れていた。つまりは、まだ小柄な少年の足は地面についていないわけで。決着が一瞬だった上に、それは少年にとって、もっとも最悪で屈辱的な終わり方だった。
「くくっ、ちとお前は蛮勇なんだよ、イアソン」
ぶら下げられた姿を面白そうに笑う男に、在りし日のイアソン少年は顔を真っ赤に染めながら、じたばたしていたのだった。
「うるせえ、離せ、降ろせー!」
じたばたじたばた、暴れて槍を揺らすが、一向にひっかかった槍は取れない。身体が無駄に揺れるだけで、正直まったく変化はないのだが、それでも少年は懸命に暴れ続けた。
「解ったから暴れるな。お気に入りの一張羅が破けちまうぜ」
ぴたり。クーガーの一言でようやく動きを止めたイアソンは、しばらくまたぶらぶらとしていたが、やがて止まって、槍から解放された。この新米の少年は、すぐに青い上着を羽織りなおして、むすっとした顔で大男を見上げた。
「吊るすなよ」
「はは、悪かった。そう気を悪くしないでくれ」
頭を鷲づかみにするような大きな手が、イアソンの頭の上に遠慮なく置かれた。そのまま頭を掴んで、持ち上げられそうなくらいに、その手は大きい。おまけに年季の入ったタコでごつごつとしていて、固かった。
そんな手でぐりぐりと頭を撫でながら、この師匠は決まってこう言うのだ。
「何しろ面白くてな」
そして、イアソンは必ずこう言い返す。
「弟子で遊ぶな、師匠が」
「悪かった、本当に。まあ、何だ、酒場に飯でも食いに行こうぜ、弟子」
イアソンの一言をますますおかしく思ったのか、クーガーは大きく口を開けて一しきり豪快に笑ったが、この弟子の少年がますます不機嫌な顔をすると、頭から手を離して外を指差して言ったのだった。これもまた、いつも通りの展開で。
「師匠のおごりだからな」
「ああ、ああ、解ってるさ。ほれ、行くぞ」
そうして、最終的には彼らはいつもこうやって、連れ立って酒場に歩いていく。という事で、決して二人は不仲な師弟というわけではないのであった。
「で、師匠。最近、姉貴は元気してるのか?」
まだ知らぬ未来より大きな街を悠々と闊歩しながら、二人はとりとめもない世間話を交わす。とりとめもないという限り、内容は大体はありふれたゴシップ。それから、時々は冒険者達の最近の状況。そして、ごくごくまれに、イアソン少年の姉弟子の話と言った至極身近な話をちらほらと。とにかく、彼らの「とりとめもない」とはそういう事で、本当に、とりとめがないのだ。
「おうよ。男だろうと一ひねりで負かしちまう、超一流の女戦士だぜ。さすが、俺の最初の弟子ってところだ」
己が腕を叩いて、クーガーは大股で歩きながら、からからと笑った。
「へえ。姉貴、いつも思うけど、すげえな」
「へへ、すげえだろ」
歩幅の差で追いつかない分、小走りをしてイアソンはクーガーと並ぶ。屈託の無い笑顔で、素直に姉弟子に対する尊敬を見せる姿を見て、クーガーも誇らしげに胸を張って、ますます背丈が大きくなったように見えた。
「お前も、姉貴分に負けねえように、デカイ奴になれよ」
この心も身体も大柄な師匠を見上げながら、イアソンは自信ありげに微笑んで、師匠の口調を真似て言った。
「おうよ。今に追い越してやらあ」
海から来る潮風を感じながら、二人はさまざまな物を通り過ぎて、酒場に向かっていく。
冒険者御用達の、二階建ての薬草屋、兼ね医者。ここの本当の主人は、いつもいつも、不在。
これもまた冒険者のお墨付き、鍛冶屋兼ね武具店をしている一軒家。頑固な親父がうるさいけれど、腕は確かで人気が高い。
郊外にあるもう一つの武器屋は、近頃営業停止中。何を思ったか、留守にする事も多いようで、どうしたのだろうと町中からの疑問の的。
街の真ん中に建つ図書館は、六つになる双子の娘さんと一緒に、仲むつまじい冒険者夫婦が経営している。イアソンは、まだ図書室に入った事はなかったけれど、時々彼の師匠が出かける事は知っていた。
ぽつんと立ちつくすゲートは、昼は閑古鳥だけれど、朝になれば出かける者、夜になれば帰る者がやって来る。少年にとっては、未だ知らぬ果てしない、そして魅力的な旅の入り口に見えていた。やはり、興味があるだけに、目も輝く。
「何、お前もすぐ使う事になるさ。さあて、急ぐ理由はないが、急ぐかな」
それを見たクーガーが軽く言って、少し歩調を速めると、たちまちイアソンは本当に走らなければならなくなった。視界から、一気にゲートがいなくなると、後に残るのはもう、ひたすら大きな彼の背中と、海沿いに続く路の果てにある、桟橋の風景だけだった。
視界の向こう側にある、本当の意味で使われる事がない小さな桟橋には、遊び半分にいかだを造る少年達がたむろしていた。彼らもまた、戻らない船出をするのだろうか。満面の笑みで、不ぞろいの木材を組み立てては、好奇心の満ち溢れた眼差しで青色の果てを見つめていた。
様々な人々の群像が、島に来て間もない少年の視界をよぎっては、後方へと別れを告げていく。
何もかもが、当時のイアソンにとっては眩しかった。
永遠に広がるように見える草原も、郊外に広がる広大な小麦畑も、街に溢れる家々も、未知に挑む勇敢な先輩冒険者たちも。彼の視界には輝いて見えていた。触れたい、もっと、もっと知りたい。尽きせぬ憧憬と探求心が、この茶髪の少年の心の中ではいつも燃え上がっていたのだ。まだ伸びきらぬ、小柄な身体の中から溢れ出すほどに。
「おし、到着だ」
ようやく目的地に着いて、足を止めたクーガーが看板を見上げた。イアソンもつられるように酒場の看板を見上げて、好奇に心臓を高鳴らせた。
そう、この時もそうだったのだ。何しろ彼にとって、その知らないものの一部に出会える場所こそが、酒場だったのだから。
少年にとって、ドアを抜けたそこは、魅力に溢れた未知の領域。不思議な別世界。
「よーす、お前ら元気してるか?」
まずはクーガーが体格に似つかわしい大声で挨拶する。すぐに彼をよく知る冒険者の何人かが、笑顔でこの大男を迎え、手で招いた。手招きの場所へ、二人はのんびりと歩いていった。
島の人々が憩いを求めて訪れる酒場は、見知らぬ未来のそれよりも幾分か大きかった。
ごった返すとは言わないまでも、人はやはり多い。ここではいつも、ベテラン新米問わず冒険者達が自分の物語を語り、学者達がそれを見聞きして島を知り、どちらでもない人々が、物語の数々に微笑み、泣き、怒り、大きく笑っていた。
この島に来て一週間しか経っていないというのに、何と懐かしい世界なんだろう。まるで昔から、ここにいたようだ。イアソンは、こういう気持ちを湧き上がらせてくれる、真新しくも懐かしい、この酒場の空気が大好きだった。
「ちと邪魔するぜ。こいつもな」
今日この日、クーガーが座ったのは、女性をはべらす若いナイフ使いと、もうすぐ壮年になろうかという剣士の腰掛けていた円卓だった。
冒険者二人は大男と、少し小柄な少年に軽く挨拶をして、席を勧める。二人は、それぞれ自分の身長に見合った椅子に座った。もっとも、イアソンはそれでも足をぶらぶらさせていたが。
「アルコフ、タルバイン、しばらくだったな」
久々に出会ったのだろう、イアソンの横で、大男があごに生えた無精ひげに手をやりながら、テーブルの先客二人へと挨拶を返す。弟子の少年は挨拶をしながらも、この二人を交互に見比べる。
「おおっ、君が噂のイアソン君かい。うんうん、将来有望だねえ」
若いナイフ使いは、鮮やかな青の髪が印象的な細身の青年。赤茶の瞳をまたたかせながら、こちらを興味深げに見つめている。彼の肩に手をかける女性は、彼の耳に何やら質問を投げかけていたようだったが、やがて挨拶もなく、ぷいとそっぽを向いて行ってしまって、イアソンが彼女の正体を見極める事は出来なかった。
「なるほどな。いやいやクーガーは人使いが荒いから、苦労しているんじゃないのか」
一方の壮年一歩手前の剣士は、人の熱気で蒸し暑い酒場にも関わらず赤い鎧をまとったままで、無理もないが少し暑そうにしていた。赤い鎧の戦士は手で顔のあたりを扇ぎながら、もう片方の手を、微笑ましいと言わんばかりの表情を添えて、イアソンに対して好意的に振った。
「えっと、あの」
こういった自分の見知らぬ世界を知る人を知りたいはいいが、少年は何を言うべきか解らず、ついつい言葉を詰まらせてしまった。が、すぐに青髪の青年が会話の潤滑油に変身して、テーブルに囲まれた四人の世界をぐいぐい動かしていった。
「ああ、まずは自己紹介をしなきゃね。ボクはアルコフ、一応歩く鍵って事で通ってる。つまり、罠解除担当ね。そんで、こっちの剣士が」
ちらと赤茶の瞳が戦士に向けて動くと、赤い鎧の男は頷いて、イアソンにその茶色の瞳を合わせて自己紹介を繋げた。
「俺はタルバイン。戦力不足のこいつをガードする、見ての通りの剣士だ」
「戦力不足とは失礼な。ダーツ、ナイフ、ボウガン、果ては吹き矢。飛び道具なら、ボクは何でもござれよ?」
「で、接近されたらどうするんだ」
タルバインの冷たい問いに、アルコフはちちち、と指を振って、懐からダーツを取り出した。
「ダーツで突き、突き、突きぃーっ! ね、こう、ぶすぶすぶすっとね」
冗談めかしてアルコフがダーツを刺す真似をすると、すぐさまタルバインが切り返した。
「十分すぎるほど戦力不足だろうが! と言うよりも、待て。せめてナイフにしろ、ナイフに!」
まるで申し合わせたように、この二人組は漫才のように言葉を交わした。近場のテーブルから聞こえた、またかよ、という別の冒険者の笑い混じりの一言が、上手に相槌代わりになって、周囲はたちまち笑いの渦に包まれた。もちろん、その中にイアソンもクーガーもいて、笑っていたのだった。
それだけ、長い間の付き合いなのだろうと、イアソンは直感した。彼は知らなかったが、本当にそうなのだ、この二人組は。
二人組の漫才じみた会話は、なおも続く。
「ではイアソン君、早速今度ナンパの方法を君にも伝授、あだっ!」
がつんと一撃。タルバインの見事な一撃が、相棒のアルコフの脳天に決まった。
「いたいけな少年に教育上よろしくない事を教えるな、よろしくない事を! しかもお前、子持ちのくせに何て事を!」
「あいたた、タルバイン、ぐーは無いでしょ、ぐーは。もう、ちょっとしたジョークよ、男のロマンとも言うけど」
「やかましい。まったく、純情な少年に何て事を教えようとするんだ。お前は」
ぶうぶうと非難を浴びせるアルコフを、赤い鎧の戦士は一蹴する。それが駄目だと理解した青髪の青年は、大げさに頭を抱えて、ひどくうめいた。
「うう、本当に痛いよ、頭が変形しちゃったらどうするのさあ」
「するか、阿呆。俺は手加減している。それで変形したら、お前の頭蓋骨が軟弱なだけだ」
「タルバインの頭は貧弱」
「いらん方向に混ぜっ返すな、アルコフ!」
「だって真実じゃん、謎解き一つ出来ない、で、あだっ!」
ごつん。がつん。頭に連発された拳骨に、冒険者アルコフは炒めた玉ねぎのようにしんなりとなって、沈黙した。本当に頭が変形してはしないだろうかと、イアソンが不安そうにうかがう中、見る見るうちにたんこぶがふくれ上がった。ある意味、アルコフの頭は変形した。
「すまないね、イアソン君。うちのアルコフが迷惑を掛けて」
いやいやと慌てて―少なからず怯えて―首を横に振って、イアソンはタルバインに応じた。
タルバインはしばらくの間、イアソン少年をじろじろと見つめていたが、その内に納得したように大きく頷いて、白い歯が輝く笑顔を見せた。
「ふむ、筋肉もしっかりしているし、骨も太い。冒険者としても将来有望そうだね。おじさんが鍛えてあげようか。剣術も必要だぞ」
「イアソン、注意しろ。タルバインは子ども好きでな。アルコフの女好きよりひでえんだ、これが」
即座にクーガーの警告が入ったところで、この新入りの少年はようやく緊張をほぐして、周囲の冒険者たちと一緒になって笑ったのだった。
たくさん、聞いた。アルコフ達の語る、楽しい旅の話を。
「それでな、海岸洞穴の人魚のお姉さまがね」
「お前というヤツは……すぐその手の話題にしようとするあたりが――」
「ああん、タルバインったらつれなーい。寂しくて死んじゃう」
「き、気色悪い声を出すんじゃない!」
けれども、そのうちにすり替わってしまった難しい大人達のお喋り続きで、イアソンはいつの間にか、うつらうつらと気持ちの良い夢の中へと去っていってしまった。
とどのつまり、過度の緊張が、さっさと少年を夢の布団の中へと引きずり込んでしまったのだ。
稽古疲れとも、言うのかもしれないが。
閑話休題。
そういう訳で、酒場の一件からしばらくの後、火照って痛む稽古の傷を冷やすために川に来たイアソンは、今油断無く槍を構えていたのだった。
(何が来る。狼か、コボルトか、それともスライムか!)
物陰はより一層近づいて、ついにほんの少しの草むらの向こう側にまで来ていた。そして、いよいよ。
がさがさ、がさっ。
(来た!)
イアソンはより一層、警戒した。初めてになるであろう、戦いに。
「お?」
ところが、その姿を見ると、イアソンは目を点にして、奇妙な声を上げ、思わず槍を降ろしたのだった。
姿を見せたのは、華奢な子どもだったのだ。草原に似た緑の髪が印象に残る、傷だらけの。
Last Update:
2005-06-30
Written by 皆川 新茶
Edited by ダイス
Powered by PHP
Powered by Lolipop