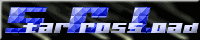「じゃ、今日も行ってくるよ」
リトが冒険者の仲間入りをして、二日目の事。
彼が今訪れているそこは、新入りの通過儀礼として知られる冒険の入り口。人は、王の墓所と呼ぶ。
「――――!」
白い刃の一閃が、どろどろの身体を貫く。彼らは地面に融け、やがてその跡も消えていく。消滅を確認せず、振り返ってもう一体にも止めを刺す。こんな事を、もう何度も繰り返していた。周囲からその気配がいなくなるまで、短剣を振り、突き、払うの繰り返し。いなくなれば、自分に出来た生傷の手当て。そして、しばらくしないうちにまた現れ……墓所に踏み込んでからは、こればかりだ。
王の墓所に住まうこのスライムは、この島において最下級に位置する魔物だというが、それでもその粘性の身体と不定形ゆえに取れる動きは、新米冒険者には非常に厄介な相手だ。本来ならば、ダガーよりもロングソードといった斬撃に特化した武器の方が彼らに大きなダメージを与える事が出来るのだが、それが無い以上、リトは手元の短剣で挑むしかなかった。戦いは常に長期戦で、唯一の治療薬である薬草のストックは急速に減っていく。リトにとって、目下最大の不安要素であった。
「スライムにてこずっているようじゃ、まだまだだな」
それからもう一人。スライムの体液を一振りで払い、剣を収めてリトをからかう男もここにはいた。腰には一本の剣、その背中には身長と同じくらいはあろうかという長い、使い込まれた槍が背負われている。この姿を見て、この島においてリトの同業者の一人――冒険者――ではないと言う者はまずいないだろう。
「さあて、ユリアンとシアを探しに行かねえと……二人とも思い込んだらすぐ駆け出すから、早く見つけてやらないと……。」
彼は心配はしているもののぽりぽりと頭を掻いて、槍を背中に能天気な表情で天井を見上げる。その背後から、音も無くスライムが粘性の身体を広げて襲い掛かる。先に気付いたリトも、彼へと声を掛けようと口を開こうとする。だが、それよりも彼の動きの方が数段速かった。
鞘から剣を外す、小さな金属の音。刹那。
「っと……!」
一閃。剣が輝く銀色の弧を描き、その動きを止める。彼はスライムをその一刀の下に斬り捨て、再び剣を鞘の中にしまってため息を付いた。そして、スライムをあらかた片付けたリトの動きを見、ふっと目を細めて呟いた。
(だが、センスはいい。これはうかうかしていられないな、俺も)
戦い終わって安堵の息を付くリトの背をばしっと叩き、彼は意気揚々と一本道の奥へと進んでいく。あまりに強く叩かれてむせかえっていたリトも、やがてその闇へと吸い込まれるように進んでいく。その先で飛び回るいくつもの羽音を聞きながら……。
――――島の中で最も漆黒の迷宮に近い男。それが、リトを先導するかのように歩く冒険者であった。リトが彼と知り合ったのは酒場であり、向こうからしてみれば、それは丁度酒場のマスターから新人冒険者の保護を依頼されていた時であった。お互いに行き先が同じという事で、少しの間の道連れである。
リトはその仕事内容を知らない。だが、時々思い返しては少々不服そうにしているところを見ると、実力からすれば割に合わない仕事なのだろうと推察出来た。だが、それは思い返した時だけで、それ以外は非常に落ち着いた手馴れの貫禄を見せている。少しの事では動じない、ゆったりとした余裕があるのだ、彼は。その言動は、何処か飄々とした雲をも思わせる。
(今の俺とは、随分違う)
リトもその言動に感服せざるを得なかった。その余裕があるからこそ、彼は今一番の実力者として酒場でも注目されているのだ。だが、彼は誰からの評価も気にも止めず、我が道を突き進んでいく。ただ、文字が読めないのは彼にとって非常に大きなハンディキャップとなっているようで、時折予期せぬ罠にかかってしまうらしいが。
……湿った泥を踏みしめるたびに靴から伝わる、ほんの少し沈み込む感触。程よく湿った地面は、砂埃を舞わせる事もない。戦う側としては、この安定した足場はありがたい。これもまた、ここが通過儀礼として冒険者が最初に訪れる理由の一つだろう。
「んじゃ、一旦ここでお別れだな。ちゃんと生きて帰ってこいよ、新米。生還の記念に、酒くらい奢ってやるからさ」
歩きながら、基礎知識云々を教えてもらいつつ――むしろ一方的に聞かされつつ――、この島に点在する転送装置、ゲートクリスタルまで来て、リトは休憩を取る事にした。支障はさして無いにしろ、まだまだ身体は重く、完治とは言い難い。彼はどうやら先を急ぐらしく、軽く一言残して次の道へと向かって行った。鼻歌まで歌って、余裕綽々の様子だ。まず、こんなところで死ぬ事はないだろう。酷い罠があって、彼がそれに手を出さない限りは。もっとも、そんな事をしているなら、きっと彼はあの実力までたどり着けなかった訳で。この心配が杞憂である事など、リトは百も承知だった。
(よし、今日は少し休憩したら、もう少し奥まで行ってみよう)
リトはそう思いながら、身体を休める間、しばし酒場のひと時を思い出し始めた。
あれは、ここでしばし鈍った身体を慣らし、一度街へと戻った時だった。彼は道具屋に戻る前に、その日はイリスに勧められていた酒場へと足を向かわせたのだ。そこには実に個性豊かでたくさんの同業者達がいた。
酒の匂いと、ほんの少し気だるい空気。酒場特有のあの雰囲気の中にいた冒険者達は皆、自分と同じように記憶を失っていて、漆黒の迷宮を目指していた。それなのに、誰もがとても生き生きとして、それぞれの休息の時を過ごしていたのだ。
「ねえ、タルバインってばー!」
「ええい、やかましい、グレッグ!こいつめ、今回は無事だったから良かったが、罠の解除に失敗してからに……!」
無邪気な笑顔で相棒に呼びかける青い髪の少年グレッグが、大柄な戦士に一発頭を殴られたのを見た。手加減こそしていたようだが、それは彼の頭にたんこぶを生やすには十分すぎる程の威力だった。
「うー、解ってるってば!殴る事ないじゃないかあ……!」
「……。」
彼は頭をさすりながら涙目で見上げて訴えるが、それっきり相棒の反応は無し。その途端にグレッグの表情が憮然としたものになる。そして、彼がちょっと酒から目を離した隙にテーブルに置いてあった調味料――私たちで言うところのタバスコ――を投下、後は何食わぬ素振り。その後、ほろ酔い加減だった戦士タルバインの素面に戻った絶叫が酒場にこだましたのは言うまでもない事。それから、グレッグのたんこぶがもう一つ二つ増えた事も。
「あーもう、うるさいったらないわ!タルバインは声が大きいのよ、解る!?」
先の図太い絶叫に気分を害したか、物凄い剣幕で迫る短い金髪の女性がタルバインに食って掛かる。今度は不意打ちを食らった彼がたじろいだ。若干、唇が腫れ上がっているのは目の錯覚が見せているものだろうか。
「ハティ、その辺で……ね?」
その彼女を羽交い絞めにして、緑の髪の華奢な青年が必死に止める。前者の女性は見るからに気が強そうで、女傑という言葉がよく似合いそうだ。それとは全く正反対、後者の青年はいかにも気が弱そうだった。線も細いが、神経も細そうだ。しかし、彼らのいたテーブルに立て掛けてある棒杖は彼のもので、つまり、彼も冒険者の一人だという事の印だった。
「止めないでよ、ビンセントッ!」
「あ、う……、はい……」
案の定、強烈な一言に一喝されたビンセントが縮こまって身を引く。大柄なタルバインの背も、この時ばかりは少し小さく見えた。グレッグが少年らしい悪戯っぽい笑顔を浮かべて――しかし本当に楽しそうに――その様子を見ている。最も、リトもすぐ近くのカウンターでこの様子を呆気に取られて傍観していたわけだが。どちらとも、幸いにしてハティ嬢のとばっちりは免れた。
「それじゃ、いただきまーす!」
そんなケンカの状況など何処吹く風。まったく気にする事なく、ひれ料理を山盛りにした皿を目前にし、奥のテーブルで長い茶髪の可愛らしい少女がにんまりと嬉しそうに笑う。それを呆れたように眺めながらくらげの刺身をつつく、金髪を束ねた青年が彼女の向かいに座っていた。
「う? ミルコ、食べたい?」
「いや、腹の余裕がねえ。今回はいいや」
少女が皿に乗った料理にフォークを刺して彼に近づけるが、彼はそっけなく返す。この態度に少し頬を膨らませ、やけ食いのように彼女はもぐもぐと料理を頬張る。その速さと言ったら。彼女はあっという間に、山盛りのひれをぺろりと平らげてしまった。これには彼も仰天する。くらげの刺身は、まだ半分も減っていない。
「今度は一緒のメニューだからねっ!スライムゼリー、お腹一杯食べるんだからねっ!」
「へいへい、解ってますって。だけど、それより前にコウモリのスープだ、これは前からの約束だろ?」
よく料理について話し合っている二人。グレイスとミルコもまた冒険者である。二人で食材探しに出る事もしばしばで、それを使った酒場のマスターの料理はまた格別、とのこと。そのマスター、ロックはといえば、酒場の様子を平和だなあとでも言わんばかりに眺めている。どうやら、ハティを止める気はないようだ。それとも、いつも結局のところビンセントが健気に血の気の多い彼女を止めてくれるのを知っているのか。もう一度にぎやかな騒動を見やれば、彼は果敢にも彼女に再挑戦していた。
「ハティ、落ち着いて、落ち着いて」
「これが落ち着いていられるものですか!前々から、ずっと思っていたんだから!」
どうやら、当分かかりそうだ。リトはそれ以上の傍観を止め、ふと隣にいた人物に目をやった。
「ふう……無事帰還した後のお酒は、やはり格別ですね」
リトの隣のカウンター席に座っていた男性が落ち着いた様子で息を付いていた。のほほんとしながらも知的な印象を受けるその眼差しと中性的な容貌が相まって、冒険者と言うよりも詩人と言った雰囲気を漂わせている。だが、腰に下げられた一本の細身剣は、彼もまた冒険者であるという事を誇らしげに証明して見せていた。
「おや、あなたは……。ふふ、イリスさんにはお世話になっているとお伝えください」
視線に気付いた彼は礼儀正しくリトに会釈した。彼は道具屋にリトが居候している事をすでに知っている。昨日、薬草を買いに来たからだ。言うなれば、リトが初めて出会った冒険者なのだ、彼は。
「ポロス、ちょっといい?」
彼は声を掛けられて後ろを振り向く。まだ打ち解けきれず、何処に視線を向けていいやらで、リトも結局一緒に振り向いた。そこでは黒髪の少女が青髪の少女と一緒に食事をしており、丁度その手を休めて彼に問い掛けていた。
「墓所、到達できそう?」
「いいえ、まだですね。いずれは踏み入ってみたいものですが……」
どうやら、王の墓所以外にも墓所があるらしい、とリトは解釈した。雰囲気から言って、冒険者曰くの新人通過儀礼でまだてこずっているとは到底思えなかったからだ。
「それに、きっと私よりもピリカの方が早いと思いますよ。私は見ての通り、呑気者ですから」
「いきなりわたしを話題に上げるな、ポロス」
「あはは、すいません」
向こうから赤髪の女性が苦笑交じりに彼へと声を掛けるが、彼はそう言って、後はのんびりと頬に手を当てて微笑むばかりで、それ以上答えなかった。二人の少女もお互いに顔を見合わせて和やかに微笑み、また食事を再開している。リトはまた視線を巡らせてみる事にした。
少し向こうでは、酒を交えて語り合う長い金髪で青い瞳の女性と短い黒髪の男性がいる。その雰囲気は他とは少し違っていて、どちらかといえば、リトに似ていた。つまり、二人からリトが感じたのは独特の、自分とそっくりな新米の雰囲気。ここにいる彼と彼女こそ、先ほどの冒険者が現在探しに行っているユリアンとシアなのだが、当時のリトに知る由はない。
ピリカと呼ばれた女性のいたテーブルの近くを見やれば、女性が軽く手を振って彼に応えた。彼女は酒場にいて、新人に生き残る術を教えてくれる、言わば教官と言ったところだろうか。名前をナインと言って、熟達した冒険者達からも慕われているところを見ると、ずっと前からここにいて、生存術を教えているらしい。物静かで、不必要な事は語らないよう人物のように思えた。ここには大まかに分けて二種類の人がいる。片方は彼女のように酒場にいて新米に生き残る術を教えてくれる人物、もう片方はこの小さな島を所狭しと渡り歩き、自分と同じように旅をする人物だ。例えば、ポロスやハティ、そして墓所の向こうへ進んでいった彼などが、その冒険者の代表格だろうか。
「お、やっほー」
目が合った途端、もう一人の女性も元気良く手を振って返してくれた。ナインと同じく生存術を教えてくれるレジーナという人物は、彼女とは対照的に明るく奔放な印象を受ける。ちなみに、この直後に彼女は何処かへ出かけてしまったので、残念ながら話す機会はなかったが。
リトは一通り視線を巡らせ終え、自分の手元にその視線を落とした……。
「……」
いつの間にか、彼は自分の手に視線を落としていた。酒場の時のように。その様子に何を思ったか、彼は小さく笑う。彼はそのうちに立ち上がり、休憩を終えて先へと進む事にした。好奇心が押さえられない。もっと、この墓所のいろんな場所を見たかった。気が急くままに、彼は進む。
遠い昔に壊れた守護達の残骸を横切り、彼は歩く。隠し通路の証、かすかな風に注意しながら。足音は湿った地面に吸い込まれて、ほとんど聞こえない。聴覚の優れたバットならば、即座にこちらに接近してくる可能性もある。しかし、今の所いるのはスライムの類ばかり。彼らの感覚は決して鋭敏ではない。ところどころにある目も、実際に獲物の姿を確認しているかどうか。それでも地面の振動には敏感だというが、こんな地面ではそれも叶わない。そういう訳で、リトはスライム達に気付かれる事なく、意外とあっさり墓所内を通過していく事に成功した。
「ふう、大分来たな……」
いよいよ墓所も深くなり、いつの間にか足場は石の床と化した。閉鎖された空間独特の、部屋から部屋へと反響していく乾いた足音が緊張感を誘う。彼の顔にも、先ほどよりずっと強い警戒の色が表れていた。この辺りともなると、群れで行動するバットの類が多数飛び回り、ゴーレムと呼ばれる侵入者排除のために生み出されたからくりの『守護』達が、いかにも技巧的な動きで歩き回っている。ゴーレム達の亡者に良く似た眼差しは、何も映しはしない。だが、触れたり目の前に出たりすれば、無論侵入者として排除されてしまう。もちろん、ダガー一本のリトにまず勝算はない。ここでリトは初めて事の重大さに気がついた。
例えば、スライムに威力を発揮する斬撃特化の剣や、バットを打ち落とせる弓、土くれのゴーレム達を砕く打撃武器など。例の先輩冒険者曰く、冒険者として生計を立て、生き抜くには、そういうものを探す事も重要なのだとの事。あらかた奪われたとはいえ、この王の墓所にもまだまだそういった武具が眠っている。リトは好奇心のままに、進む事だけを考えて、一気に下ってきてしまったのだった。つまり、宝箱にほとんど手を付けずここに来てしまったわけだ。
(このダガーじゃ先に進むのは少し無理、みたいだな)
ため息を付いて、自分の焦りを悔い、彼はその行動に対し、かすかに後悔の苦笑いを浮かべた。
きい、きい。少し向こうの暗がりでは、来訪者を招くかのようにコウモリ達がせわしく飛び回っている音がしている。
(ここで一旦戻るか、それとも先へ行くか)
選択肢は一つしかない。いくら新米といえども、この状態で先へ行く事の危険さは容易に解る。リトは、一旦装備を整えるべく、踵を返してスライム達の塒へと向かおうとした。しかし、そうは問屋が卸さなかった。こんな絶好のカモを、彼らが逃がす事などするはずがない。
『きい、きい、きいぃぃ……』
羽音と共に、その甲高い鳴き声が近づいてくる事に、リトは気がついた。しかも、かなりの速さで。数も一匹ではなさそうだった。今ここで逃げたとしても、逃げ切れるかどうか。否、逃げ切れない。覚悟を決めて、リトは短剣を抜いた。
少しの時も待たず、緑の羽音が目前に迫った。それは本当に一瞬のことで、彼が短剣を抜いた時には、すでに彼らはリトの周囲を取り囲んでいた。くるくると飛び回り、彼らは金切り声で鳴き喚いて獲物を歓迎している。周囲を見回せば、全部で五匹。
「くっ……!」
早速急降下してきた一匹に狙いを定め、ダガーを振る。だが、ひらりと身を躍らせ、バットは彼の腕に勢い良く噛み付いた。それに向けて、リトは短剣を突き刺す。傷は負ったが、一匹、何とか仕留めた。だが、すぐに次のバットが飛びかかる。今度は一匹だけとは行かない。出来る限り冷静に、抵抗を試みる。
記憶の霞の向こうで誰かが囁く。冷静さを失った時点でこちらの敗北だと。よく見て、よく狙えと。不思議と頭痛はしなかった。リトは無意識の内に、その言葉を受け入れ、冷静さだけは決して手放そうとしなかった。それが幸いして、もう一匹。さらに一匹。確実に狙いをつけて、一匹に集中し、撃破していった。
確実にバットの数は減っていき、残りは二匹。だが、自分自身を囮に使ったこの戦法は、彼に最悪の状態を引き起こさせた。
「――――!?」
突如、ガクンと膝が崩れ、リトは自分の意思とは関係なくその場にくずおれた。一体何が起こったのか、しばらく彼自身にも解らなかった。しかし、そう長くしないうちに、その原因に気がついた。否、腕から流れる血を見れば、嫌でも気付かされる。異様に青紫色に腫れ上がった腕を見れば。
(しまった、毒が回ったのか……!)
そう、バットの牙には毒があるのだ。だが、解き既に遅し。目が霞み、意識が遠のく。身体が麻痺して思うように動けない。旋回するバットが、こちら目掛けて急降下してくる。逃げられない、避けられない、動けない。目を閉じ、あまりにあっけない自分としての時間の幕切れを予想し、彼は悔いても悔みきれなかった。
ところが、何の因果か、気まぐれな幸運の女神は彼に凶悪なまでの悪運を授けた。
彼の頭上で、風切り音と共に白銀の旋風が巻き起こる。その一撃で、一匹のバットは形さえも残さず吹き飛んだ。その直後、リトは自分を覗き込む人物が誰か、すぐに気がついた。茶髪に青の瞳、トレードマークの白い鉢巻とくれば、つい先ほどまでの旅の道連れ。
「わずか二度目の探索でバット三匹、上等だぜ、新米君。ま、ちょいと運は悪かったみたいだがな」
案の定、彼は健在だったのだ。その後ろでは、二人の冒険者が待機していた。一人は弓を番え、最後の一匹に狙いを定めている。いよいよ頭にまで痺れが回ってきたのか、リトはその姿をほとんど確認する事が出来なかった。
「悪いな、こいつも手前らみたいな奴らの餌にする訳にはいかねえんだ。マスターの頼みでな」
知能のないはずのバットが、その威圧に怯えたように見えた。不敵な笑みを浮かべ、彼は的確な指示を下す。
「ユリアン、解毒剤!シア、おびき寄せて射れ!」
しかし、バットに深々と矢が突き刺さったのを最後に、リトの意識は暗闇の中に途切れた。
――――彼は、途方もない深淵の夢を見た。
……。
「おう、気が付いたか。」
リトが次に意識を取り戻した時、そこは王の墓所の入り口だった。
「――――!」
「ああ、ここはもう外だ。コウモリはいねえよ。それから、シアとユリアンは無事保護。と、俺は町に戻る気がないから、ゲートは使わなかった」
彼が淡々と状況を解説する中、驚いて跳ね起きれば、そこは街が向こうに見える、草原地帯。微風は相変わらず穏やかで、湿った洞窟の匂いは、微塵も感じられなかった。あるのはただ、優しい草の匂い。遠くには赤く染まり始めた空が在り、帰還の時を告げていた。
「……すいません」
徐々に意識が戻るにつれ、出来事が思い返される。あのまま、担がれて洞窟の外まで運ばれたのだ。リトは自分の情けなさと考えの甘さに俯き、謝罪の言葉を投げかけた。しかし、向こうの方はといえば、視線はあらぬ方、頭を掻いて、あまりその事に頓着はしていない様子だった。
「別に謝る事じゃないさ、シアもユリアンも危なかった。それ以上に冒険者歴の浅いお前が、五体満足、無傷で生還ってワケにはいかないだろ?」
予想以上にあっさりとした返事が返ってくる。これにはリトも少し意外そうな顔をしたが、その答えの次には、彼はリトに視線を合わせ、鋭い眼光で見据えた。熟達した冒険者、同時に魔物を殺す時の、身体に流れる全ての血が凍てつくような戦士の瞳で。
「だが……次に幸運はないぜ、新米。ここにいる冒険者ってのは、俺を含め誰もが命懸けで真実を探しているんだからな」
まるで、首筋に冷たい刃を当てられているような感覚が襲う。彼の目には、決して反論を許さないという意思が込められていて、リトは一言も喋る事が出来なかった。彼の厳しい表情は変わらない。釘を刺すように、しっかりと、ここに来たばかりの新人に伝えるべき事を伝えるまで。リトも、その言葉を刻み込もうと彼を見上げる。その目に明確な覚悟を示して。
「甘さを捨てきれないまま、死んじまった冒険者なんて星の数だ。お前も真実を求めるのなら、ここで一回死んだと思って……強くなりな」
その言葉に、軽く「以上、後輩に対する先輩の助言」とだけ付け加え、彼はそれっきり厳しい表情から一転、普段の表情に戻って空を見上げた。視線の先では、ぽっかりとはぐれ雲が浮いていて、深い宵闇の方へと向かっていく最中だった。まるで吸い込まれるかのように、追い風に急かされた急ぎ足で。
「あー、そういや、お前の名前聞いてなかったな」
しばらく黙っていた彼だったが、やがて座ったままのリトに手を貸しつつそう訊ねた。いきなりの質問に少々驚いたリトに、彼はにっと笑ってみせる。
「俺は、冒険者としての覚悟が出来ている奴を新米とは呼ばない。で、ダチとして付き合う事にしてるんだよ。だから、敬語も禁止だ」
その手を取って、座ったままだったリトも立ち上がる。その質問に答えながら。
「リト。そう名乗ってる」
その手をそのまま握手に変えて、彼は笑顔で返す。
「……リトか、いい名前だな」
そうして、彼はリトに背を向け、歩き出した。最後に、その名を名乗って。
「俺の名はイアソン。また近いうちに会おうぜ。グッドラック、リト!」
後は振り向く事無く、ひらひらと手を振って、彼は歩き出す。街への帰路ではなく、どこか次の道へと。決して焦る事ない、悠然とした歩調で。
そののんびりとした後姿をしばし見送った後、リトも帰途へと着いた。
Last Update:
2005-06-30
Written by 皆川 新茶
Edited by ダイス
Powered by PHP
Powered by Lolipop