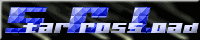「リト、ハティ、がんばるの〜!」
壺の中で休んで元気になったファルも再度交え、三人の探索が始まった。彼女はもちろん魔神ならではの力で応戦してリトを驚かせているが、今のリトにとっては、現在の道連れであるハティの存在もまた、圧巻だった。女性とは思えない、戦槌を豪快に振り回し、それでは対処出来ない至近距離の相手は拳で叩き潰す戦い振り。その様子に、ますます自分が頼りないと思う反面、彼は彼女に純粋な感服の気持ちを抱いていた。彼女くらい強くなれたらと、そこはかとなく憧れながら、道中で一度リトは「どうしてそこまで強くなれたのか」と、訊ねてみた事があった。すると、彼女は意外な事をリトに教えてくれたのだ。
「当たり前じゃない。あたしとビンセントは、いー兄さんと同期なんだから。一応、最古参の部類に入るのよ。……冒険者やってる時間の違い」
そうなのか、と言いながら、リトも納得する。なるほど、言われてみれば、彼女ならイアソンとでも互角に渡り合える気がする。と、考えながら。
「……それにしても、ファル。あたしも、あんたがここまで凄いとは思ってなかったわ」
そんな彼女も、ファルの力には驚いているようで、戦槌の返り血を払いながら、そうファルに呼びかけたのをリトは聞いた。ファルはリトの方からくるりと振り返り、彼女の方へと向き直る。
「ハティの方が、もっともっとすごいの!」
照れ臭そう、というか何というか。相変わらずの声を上げながら、彼女はハティに抱きついた。だっこぎゅ〜、と言いながら抱きつく彼女に、ハティは意外と優しく接している。だからこそ、ファルも懐いているのだが。
「……懐かしい」
「え?」
そんな中で、ただ一つ。リトが彼女について疑問を持った事といえば。
「な、何でもないわよ!」
ファルを抱きしめた時に、彼女がぽつり呟いた、寂しげな独り言だった。
さて、神殿の空気は今まで以上に古臭く、重たいものへと変貌してきている。リトは、ちらを壁を見た。ここで、一体何人の冒険者が屠られてきたのだろうか。壁のあちこちに、血の跡がこびり付いている様は、見ていて胸が悪くなるほどだ。これらの元凶は、獰猛なグリフォンか、規則正しく動く悪意の罠か…それとも。
『神殿内の石像には気をつけろ』
ふと、出かける前の警句が脳裏によぎる。そう、まだ遭遇はしていないが、もう一つ警戒しなければならないものがここにはいるのだ。
殺意を炯々とした目に秘めて、待ち続ける魔女達。リトは、まだここにいる事がはっきりしているのに見つかっていない冒険者、ユリアンの安否を気遣いながら、彼女達とさらなる深みへと進んでいった。
――――。
それから、ほんの数分後。その不安は、あまりにむごたらしい現実となって、目の前に突きつけられたのだった。ファルが怯えたようにリトの服の裾を掴み、リトもこの惨状には口を覆い、ハティですら、その場に跪いて長い間絶句するほどに。
「いー兄さんに、何て言えばいいのよ……まさか、二人ともだなんて」
見慣れた青い聖衣は、無惨にも紅と入り混じった紫と化して、妙に焦げ臭い。もはや語ることのなくなった友人は、誰かと再会する事もなく、ここで彼岸の園へと旅立っていたのだった。こうして、リトに近しい新たな冒険者二人ともが、ここに散った事を彼は知った。
「リト、とても悲しそうなの。ファルも、とっても悲しいの……」
悲しげなファルの頭を一度だけ撫でて、リトはユリアンの骸へと歩み寄った。彼は無言でハティの隣に腰をおろし、血のついたユリアンのメイスを取り上げて、綺麗に拭いてから、壊れたシアの弓と同じ道具袋に、そっと入れる。と、同時に、俯いたハティから、リトはこんな言葉を聞いたのだ。
「みんなが漆黒の迷宮の最下層を目指しているわ。そして、冒険者はそこに辿り着けないまま、こうして一生を終える。自分が目指していたものが何だったのかすら、知らないまま死んでいくのよ……」
熟達した冒険者である彼女が吐露した言葉は、冷たくて、重たかった。一日で二人の友人の死を見たリトは、その言葉を胸にしっかりと刻みつける。いつか、自分が真実にたどり着いた時に、得体の知れない禍々しい者の手によって、遠い世界にさらわれた友人の事を思い出せるように。
「……」
リトは目を閉じた。もう、彼は非現実の虚には引き込まれない。祈るように目を閉じて、この冒険者が自分の知らない遠い世界で恋人に出会える事を静かに祈る。その隣で、感心したようにハティが目を細めた事にも気付かないほど、ひた向きに。
「……急ごう。魔女が来る」
祈り終えた後のリトの行動は、驚くほどに冷静で迅速だった。突如現れ、飛来する魔女達に対して、それは十分すぎるほどに。彼女達の嘲笑が聞こえると、すぐにリトはその方向を見出して、ファルに指示を出す。
「ファル、効かなくてもいい、足止めにバマーを!!」
「了解なのっ!」
ファルも、リトの指示にはしっかりと動く。万が一、彼らの間をすり抜ける魔女がいたとしても、それは強靭なハティの槌の一撃で吹き飛ばされ、一瞬にして露と消えた。
そうして、三人は魔女の巣窟を走り抜け始めた。彼女達の哄笑が、はるか向こうに遠のくまで。走る、走る。邪悪な微笑みが消えうせるまで。駆ける、駆ける。遠方の地にありながら、もっとも町に近いあの場所まで。絶対に立ち止まらずに。立ちふさがる者に、水の壁と槌の一振りという死を。追随する者に、鋭い剣の一閃を与えながら。
「ゲートなのっ!リト、ハティ、急ぐのーっ!」
ファルが真っ先にゲートの部屋へと飛び込む。それに、後続のハティとリトが続く。
魔女の手は、もう届かなかった。
「……ふう」
ゲートの近くに、不思議と魔物は訪れない。遠巻きに眺めていた魔女の不気味な視線が、徐々に減っていく。笑い声も、もはや聞こえなくなっていた。そこには、誰かがいるというあの安堵感と、相変わらず四方を囲む、精巧で荘厳な石の檻。焦げ跡一つない、暗き万色のコントラスト。
「リト。一つ、聞いてもいい?」
その中で、最初にこの沈黙を破ったのは、無愛想なままのハティだった。リトとファルが、同じような仕草で首だけそちらへと動かした。
「俺に答えられる事?」
「か、どうかはあんたの気持ち次第よ」
妙に重たく感じた、この頼りがいのある女性の言葉に、リトは少し緊張して身体ごと向き直る。ファルも、リトの仕草を真似て、向き直る。二人が向き直ってから、ハティは一度自分の心を落ち着かせるかのように息をつき、リトを見た。
「リト、あんたにとって……ファルって、何?」
この質問に、リトもファルも目を見開いた。あまりに単純で、けれどあまりに難しい、この問いかけに。
「な、何を藪から棒に……?」
リトが、かろうじて反論する。しかし、ハティは落ち着きの中にも常日頃の炎のような激情を宿した目で、リトを見つめ返した。
「魔神を使役する人が、どんな気持ちで魔神と関わっているのか。それは、あんたにも重要な事のはずよ」
「それは……」
考えた事も無かった。そんな目をしながらも、リトはしばし現実を遮断して考えた。横で、ファルがじっと見つめていた事も全く気付かず。
ファルは、自分にとって一体何なのか。信頼すべき相棒? 使役するだけの存在? それとも、それ以外の何か? 頭の中で問いはくるくるとまわりながら、じっとりと浸透していく。
「それは……」
彼女の問いが、リトを俯かせる。しかし、ハティは別段リトの態度に失望の色など浮かべはしなかった。だが、静かに、訊ねた。
「彼女は、使役する奴隷?」
「それは違う」
ファルが見守る中、問答は続く。
「自分の心を安らがせるための、愛玩物?」
「それも違う。でも」
リトは、ここで一呼吸置いた。自分の言い放つ一言によっては、何かが酷く変わってしまうのではないかと、不安に駆られて。何よりも彼は、この告白が厳粛な誓いの儀式のようなものになってしまう気がしていた。自分が後悔しないような答えを、必死に模索しながら、ぽつりぽつりと語り出す。
「ファルがいる事で、安心する事は本当だ」
ファルが、じっとリトを見つめ続けている。ハティは、敢えて目を閉じて、耳を傾け続けている。
「町にいる時と、同じ。一人じゃないって思えると、とても安心するんだ」
「リト……」
ファルの消え入りそうな呼びかけに答える事無く、リトはハティをしっかりと見据えて、続けた。
「俺は、ファルの力も求めている。それも、本当だ」
ハティは、まだ動かない。リトの言葉も、まだ止まらない。
「けれど俺は、ファルを奴隷だとか、道具だとか思った事は一度も無い」
徐々に心の中で穏やかに広がっていく、温かな感情。その心のままに、リトはありありと町のぬくもりの中を思い返す。
「でも、俺はそれとは別に、こう思う事はある」
町で、家で、酒場での、彼女の明るい笑顔。いつも不甲斐ない自分の背中から、文句も言わずに付いて来てくれる、この一人の少女は、自分にとって何なのか。
「ファルは」
深呼吸をする。結論を、見出して。真っ直ぐと見る。今割り出せる精一杯の答えを、目の前の人に告げるために。
「ファルは……俺の家族だ、って」
自然と照れ臭そうな微笑みが頬に刻まれる。そんなリトの腕を、ファルは何も言わずに強く抱き締めていた。彼は視線を落として、ファルの頭をそっと撫でる。彼女がそうしていた、本当の意味に気付く事は、なかったけれども。
「なるほどね。だから、か」
「へ?」
その声に顔を上げれば、ハティが納得したように頷いていた。一体何事だろうと、リトがきょとんとした顔をしたが、その答えは彼にも案外早く与えられた。
「別に深い意味はないわ。ただ、あんたといると安心するってグレ坊が言っていたのを、少し思い出しただけよ」
リトとファルは、確かに見た。普段、無愛想で怖い印象を与える彼女が見せた、微笑を。
「人を惹き付ける、人に話を打ち明けさせる、何かがあるのかしらね。思えばあたしも、ビンセントの事を喋ってしまったし」
目を閉じて、彼女は小さく笑った。その笑みは、間違いなく。イアソンと同等の力を持つ、大きな先輩冒険者としての、誇り高い微笑みだった。ファルが、とことことハティの側へと寄って、嬉しそうにぎゅっと抱き締める。リトもそれを見て、自然に笑った。
「……そうね。難しい答えを言ってくれたのだから、一つ、あたしからも特別な話をしてあげるわ。これを知っているのは、いー兄さんとビンセントだけよ」
そうして打ち解けて、すぐ。ハティがこう言ったのを聞いて、不思議そうな顔をしながら、リトが壁にもたれた。しかし、その瞳には言い知れぬ興味が煌いている。ファルも、話の催促と言わんばかりに小首を傾げている。一体、どんな話なのだろうかと、リトも心をどきどきさせていた。
彼女は、語りだした。
「あたしも、かつては魔神のマスターだったのよ。十年くらい昔になるけれど」
リトは弾かれたように彼女を見た。容姿から見ても、彼女はまだ――年齢という概念があるかは解らないが――二十代前半程度だ。となれば、それは彼女がまだ子どもだった頃という事になる。リトは、幾度となく驚いた時にした仕草を、今回もした。
「主人だなんて感情、一度も持った事はなかったけれどね。むしろ小さい頃のあたしは、彼に一生付いていこうと思っていたのだから」
「どういう、事なんだ?」
リトがすかさず、真意を訊ねた。あれこれ下手な想像をする前に、真実であろう事を語るこの女性に。彼女はファルとリトを順繰りに見ながら、答えた。
「私の願いを糧にして彼は生き、彼の優しさで私は生きた」
そして、その目がファルに止まった。この言葉の意味するところをファルは悟ったのだろう、目をぱちくりと瞬かせていた。リトも、それに気付き始めたのか、信じられないという顔をしていたが、それは、本当だった。
「私は幼少の頃、魔神に育てられていたの」
リトは一瞬、このたくましい女性の顔が、懐かしい思いを抱く少女の面影と重なったような錯覚を見た。彼女は、リトの顔をちらとだけ見て、神殿の天井を仰ぐ。
「だから魔神を見ると、思い出してしまうのよ。魔神は誰もが、あの魔神(ひと)と同じ気配を持っているから」
溜息を付いて、天井を見上げたまま、ハティは続けた。
「彼は私の心の中で、いつまでも偉大な父親のまま」
「……もう、いないのか?」
「ええ」
彼女らしいといえば彼女らしいが、あまりにあっさりとした返答に、リトがかすかな反感を持って言葉を返した。
「魔神はずっと死なないって聞いた。だから、探せばこの島のどこかには……――」
けれども。
「残念だけど、もう彼は理由あって魔神ではないし、だからこそ生きた世界にもいない。逢いにはいけないわ」
リトの反論は、実に現実的な言葉で打ち消された。それでも釈然としないリトと、割り切ってしまっているハティを、ファルが見つめる。やがて、そのうち。ハティが先に、リトへと再び問いかけた。
「でも。もしもあんたが彼と出会えたら、そしてその時、あたしが生きていたら。彼はまだいると教えてくれる?」
「……」
目を開けて、彼の答えを見て。彼女はその名をリトへと告げた。父と慕った、魔神の名前を。
「彼の名はグレンデル。冥界の門に待つ『強きもの』に名を連ねる力の金剛鬼、グレンデルよ」
――――。
「やっぱり、シアとユリアンを送るのか?」
ゲートクリスタルをゲートに押し込んだハティに、リトはそう訊ねた。彼女は頷きながら、声としても返事を返す。
「いー兄さん達に、伝えに行かなくてはならないから。それに、ここから先に危険も、薬のある可能性もないもの。あたしが付いていく理由はないわ」
でも、と彼女はリトの言葉を遮って、続けた。
「ただ、リト。この先に、あんたの求めているものが必ずあるわ。それをあんたがどうするかは、自由だけれどね」
ハティが、ファルへと視線を落とし、リトへと戻す。その目は優しい光も湛えていたが、それ以上に、リトに対する厳しい色が伺える。リトは、視線に応えるべく、言葉を止めて彼女を見つめた。『求めているもの』が何であるか、おおよそ見当が付いていたから。
「その子を今後も大事にしてあげる自信があるなら、手に入れるのもいいと思う。でもね、自信がないなら止めておいた方が、あんたのためにもなるって事は確かよ」
リトは、頷いた。ファルの手を、ちゃんと繋いで。その姿に安心したのか、ハティは一度だけ息を付いて、リトの肩を一度だけ強く叩いた。
「あんたは……無事に帰ってきなさい」
だが、痛がるリトが涙目で見上げると、途端に彼女は顔を赤くして言葉をやたらに繋げ始めたのだった。何か、本心を隠すような印象を受ける慌て方で。
「か、勘違いしないでよ。あまり関わりの無いあんたが死んでもね、あたしの家の同居人がすごく悲しむの。だから、あんたを心配したわけじゃないのよ!」
「あ、あの、ハティさん」
小さなリトの呼びかけにも応じず、彼女はまだ慌てている。頬から耳まで、どんどん赤くなって、いつの間にか彼女は俯いていた。
「だからってね、あんたじゃないからって言って、あいつを心配してるわけでもないのよ! あいつがそれでまた身体を悪くしたら、あたしも迷惑だしっ、だから…――」
「ハティさん!」
今度は少し大きめの声で。ようやく止まった彼女を見て、リトは一言だけ伝えた。今出来る、精一杯の笑顔で。
「ありがとう」
「―― ふん……。あんたが神殿から凱旋してくる時を、楽しみにしているわ。がっかりさせないでよね」
まるで捨て台詞のような言葉を残して。嵐のように現れた女性は振り向く事もなく、また嵐のように、まばゆいゲートの世界へと旅立っていった。
彼女が、そうして振り向く事がなくても、リトは厳かに手を挙げて、彼女の帰還を見送った。
願わくば、あの意地っ張りながらも繊細な女性の願いが叶うよう。
リトは、確かにそう願いながら。
Last Update:
2005-06-30
Written by 皆川 新茶
Edited by ダイス
Powered by PHP
Powered by Lolipop