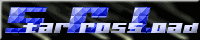帰還から、はや数日。リトは今、新たな友人と共に町を見て回っていた。
ディーヴァと名乗ったこの少女は無口で、表情を滅多に表に出す事はしなかったが、リトの熱心な説明に耳を傾けては、ぽつりぽつりと言葉を返していた。どうやら嫌ではないと知ったリトも、出来る限り上手に話そうと、あれこれ逡巡しては彼女を連れ回すのだった。
何となく、イアソンやハティがするような引っ張り方で。
「で、ここが酒場だ」
もちろん最後にたどり着いたのは、馴染みの酒場。
神殿を踏破してから、前よりほんの少し強くなったリトは、前よりほんの少し強くなった足取りで酒場へと入った。ディーヴァも、無言で続いて入った。
「ああっ、リト君発見!」
いつも通りの酒場で、まず出迎えてくれるのは、グレイス。ミルコも小さく手を挙げて出迎えてくれるが、リトは彼の腕に真新しい包帯が巻かれている事に気付いた。
「リト君、おかえりー」
テーブルの向こう側から、ぱたぱたとレジーナが手を振る。彼女の真横には、女流剣士であるナインが物静かな、それでいて元冒険者の威厳を漂わせながら、穏やかな時間を過ごしていた。
「リトにーちゃん、いらっしゃーい!」
レジーナに負けず劣らず、グレッグが声を張り上げて、満面の笑みで小さい腕をぶんぶんと振った。どうも先ほどまで、彼はタルバインの膝の上で、テーブルに置いてある地図を見ていたようだった。タルバインは集中していたせいか、このリトの来訪にグレッグが暴れるまで気付かなかったようで、顔を上げ、暴れるグレッグを片腕でがっしと掴んでおいてから、手を振った。もがもがと動くグレッグも、タルバインの腕には敵わない。そのうちに、大人しくなった。
その近くのテーブルに、ハティはいなかった。もちろん、彼女がいない以上は、緑髪の彼もいない。改めてお礼を言おうと思っていたリトにとっては、これは少し残念だった。
さらに言えば、別のテーブルに普段座っている二人組の少女―確か、カレンとマリエという二人組だった―もいなかった。他の冒険者と比べ、女性同士のペアという事もあって、面として話し難く面識も少ないリトだったが、いざいないとなると誰であれ、妙に寂しい気持ちになるのだった。
「おや、リト君。いらっしゃい」
ポロスもまた、カウンターからにこやかに声を掛けて応じて来た。相変わらず書物の読解にふけっているらしい。彼のかたわらには、まるで恋人のようにぴたりと本が寄り添っていた。
その横で酒をあおる、はちまきがよく似合う茶髪の男も、今は不在だった。
そして何よりも。向こうのテーブルに、自分と近しかったあの人達は、もういなかった。
リトはそう思った途端、たまらなく悲しい思いに陥りそうになった。決して深い親交があったわけではないけれど、彼らがいなくなった事で、ぽっかりと胸に穴が開いたような気持ちになるのも、神殿からの事だった。
紅玉の瞳をかすかに光らせて、ディーヴァはすぐさまリトの心の奥を読んだようであったが、何も言いはしなかった。それは生来、彼女が無口だったからかもしれないし、ただ単に何も言うべき事が無かったからかもしれない。もしかしたら言いたい事があるのかもしれないが、それを胸の中に仕舞っているだけなのかもしれない。少なくとも、今のところ彼女の意思を推し量れる者は誰一人としていなかった。
「俺の指定席はこっちなんだ」
ディーヴァを連れて、カウンターへと向かい、席に座る。開きっぱなしのカウンター席―否、普段はイアソンの恋人(槍)が使っている―に、ディーヴァも座った。
「二人目の魔神ですか。順調なようですね」
カウンターに座った以上は、この知識欲旺盛な男から逃れられはしない。リトは半ばそれを確信しつつ、まずは互いを紹介しなければと思い、動いた。
「ああ、紹介するよ。彼女はディーヴァ、で」
「ポロスと申します。専業という訳ではなく、むしろ学者が本業の冒険者です。どうぞよろしく」
リトの視線に合わせて、ポロスもディーヴァへと自己紹介を手短に済ませた。すでにその目に探究心が輝いている事もあり、彼を止められはしないと、リトは少し苦笑いをした。
(さて、これからどうしよう)
隣の男からの質問攻めに襲われる前にと、リトはあれこれ思索したが、いい案が出てこない。研究好きの隣人の事、ディーヴァを一目で魔神と見破っている事は明らかだった。だとすれば、しないはずがないのだ。隣の青年が「あれ」をしないはずが、ないのだ。
「彼女は何処で出会ったのですか?」
ほら、来た、始まった。と緋色の髪の青年は思った。
いやはや、まったく。このポロスという若者は決して悪い人ではないのだけれど、と思いつつも、彼の知識欲を満たすのは至難の技。手馴れの冒険者であるイアソンも彼の質問攻撃には手を焼いている事を、リトは嫌というほど知っていた。
「神殿で」
やはり端的にでも、その気持ちが言葉に現れる。手短に、やや乱雑に、リトはポロス目掛けて言葉を投げて寄越した。
「となると、あの溝の向こうの壺の主ですか」
「そうなるかな」
リトの言葉の端々に回避したいと言う意見を見たか、ポロスはリトが思っている以上に問い詰めたりはせず、自分の目でリトの隣の彼女を見た。
「ふむ、属性としては闇のようですね。ふむ、ふむふむ、ふむ」
さすがのディーヴァも、この学者肌の冒険者の飽くなき好奇心と探究心に、かすかに動いた。怒りというよりも、面食らったような表情で。
確かに、初対面でいきなり研究対象にされたのではたまったものではない。リトはディーヴァに、どうしようもなく申し訳ない気持ちを抱いた。
「興味深い」
さて、ようやくお決まりの文句を言ったところで、ポロスは目から好奇心を追い払い、魔神の主にずずいと急接近した。驚いて悲鳴を上げそうになったリトだが、何とか踏み止まって彼の真剣な緑色の瞳を見返した。
その途端に、ポロスは晴れやかに笑いながら、恐ろしく鋭い一言を言い放ったのだった。
「魔神を扱う際の覚悟を怠ってはなりませんよ。彼女にしても、ファル少女にしてもね」
ぽそりと呟かれた言葉に、リトは氷のように固まった。
「ああ、それでは私はこの辺りで。今日の成果を記録せねば」
言葉は急がせながらも、ポロスは彼らしく、やおら席を立って二人に会釈した。
「それではお二方、お先に失礼しますよ」
ディーヴァは動かず、リトはこの対応の変化に付いていけずに、ぽかんとして、本を抱えて颯爽と去っていく学者を見送った。
ただ、彼に対して言えた言葉と言えば。
「嵐のような男だ」
「ああなった彼の周りは、いつも大荒れだ」
二人とも、一言ずつだけだった。
時計の音と、他の人々の喧騒がしばし支配する。
リト達の間には、嵐の前ならぬ後の静けさというか、しばらく微妙な静寂が広がっていたのだが、ディーヴァが問い掛けた事で、それはあっさりと破られた。
「いつもここに来るのか」
「ああ。疲れた時、悩んだ時、辛い事があった時とか、いろいろ」
ごく自然に来るんだ、とリトは付け足しながら、ドアからディーヴァへと視線を移動させた。彼女は相変わらず表情に乏しくて、いつも淡々とした語り口で、なかなか心の奥底を知る事は出来なかったけれども。
「そうか。まあ、たまにはこういうのも悪くはない」
鋭い剣のような彼女からふと見えた微笑みに、リトはただ温かな気持ちになって、微笑んだ。
丁度そんな時に、酒場のドアが開いたのだった。
「みんな、久しぶり。差し入れを持ってきたよ」
久々に聞く穏健なテノールに、冒険者達は揃いに揃って、物凄い勢いでドアへと振り返った。
それからは、ほとんど酒場の面々は一斉に動き始めていた。真っ先にタルバインからするりと抜けたグレッグが、久方ぶりに酒場に訪れた客人が驚く事も気にせず、いきなり体当たりをした事を、はじまりとして。
裾がぼろぼろになった緑のロングコートに顔をうずめて、突如グレッグが確かめるように鼻を動かす。
「ふんふん。うん、ハーブのいい匂い」
鼻を動かすのを止めて、小柄なグレッグが自分よりもずっと背の高い青年を見上げて、にんまりと破顔した。
「間違いない、ビンセントにーちゃんだ!」
「た、頼むから動物まがいの事をしてくれるな、グレッグ」
タルバインは頭を抱えつつ、べりべりと音を立てんばかりにグレッグを困り顔の来訪者―ビンセントから引き剥がした。
「すまないねえ、ビンセント君。うちのグレッグが随分と世話をかけて」
「いえいえ。グレッグ君も元気そうで良かった。確か君は野苺の焼き菓子が好きだったよね、はい」
タルバインと、まるで井戸端に集う親の会話のような言葉を交わし合ってから、唇を尖らせている青髪の少年へとビンセントは手作りの菓子を手渡した。
一時はタルバインに対する不満に無くなっていた笑顔が、またもグレッグの顔一杯に溢れた。
「ビンちゃん、おかえりっ!」
続いて飛び出したのはグレイスと、彼女に引きずられるような形でドア前にやって来たミルコ。ドア前はたちまち、ちょっとした人だかり。
それだけ彼がこの酒場において無くてはならない存在なのだと言う事は、この場にいる誰もがすぐに理解出来た。
「すまねえな、こいつ相変わらずでよ」
「む、相変わらずってどういう事、ミルコ!」
さばさばとした言動のミルコの相変わらずという言葉に、むっとしてグレイスが食って掛かる。
「ふんだ、『こーじんぶつ』じゃないミルコには、あたしの気持ちなんか解らないもん!」
「お前、好人物の意味、解って使っていないだろ?」
ミルコの反論もむなしく、グレイスはいじけるばかり。そんなグレイスにも、包帯の無い方の手で頭をばりばりと掻きむしって、どうしてくれようかと思案するミルコにも、ビンセントはまず差し入れを渡し、すぐに仲裁に入った。
「まあまあ、グレイス。落ち着いて」
ぐすぐすと手で目を覆っていたグレイスは、それであっさり機嫌を直したらしく、ぱっと顔を上げて笑った。
「うん、落ち着く!」
「俺、もうやだ。疲れた」
どっと疲れ果てて、がっくりとうなだれるミルコの肩に、無言で深くうなずきながらタルバインが手を置いた。
「はあ」
同病相憐れむ。そういった雰囲気で、保護者二人は一緒になって、こんな深い深い溜息と共に、肩を落とした。
(やっぱり、ハティさんを抑えるだけの事はあるよな。彼はいつも調停役だ)
彼らのやり取りなどとは、まったく無縁な遠巻きから見ていたリトはそのように思いながら、今回ばかりはと一歩身を引いて傍観者状態。に、するはずだったのだが。リトの一歩身を引くという考えは、いつも何かにつけて否定されてしまうもの。今回もやはり、そうだった。
突如、リトの隣で立ち上がる少女の姿をした魔神が、一人。何事かと思い、リトも驚きながらつられたように立ち上がる。
かすかな疑問を抱いた瞳で、彼女はつかつかと歩み寄って、人だかりの前へと抜け出し、少し背の高い華奢な青年を見上げた。
「お前、もしや……」
ディーヴァの見上げながらの呟きは、人だかりにいた誰もが聞いた。リトもまた、そうだった。
そうしてリトはこの呟きの意味を考え、ある事に思い至った。緋色の髪の青年が立てた仮定は、すぐに目を丸くしたビンセントが確信へと変えたのだった。
「え、あの、もしかしてディーヴァ、さん?」
何故かビンセントは、ディーヴァの事を知っていたのである。一体何故。リトがディーヴァに訊ねようとするよりも早く。
「リト、席を外してくれ」
ディーヴァは、リトに話の場を欲した。
町の郊外は、潮風をわずかに含むそよ風が吹いていた。この町のもっと向こう側では、この風を一身に受けて緑の絨毯がそよいでいるのだろう。反対側の海辺では、海から生まれた白い鳥達が肩を並べて、揺れる青を駆け抜けているのだろう。
争乱を呼ぶ風。運命を運ぶ風。時として背を押し、時として真っ向から吹き付ける、けれども不変の、風。
「かれこれ、十年ぶりですね」
とても昔の事を懐かしむように、草原と同じ色の髪をこの風にたなびかせながら、先に切り出したのは、ビンセントだった。が、先に質問をしたのはディーヴァだった。彼女の問いは手短なものだったが、それだけで充分な問いだった。
「お前の兄は健在か?」
「イアソンは息災です。彼は十年前よりも、ずっと背も高くなって、それと一緒に人柄も大きくなって、随分遠い人になってしまった気がします」
ほんの少し寂しげな印象を与える微笑みを頬に刻み、語る青年の言葉をディーヴァは目を閉じて聞いていた。
「僕も好きな人が出来たり、身体が弱くなったりと、いろいろありました」
彼の羽飾りが、そよ風にさえ頼りなく怯えて、赤色のバンダナにひしとしがみついている。
「本当に、十年間は短かった」
穏やかな、けれど少し悲しげな声が、静寂の中を思うより深く切り裂いて、風にまぎれていった。静寂を好むディーヴァにとって、水面に波紋が浮かぶ事はあまり好きではなかったけれど、今はさして嫌悪を示しはしなかった。
「私にとっての十年間は、お前達の来訪以外は不変だった」
しみじみと、ディーヴァが囁くように言った。
「だが、お前達にとっての十年間という時は、私達と違って流動するもの」
囁きが、風に消されるか否かの境界線を漂いながら、何とかビンセントの耳に運ばれた。
「お前は、随分と変わったな」
「変わって、しまいましたね」
強くも優しい紅玉の瞳と、儚げな光を帯びた緑の瞳が視線を交錯させる。
それが丁度真っ向からぶつかりあった瞬間に、ゆるゆると首を横に振りながら、ビンセントがまず言った。
「僕は答えを知っているのに、身体は遠くへ行く事を許してくれない。なかなかに、これは辛い事です」
「そう、だろうな」
静寂の中、二人は語らう。直立のまま、風に髪と服とを揺らしながら。
「お前はどれほど知っている?」
「おそらくは、今生きる冒険者の中の誰よりも」
傲慢でもなく、過剰な自信でもない、ありのままの真実をビンセントは歌うように言った。
「お前は、真実が何処にあるか、真実に座する者が何を求めているか、知っているのか?」
「知っています。けれども、いいえ、だからこそ、それは誰にも言ってはいけない事だとも」
この答えにディーヴァが、小さな溜息を付いて言い放つ。
「一人で抱えられる程、真実は小さなものではないぞ」
解っています。その一言は、真摯な眼差しからも見て取れた。
それでも、抱える気なのか。確信しながら、ディーヴァは燃えるような紅玉の瞳で氷のように冷徹に見据えた。出来得るなら、否定をしろと心の中で言いながら。
しかし、答えは闘神の予想通りであり、結果として彼女の思いを裏切るものだった。
「お前は優しすぎると人から言われた事はないか」
それがまた、彼女にぎこちないながらも苦笑いといった表情を浮かべさせた原因でもあった。ビンセントにもその苦笑いは伝染して、彼もまた、そのような表情を浮かべた。この苦笑こそが、何よりの肯定の返事だった。
「結果として、お前は完全ではないにしろ、我々に近しい者になってしまったではないか」
「貴女は知っていたのでしたね。僕が取り返しのつかない逸脱を受けてしまった事を」
ビンセントの投げかけた問いに、ディーヴァは神妙に頷いてみせた。
「お前からは、相変わらず月の残り香がする」
「それでも今はもう呼ばれない昔の呼び名を懐かしく感じてしまうのは、きっとまだ僕が人間である証拠なのでしょうね」
もう戻れない事を知っている笑みを見せて、けれども決してディーヴァから視線を逸らす事をせず、彼は真っ直ぐに立ち向かった。
「ディーヴァさん。人は確かに、たった十年で変わってしまいます」
流れるように、彼は優しく風に囁く。
「けれども、その本質は決して変わらないものですよ」
しかしながらその声は、はっきりとディーヴァの耳に届いたのだった。
それから長らく時を経て、ようやく話を終えたディーヴァは、酒場へと舞い戻った。
この頃にはすっかり人気がなくなって、酒場の中はまったくのがらんどうと化していた。外では夕日がきらめいて、各自帰還の時を告げていた。
「あれ、ビンセントは?」
「花を手向けに行った。誰かは知らないが」
ディーヴァは、一度勧められたカウンター席へと座って、じっと隣のリトの顔を見た。
リトの顔はディーヴァの言葉を聞いて、随分と沈んでいるようだったが、しばらくすれば何とか持ち直して普段の表情に戻った。そのまま、この青年はカウンターに向いて、静かに目を閉じた。
ディーヴァを気遣ってか、リトは何も聞かなかった。何も聞かず、また、彼女から話す事を待つ事もしなかった。
「さてと、そろそろイリスの所に帰ろう」
「リト」
そう言いながら立ち上がるリトを、不意にディーヴァが呼び止めた。リトは紅玉の瞳を見下ろしながら、どうかしたのと言いたげに小首を傾げた。
ディーヴァは、一瞬だけ紅玉の瞳を揺らしたが、すぐに彼に対し言うべき事を言った。
「今日は私が食事を作ろう」
彼女もまた立ち上がり、先導するリトの背中を追いかけた。リトの問いかけや言葉に、ぽつりぽつりと―前よりもほんの少し多く―応じながら。
ディーヴァは先の一瞬だけ、不覚にも彼の仕草に懐かしい友人の姿を重ねてしまっていたのだった。
もしかしたら、食事を作ると言い出したのは、懐かしくも新しいマスターにそれを悟られないための、不器用な優しさだったのかもしれない。
Last Update:
2005-06-30
Written by 皆川 新茶
Edited by ダイス
Powered by PHP
Powered by Lolipop