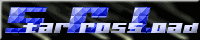あれから、しばらくの時が経過した。
冒険の日々の中、何度、この街の平穏な世界に救われただろうか。いつしか、酒場は旅で疲れた心を癒してくれるなじみの場所となり、冒険者達はかけがえのない友人となり、友人達は、自分がここにいるという何よりの証となっていった。それが何より大事な事だと思うという点では、リトも、彼の側にいるファルも、同じ事で。いつの間にか、そこはいつも必ず親しい友人達が迎えてくれる、温かな場所だと思い込んでいた。
しかし、冒険者のたった一つの命を狙うそれは、ずっと、彼らを狙い続けていたのだ。それを、リトはすっかり忘れていた。今日この日、初めて踏み入れた石造りの遺物で、その事を思い知らされるまでは。
――――。
「神殿、なあ。まあ、今のお前の実力なら、何とかなるだろ。ファルもいるんだし」
慣れたカウンターの席でリトが神殿について訊ねると、イアソンは酒を飲みながらそう答えた。
「ですね。しかし、用心に越した事はありませんよ、リト君」
ファルに採れたての果物ジュースをおごりながら、ポロスがそれに続く。本当にいいの、と訪ねるかのように小首を傾げるファルに、いいんですよと、彼女の頭をそっと撫でながら。それで安心したか、彼女はジュースに口をつける。笑顔のままのあたり、口に合うのだろう。
「うまいか?」
「みぃ!」
手短だが、イアソンに問い掛けられ、ファルは満面の笑みで見上げて返す。イアソンはその笑顔を、リトへも分ける。
「お前の相棒は、可愛いな」
「へへー、兄貴さんったら、ファルちゃんが趣味?」
彼の呟いた言葉は聞き逃さず。すかさずグレイスが悪戯に満ちた声を投げかける。
「あればあったで面白いだろうが、あいにく俺にそんな趣味はない」
グレイスのからかいを笑いながら一蹴し、イアソンは酒をちびちびと飲んでいる。いつもなら豪快に煽る彼にしては珍しいと、リトはしばし怪訝そうな顔を浮かべていたが、側にいたファルと、グレッグのやり取りを視界の横に捉え、そちらに視線を向けた。
「ね、ね!ファル!」
あくまでも見た目だけだが、ほぼ同年代であるファルとグレッグは、街で出会う度に一緒になって遊ぶ。ますます冒険者達の心を和ませるのだが、一方でグレッグの受ける鉄槌の数が増えた事も事実であり、その内頭が変形しないかと心配になっているリトだ。しかし、本人はどこ吹く風。悪戯を減らすどころか、ますます増やしているのが現状だ。しかも、それにはグレイスも混ざっている。魔神が怖いと言ったのは本当に彼女だったのか。今ではすっかり、ファルの姉のような雰囲気まで漂わせている。その理由は、ファルが人懐っこいからというのが大きな部分を占めているようだけれども。まあ、微笑ましい事には変わりないと、リトは見守るだけに留めていた。
「みぃ?」
ファルもそれに混ざって、周囲を和ませている。彼女はグレッグよりかは分別があるらしく、いつも鉄槌寸前の彼の抑止力にもなってくれている。だから、リトも安心して彼女を彼と一緒に遊ばせているわけだが。今日も真横でタルバインの目がぎらぎらと光っている。リトにとっては内心、ひやひやものである。
「今度は何して遊ぼっか。レジーナ姉んとこに行く? それとも、もう一度タルバインに鼻毛、あだっ!」
三度、鉄槌下る。タルバインの大きな拳の一撃を受け、グレッグは目から火花を出しながら撃沈した。今日一番の威力の一撃は、間違いなく彼を再起不能に――もっとも、それは今日一日だけの効力だが――追い込んだ。ちょっと不安げに、ファルも彼の服の裾を引っ張って、みぃみぃと声を掛けている。震える手をひらひらと動かし、グレッグは大丈夫だと伝えているようだが。目じりに涙が浮かんでいる。相当痛かったのだろう。悶絶して、それ以上何も言えはしなかった。
「ぐーちゃん……タルおじさんに向かって鼻毛はだめだよ、鼻毛は」
かつての光景を思い出したか、その横で肩を振るわせるグレイスに、少々むっとした顔でタルバインが睨みつけている。彼女にも鉄拳が降りなければいいが。そう思いながら、リトは視線を先の二人へと戻す。彼の視線が戻ってきてから、イアソンはもう一言二言忠告に足した。
「……神殿には、俺が知っている限り、シアとユリアンが行っているはずだ。ああ、二人でなくとも、誰かと出会ったら、一緒に行動するといい。その方が生存率はぐっと上がるからな」
「ああ、出会えたらそうさせてもらおうかな」
多少酒を飲み、リトはイアソンに向き直る。ようやく奢ってやれた、と嬉しそうなイアソンだったが、その言葉にしっかり頷いて、リトへの忠告を続ける。凍てつく戦士の目というよりも、酒場でいつも仲間を見守り、温かく諭す兄のような目で。
「いいか、あそこで前の時みたいな囮作戦は自殺行為だ。命あっての物種、まあ、冒険者って名乗るからには宝を狙うのもいいが……神殿内の石像には気をつけろ、リト」
「石像?」
首を傾げるリトに、今度はポロスが納得したように頷いて、苦笑いを浮かべた。
「ああ、あれですか……あれは驚きましたね」
「一体、石像が何か?」
さらに問い掛けるリトに、ポロスがイアソンに変わり、気をつける理由を述べた。
「……魔女、ですよ。彼女達は石像に化けて、餌食となる冒険者を待ち伏せしているのです。貴方もうかつに近づくと、一瞬でその命を失う事になりますよ」
一瞬で命を失う事になる。リトは、思わずその言葉に息を飲んだ。無意識のうちに、手に力を込めてしまう。
「あそこで殺された新米は、大勢いるんだ」
そう言って固まるリトの肩を叩きながらも、何処か疲れたような溜息をつき、イアソンは遠い目で呟いた。彼は見てきたのだ、その数々の死を。リトは、直感した。
「……じゃあ、俺はそろそろ」
「ああ、悪いな。ちと酒をまずくしちまうような話、しちまって」
詮索したい気持ちにも駆られたが、一瞬見たその表情の、あまりに憔悴した瞳に自分の言葉を押し込めて、リトは立ち上がった。ファルも、それに気付いてグレッグとグレイスから離れる。申し訳なさげに見上げるイアソンを、軽く手で制しながら。
「みぃ、ばいばいなの〜!」
ファルは小さな腕、振り振り。グレッグもまだ小さな腕、振り振り。グレイスは白く綺麗な手を小さく振って。
「頑張れ、ファルちゃん!お姉さん、応援しちゃうから!」
「ボクもだよ。だから、ファル!リトにーちゃんと、元気で帰って来てね!」
大声を上げたせいか、頭を抱えて再び撃沈するグレッグに向け、もう一度、みぃ!と声を上げて、ファルはリトへと駆けていく。
「じゃ、行こうか」
リトもファルに一言呼びかけ、そして一緒に酒場を出て、殺伐とした場所へと向かっていった……。
――――。しかし、今回の酒場の物語はリトが退場しても終わらない。
「やれやれ、貴方も意地っ張りですね。このまま、魔神を求めないのですか?」
……リトを見送った後、イアソンは自分とよく似た立場の青年に、問いかけついでに見つめられ、小さく肩を竦めて返した。
「ああ。それじゃ、あの人を超える事は出来ないからな」
酒を名残惜しそうに、相変わらず少しずつ飲み、彼はポロスを横目でちらと見た。穏やかながら、強かで、相手の心をすぐに読んでしまう友人に何か言われる前にと、彼はさらに付け足した。その行動に、何か言おうとして口を開きかけたポロスも、再び口を閉じてくれたようだった。
「今も俺は……あの人に心底惚れちまっている。だから、あの人の為しえなかった方法で、あの人を超えたいんだ」
子どものような目を垣間見せ、そう言いながら、最後の酒を煽って飲み終えた彼は、酒代の銀貨を置いて立ち上がった。唯一の相棒である白銀の得物を背負って。
「ああ、イアソン。それならば」
ふとポロスに呼び止められ、彼は足を止めた。くるりと振り返って、一言どうしたと問い掛ける。その瞳の異様な輝きに気付き、小さく溜息を付きながら。
「少し、その経験と記憶力を貸して頂けませんか。どうしても、照らし合わせたい文献があるんですよ」
その瞳の奥で探究心の劫火を燃やしながらも、あくまで理知的な微笑みを浮かべ、ポロスは一冊の本を取り出した。片眉を吊り上げ、しばしその意味を考えていたイアソンだったが、その意味に気付き、ますます苦笑いを大きくした。
「解ったから、その目は止めとけ。見ていて、怖いぞ」
酒場のマスターの口から、吹き出す音が聞こえた。
「天才学者には、いかな最強の冒険者も恐れをなすってか?」
「……うるせえよ、ロック」
頭を掻きながら、彼はマスターへと視線を返す。だが、その頬には困ったような、仕方ないかというような笑みが刻まれていて、横槍を投げて寄越した酒場の主人に、微塵も恐怖を感じさせる事は出来なかった。それを見て、誰かが笑い出す。それは波紋のように広がって、みんなの笑いに変わる。イアソンに、珍しく焦った恥かしそうな表情が浮かぶ。ぶんぶんと腕を振り回して周囲の人々を散らしながら。その耳は、真っ赤だ。
「おい、こら!笑うな、そ、そんな変な顔したか、俺は!!」
カウンターの周辺からの笑い声に、生きる術を教える女戦士は息を付き、優しい微笑を浮かべた……。
――――。
冒険者となって間もない者のほとんどが、その地に潜む獣の毒牙に掛けられて死に至るという。だが、その地から戻ってきた冒険者は、長らく生きて冒険者を続けられるというジンクスは、新米冒険者達を強く惹いてやまない。
ただあるのは冷たい石の感覚。未だ生きながらにして無の褥であり、魔女と魔獣の巣窟。
人はそこの名を知らないのか、ただ『神殿』と呼ぶ。
「速い!」
リトは少し毒づきながら、とっさに剣を振るうが、それよりも早く茶色の衣をまとった獣は彼に牙を剥いた。早急に来るであろう衝撃と激痛に身構え、リトが思わず目をつぶる。しかし、牙よりも速い言葉が、その獣を押し流した。
『おいで、優しい水色の子。貴女の怒りは全てを薙いで、息吹を刈り取る鎌になる――――』
樫の杖を振りかざし、果敢に彼女は力を呼ぶ。
「みぃぃ〜!雄風(シアル・サー)!」
突如吹き荒れる風に切り刻まれて、無言のまま、三体の狼は壁に横たわった。だが、次の追っ手はすぐ側まで迫っている。
「みぃ、みぃ、リト!」
「解ってる、急ごう、ファル!」
手を繋いで、二人は走る。獰猛な狼たちの影をすり抜けて、串刺しにしようと身構える多くの槍を飛び越えて。彼女が走る事に疲れてしまったら、力強く抱き締めて。
「みぎゃ〜、だっこぎゅ〜」
彼女の愛くるしい笑顔はこの殺伐とした場には似つかわしくないが、それはそれで安堵の気持ちで一杯になれる代物だった。仲間がいる。すぐ側に。それだけで、何と心が軽くなるのだろう。リトも感謝の意を込めて、彼女に優しい微笑みを見せた。
神殿の内部は巧妙な罠に溢れていた。壁際を歩けば、速やかに狼達が死を運ぶ。足場を踏み外せば、即座に串刺しになるであろう槍もまた、走る妨げとなってリト達にまとわりついた。しかし、歩みは止められない。止めれば、たちまち灰色や銀の毛皮を被った化け物に、二人共々、その手はおろか、その身体さえも引きちぎられてしまうから。
――――やっとの思いで一階を突破したのは、もはや、すっかりファルが疲れきってしまっていた頃。さすがに、外見からは想像できない予想以上の広さに、リトも肩で息をしながら、一時壁に寄りかかって息を整えようと深い呼吸を続ける。古ぼけた匂いは墓地に良く似ているが、押し寄せてくるような壁から受ける閉塞感は圧倒的だった。息を整えても、まだ息苦しく感じさせる。その理由は、まとわりつく湿気のせいか、それとも死んでいった冒険者達の無言の念か。どちらにしろ、疲れをより一層ひどくさせるものに、変わりはない。
「ファル、少し休んでいてくれ。もう少ししたら、呼ぶから」
リトは横で疲れ果てている彼女を少し休ませようと壺の中へと戻し、一人になった時点で溜息を付く。そして、ふと思う。魔神の力を借りるという時点で、もう覚悟はできていたはずなのだが。
「俺って、弱いな」
誰にも届きはしないのに、そんな言葉を呟いてしまう。人間と魔神の力の差は、あまりに大きい。それを、ファルと共に旅するようになって、ますます思い知る事となったのだ。守るどころか、守られてしまっている。解ってはいるが、自分の不甲斐なさに思わず嘲笑をこぼしてしまう。そして、そう思った次の瞬間。ひやりとした何かが、心の中に滑り込んできたのだった。悲鳴も上げられず、ただ目を見開いて、リトは響くその声を聞いてしまった。
――――では、私のところに来れば良い。お前は、私にまみえる権利を有しているのだから。
背筋に走る悪寒。呼び覚まされる耳鳴り。心の奥で、誰かが呼んでいる。息が、苦しい。リトは思わず、壁に背中を預けてずるりと座り込んだ。
「う……」
かろうじてうめいてみるが、やはりここは神殿。魔物ならば来てもおかしくないだろうが、人は誰も来るはずがない。ファルも、先ほど休ませるために壺へと送ってしまった。部屋が妙に暗く見え、一人置き去りにされた気分になってしまうのは気のせいか。そう、リトは、やや霞みかけた思考でぼんやりと考えた。
――――だが、あの女は私に会う権利は有していなかった。
その思考でも、はっきりと聞こえるその声に、リトはかすかに肩を振るわせた。
「……何、だって?」
思わず、問い掛ける。その声は、遠くからのような、近くからのような、不思議な位置から呼びかけてくる。リトはよろよろと立ち上がり、声のまま、そちらへと歩いていく。壁から何かクチバシを持った生き物がこちらの様子を窺っているが、彼らは様子を見ているだけで、襲い掛かってくる気配はない。しかし、今のリトにとって、それは些細な事だった。呼ばれるままに、歩く事にだけ、心を奪われていたから。
―――― そちらだ。哀れな『それ』は、お前とは違い、権利を有さなかった生き物だ。
身体が熱を帯び、がくがくと震える。止めたいのに、止められない。その先に、何があるか。心のどこかで知っている。しかし、歩みは止められない。乾いた足音だけが、耳へと響いては、霧散していく。まるで催眠術にでもかかったように、意識が遠のいていく。それは、一歩踏みしめる度に、なお強く心を縛る。
暗がりに人影が見えた。はっきりとは見えない。薄暗くて解らないけれど、リトはその鮮やかな長い金髪に、何処か見覚えがあった。近くに何かがいる。動けない彼女を千切れんばかりに引っ張って、深淵へと引きずり込もうとする、何かが。
いけない。彼女を連れて行ってはいけない。彼女は仲間だ。彼女は見知った友人なんだ。命を助けてもらった、恩人の一人なんだ。彼女を引きとめようと、リトの心が足掻く。心を縛る何かから、必死に逃れようと。そして、その時、糸が切れるかのように枷も外れた。
「う……うおおおおおおっ!」
奥底から響くような、咆哮を上げて。気が付いた時には、リトは剣を構えて、彼女を死へと引きずり込もうとしている影に飛び掛っていた。それは、翼を背負っていた。獅子と鷲、高潔な二匹の獣が入り混じった、雄々しくも恐ろしい姿をしたそれは、グリフォンと呼ばれる危険な猛獣だったのだ。リトは、初めて見るその正体を、知っていた。否、それはリトではなかったのかもしれない。あの声同様、近いようで、遠い存在だったのかもしれない。しかし、今のリトにとってはそれもまた、些細な事だった。ただ無我夢中で、半狂乱になって追い払おうとだけしていたから。
グリフォンが雄叫びを上げて、風を巻き起こす。だがリトは、まとわりつくつむじ風を強引に振り払い、喚声を上げながら、喉元目掛けて剣を突き上げた。しばらくグリフォンはその剣にもがいていたが……やがて、動かなくなった。
折角整えた呼吸が再び乱れ、リトは剣を杖代わりに、息を整えるために俯いた。
「……」
そして、あらかた呼吸も落ち着いて着たところで、リトは改めて横たわる女性を見下ろした。やはり、その金髪に見覚えがあったし、折れた弓にも見覚えがあった。ただ違うのは、当時生きていたか、現在死んでいるかの違い、だけ。彼が助けた時には、もはや手遅れだったのだ。
「……シア、さん…」
初めて、彼女の名前を口に出した。その言葉は、闇に飲まれ、やがて消えていく。霧散した言葉の後に、彼は跪いて友人の死顔を直視した。青い瞳は、もはや何も映さず虚空ばかりを見つめている。色を無くした肌は、酒場にいた頃とはまったく異質のもので、触れる事すら躊躇われた。裂けた服から、真紅がにじんでいる。傷口は、直視さえ出来なかった。
(これが、さっきまで生きていた人なのだろうか)
よく似た人形ではないのか。そう思ってしまうほどに、その死は衝撃的だった。だが、せめて目だけは閉ざしてやろうと、そっと顔に手を伸ばし、静かにまぶたを閉ざす。伝わってくるのは、まるで氷のような冷たさと無機質さだけで、もはやそこには何も無かった。
「……」
リトは、呆然としていた。あまりに鮮烈過ぎる光景に、対応しきれていなかった。目の前には二つの死体。一つは大きな獣の骸、一つは見慣れた友人の身体。頭の中でぐるぐる回って、非現実を照らし出す。そして、現実を覆い隠す。リトの背後に忍び寄る、羽の帳を背負った獣。それに、リトをまったく気付かせなかった。
「――――ちょっと、後ろッ!」
ふと、急に声がした。ぼんやりとしながらも、リトはそれに答えようと、未だ非現実の空間から逃れられていない瞳で立ち上がり、振り向く。鋭い爪とクチバシを振りかざしながら、こちらに向けて飛び落ちてくる影。しかし、それに応じきれない。避けきれるはずもなく、リトはただ、喪神したように立ち尽くしていた。
「動かないで!動いたら、命の保証は無いわよッ!!」
だが、その巨大な獣の身体は、横から突如襲い掛かった強烈な一撃によろけてリトを殺める事は出来なかった。慌てて体勢を整えようと、彼か彼女か、グリフォンは必死にその影を追う。しかし、それよりも早く、光のような鉄槌が下った。この無慈悲な審判に、グリフォンは抗議のうめきを上げるが、もはやそれまで。さらに下った一撃に、ぴくりとも動かなくなった。リトは先ほど以上の非現実にますます呆然としていたが、その声でかすかに現実へと戻ってきた。
「あんた……」
その人影は近づいて来る。リトも、そちらへと歩き出す。そして、リトが声を掛けるよりも前に。
「あんた、何ぼけっとしてんのよ!ここが何処か解ってんの!?」
リトに豪速の張り手が一発、寄贈された。戦い慣れた、タコだらけの掌から繰り出された一撃は、まるで噂話に聞いたオーガーの一撃。リトはたまらず先のグリフォンよろしく派手によろけ、尻餅をついて、きょとんとその姿を見上げた。改めてみれば、その姿、しかと見覚えあり。完全に現実に引き戻され、三度呆然としていた彼の胸倉を乱暴に掴み、耳元で盛大に怒鳴る女性は、かつて初めて酒場に訪れたリトに強烈な印象を与えた人だった。
「……ハティさん?」
酒場でも何度か見かけ、話した、その人の名前を呼ぶ。溜息を付きながら、リトの命の恩人にして声の主、金髪の女傑ハティはリトを睨みつけた。その手にはナックルをはめ、さらに背中には重たそうな槌を背負っている。少なくとも、冒険者といえども女性が持つような代物ではない。リトは、目を丸くした。
「他に何に見えるっていうのよ。それとも、あたしがポロスやミルコに見える?」
唖然としたまま張り手を食らわされたリトには、突然の攻撃に対する戸惑いと怯えで、必死になってぶんぶんと首を横に振るのがやっとだった。ところが、そんなリトなどお構いなしに、ハティはシアの亡骸を見下ろす。
「犠牲者、か。見慣れたものね。大体、ここか魔女の場所なのよ」
慣れきってしまった事を克明に示す、冷たい声色。改めて、リトも彼女を見下ろす。血の気が戻って、ふと動き出すのではないかと思った。しかし、彼女はもう動かないし、息もしない。漆黒よりもなお暗い、死の世界へと旅立って、もう戻らないのだ。悲しい。視界が、涙で霞むほどに。
悲しみながらも、ようやく我に返ったリトは、視線を生きたもう一人の冒険者へと移した。一つ、訊きたい事があったからだ。
「一体、どうしてここへ?」
しかし、それには味気ない返事が返って来るだけだった。
「あんたが知る必要なんてないわよ」
少しむっとする言葉ではあったが、全く持って正論だった。そういえば、ついこの間、イアソンに「次に幸運は無い」と釘を刺されたばかりではなかったか。よくよく考えれば、今回もハティという人物という幸運に恵まれて、命を繋ぎ止められたのではないか。リトの心に、暗い自己嫌悪の情がにじみ出てくる。悔しい、何よりも、不甲斐ない。しかも、これが初めてではない。心の暗雲を押し出そうと、ひとりでに辛気臭い溜息が出た。
「……薬、探してんの」
はて、リトの言動を怒りと取ったのか。不意にハティがここにいる理由を呟いた。かろうじて聞いていたリトは、何とかそれをオウム返しに問う。
「く、薬?」
「そう、時々遺跡とかに転がってるでしょ? 昔からある、特別な薬。それを探しているの」
ハティはその先の闇を鋭く見据えながら、答えた。となれば、リトにもう一つ疑問が浮かぶ。何故、彼女が『薬』を欲するかだ。一見して悪いところはない。しかし、もしかして、もしかすると。リトは、逡巡の末、こう訊ねた。
「もしかして、ハティさん、何処か悪いの?」
無造作な質問に、容赦なく雷は落とされた。
「うっさいわねえ!あたしが病気に見える!? ビンセントのに決まってんでしょ!?」
「……ビンセント? ビンセントって、あの?」
リトが知る限り、ビンセント、と言えば、時折彼女と一緒に来て酒場で話す、華奢な緑髪の青年の名前である。彼が、どうかしたのだろうか。病気なのだろうか。友人の死を目の当たりにしたばかりだけあって、リトも不安でたまらなくなって、思わず訊ねた。その簡単な問いに、彼女は苦虫を噛み潰したような顔で、しばし答えを渋っていたが、その内に、その重い口を開いた。
「あいつ……持病、あんのよ。感染(うつ)らないけれど…結構、重い病気。普通の薬草では、治らない病気」
その返事は、大方リトの予想通りのものだった。
「知らなかった。彼は、元気そうだったから」
「振舞っているだけ。あいつは他の人が悲しむのが何より嫌いなのよ。バカみたいにお人好しだから」
ハティ曰く、最近目に見えて具合が悪くなってきているらしい。道理で、酒場に現れなかったのかと、リトも納得する。ハティは、辛そうに天井を見上げた。それから、シアの死を仲間に告げるために、折れた弓を拾い上げる。これで、彼女も同行者。これが死んだ友を見た時の、冒険者の慣わし。そうリトに教えながら。
「最近のあいつ、無理してばかりいて。発作とか……酷いくせにさ、昔っからそうなのよ。あたしに一生懸命付いて来ようとするの。留守番頼んでも」
しかし、彼について話す間は相も変わらず苛立ち混じり。それでも、彼女は独白を続ける。それに、リトが質問を織り交ぜて、一つの会話を成立させていく。二人の耳に入れば、後は暗がりの中に飲み込まれていくばかりの言葉の数々。それでも、一人よりかは幾分気が楽になった。人の病気の話をしているのに、不謹慎かとも思ったが、今のリトに、誰かとの会話は必要だった。止めてしまえば、今度こそ暗い世界に魂を連れて行かれそうだったから。
「ハティさんとビンセントって、一緒に住んでいるの?」
「アンタが来る前から、そうよ。あたしはよく冒険に出ているから、留守が多いけれど。料理は帰る頃に美味しいの、作ってくれていて……魔物にやられて切れた服だって、綺麗に直してくれているし……あたしがよく買い忘れるものも、ちゃんと…買ってくれていて」
と、ハティはリトと歩き出しながら、文句交じりに生活での出来事を羅列していく。その話から聞いていけば、彼は病人というよりも、むしろ何だか、がさつなハティを支援してくれる要領のいい主夫のような。その光景がありありと思い浮かばれて、リトは小さく微笑んだ。
「それでも、ハティさんは嫌なの?」
「鬱陶しいに決まってるじゃない!あいつ、自分の事なんかそっちのけで、あたしに余計なお節介ばっかり焼くんだから!」
彼女は案の定、その問いに大声で怒鳴った。周囲がざわめく。グリフォン達が、その殺気に気圧されたのか、魅入られたのか。リトも少し気圧されて、数歩後ずさる。あの時のタルバインも、こんな気持ちだったのだろうか。しかしながら、それ以上にリトが思案する前に、ハティは言った。
「でも、いなくなったら、悲しいわよ。あたしだって、一人は嫌だもの」
次に彼女の口を突いて出たこの言葉に、リトは思わず微笑みを大きくした。普段の刺々しい彼女の言動からすれば、とても温かく、柔らかい言葉だったからだ。そのリトの顔を見、不満の色を顔面一杯に浮かべたハティが、さらに語調を荒くする。
「ちょ、ちょっと!何よ、その顔は!」
「ご、ごめん。俺、ハティさんって、もっと怖い人かと思っていたんだ。ビンセント、苦労してるんじゃないかと」
慌てて謝るリトの顔を、疑うような目で彼女は長らく見ていたが、やがて諦めたように息を付き、居所が悪かったらしい槌を、背負い直した。
「……馬鹿。本当に鬱陶しかったら……あいつのために薬探しなんてしないに決まってるじゃない」
リトにも、ほっとした笑みが浮かぶ。ハティも本当に諦めて、首を横に振りながら、もう一度だけ息を付いた。
「何だかんだで、あたしも彼には助けられてるの。だから……願いの一つくらい、叶えてあげたいじゃない」
「ビンセントの、願いって?」
そのリトの問いかけに、かすかに頬を朱に染めて、彼女はそっぽを向き、彼女らしからぬ小声で答えた。
「あたしと一緒に遠くまで冒険がしたいんだって。あいつ、そういう理由で近場しか行けないから」
なるほど、彼の願いそうな願いだ。呑気に納得する彼の横で、武具のついた拳を壁に食い込むほどに強く打ち付けて、ハティは苛立たしげに言葉を漏らした。
「だから、急がなきゃならないの。あいつが病気に殺されるより早く、あたしがとっておきの薬を見つけて、元気にしてやるんだから……!」
そして、俯き加減にリトに言うでもなく、独白を繋ぐ。しかし、リトは彼女の言葉に耳を傾けていた。それとなく、聞かなければならないような気になっていて。
「だけど、『それまで頑張っていて』って無責任な言葉は、言えない。そんな所ばっかり気弱で……心底、嫌になるのよ」
みしり、と壁から音がした。よほど脆くなっていたのだろう、彼女の沈黙を代弁し、ぱらぱらと壁の破片がむなしく落ちる。リトはといえば、自己嫌悪に陥っていた自分と、今の彼女が重なって見えて、何とかしなければという気持ちになったのだろう。苛立ち続けるハティに、声を掛けた。
「ビンセントなら、言わなくても、きっと笑って頷くと思う。見ている限り、彼は誰にでも優しいから」
「ふん、勝手に推測しないでよ……っ、どうしてくれるの!その顔がはっきり思い浮かんじゃったじゃない!!」
リトの言葉に、少しだけ震える声で、ハティは抗議した。前半は一人ごちるように、後半ははっきりとリトに立ち向かって。その顔は、耳まで真っ赤だった。
神殿という、危険な場所なのに。何故か、小さくても笑ってしまった。酒場の中の、優しい空気の中のように。グリフォン達はここにいるというのに。また、自分たちを襲いに来るというのに。穏やかな笑いが止まらない。隣に誰かいる事が、こんなに安心出来る事だったとは。そういえば、今休ませているファルが隣にいた時も、同じ気持ちを抱いていたのだ。すぐ側にある温もりが、どれほど愛しいものか。リトは、ようやく解った気がした。心の何処かで、懐かしい誰かをおぼろげに思い出しながら。
それからしばらくお互い考え事にふけっていたが、ややあった後に、先に口を開いたのはハティだった。
「……リト、だったわね」
「な、何か?」
再び、衝撃で冷えた心を温め直していたリトだったが、その言葉で思い出したように硬直し、一歩下がって身構える。取って食いはしないわよ、とぶっきらぼうに返し、ハティは自分とリトの武器へと交互に目をやった。
「いー兄さんが言っていなかった? 誰かと出会ったら、一緒に行動して生存率を上げろって」
リトも、それに気付いて、ああ、と納得したように頷く。その気楽な仕草の彼に向けて、ハティは片手を差し出した。リトは、不思議そうに手から視線を伝わせて彼女の顔を見る。彼女は、未だ解っていないリトに、言葉を付け足した。
「薬探しついでに、条件付きだけど、あんたの手伝いしたげる。付いて来たければ、付いて来て。ここは詳しいから」
「条件付き?」
ハティが、リトの言葉に頷く。条件だけなら聞いても問題ないかと、リトはその条件について訊ねたところ、ハティは少し恥かしげにリトを見返しながら、その条件を告げてくれた。何、その条件は、とても簡単なもので。聞いた時には、リトの心は、すっかり温もりを取り戻していた。
とどのつまり。それは「ビンセントは無駄な心配をするから、酒場で会っても今の話を絶対するな」という、とても簡単で不器用な。優しい、約束だったのだ。
Last Update:
2005-06-30
Written by 皆川 新茶
Edited by ダイス
Powered by PHP
Powered by Lolipop